NHKでも話題になった障害者同士のいじめ。
- その実態
- 背景
- 支援の必要性
- 具体的な対策
コミュニケーションの難しさや閉鎖的な環境、社会の偏見など、様々な要因が複雑に絡み合い、いじめが発生している現実を理解し、私たち一人ひとりができることを考えましょう。
障害者同士のいじめとは何か

障害者同士のいじめは、障害を持つ人同士の間で起こる、身体的・精神的・社会的な苦痛を与える行為です。
健常者間のいじめと同様に深刻な問題であり、当事者の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
多くの場合、周囲の理解不足や支援の不足により、隠れた問題として扱われがちです。そのため、実態把握と適切な対策が急務となっています。
障害者同士のいじめの定義
障害者同士のいじめは、一方の障害者が、もう一方の障害者に対して、継続的に身体的・精神的・社会的な苦痛を与える行為を指します。
- 暴言・暴力
- 無視・仲間外れ
- 悪口・陰口
- 金銭の要求
- 性的ないたずら
など
これらの行為は、直接的なものだけでなく、インターネット上での誹謗中傷といった間接的なものも含みます。
障害者同士のいじめの特徴
障害者同士のいじめは、健常者間のいじめとは異なるいくつかの特徴があります。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| コミュニケーションの困難さ | 言葉によるコミュニケーションが難しい場合、誤解が生じやすく、それがいじめにつながるケースがあります。また、自分の気持ちをうまく伝えられないことで、不満が蓄積し、攻撃的な行動に出てしまう場合もあります。 |
| 依存関係の発生 | 日常生活で介助が必要な場合、加害者は被害者への介助を担っている場合があり、その関係性を利用したいじめが発生する可能性があります。 被害者は支援を失うことを恐れ、いじめを訴えられない状況に陥ることがあります。 |
| 閉鎖的な環境 | 障害者支援施設や特別支援学校など、特定の環境に限定された人間関係の中でいじめが発生すると、逃げ場がなく、深刻な状況になりやすいです。 また、周囲の大人も気づきにくいという問題点があります。 |
| 障害特性の利用 | 加害者は被害者の障害特性を理解しており、それを利用した巧妙ないじめを行う場合があります。 例えば、聴覚障害のある人に聞こえないように悪口を言ったり、知的障害のある人に嘘の情報を吹き込んだりするといったケースです。 |
| 発見の難しさ | 被害者が自身の被害を訴えることが困難な場合や、周囲が障害特性による行動と誤解してしまうケースがあり、発見が遅れがちです。 また、いじめを訴えても、障害特性ゆえの行動と捉えられ、真剣に取り合ってもらえない可能性もあります。 |
障害者同士のいじめの事例

ここでは、具体的な事例をいくつか紹介し、そこから見える問題点について解説します。
具体的な事例紹介
事例①
肢体不自由のある生徒が、同じ特別支援学級の知的障害のある生徒から、日常的に暴言や暴力を受け、学校生活に支障をきたしていた事例。
加害生徒は、自分の気持ちをうまく伝えられない苛立ちから、いじめ行為に及んでいた。
事例②
聴覚障害のある生徒が、同じろう学校に通う生徒から、手話での悪口や仲間外れなどのいじめを受けていた事例。
いじめの背景には、聴覚障害者コミュニティ内での特有の力関係やコミュニケーションの難しさがあった。
事例③
視覚障害のある生徒が、同じ盲学校に通う生徒から、点字教材を隠されたり、歩行訓練中に意図的につまづかされたりするなどのいじめを受けていた事例。
加害生徒は、視覚障害の程度の違いによる優越感から、いじめ行為に及んでいた。
事例から見える問題点
これらの事例から、障害者同士のいじめには以下のような問題点が見えてきます。
- コミュニケーションの難しさ:
障害特性によるコミュニケーションの困難さが、誤解や摩擦を生み出し、いじめにつながるケースがある。 - 閉鎖的な環境:
特別支援学校や障害者施設など、閉鎖的な環境では、いじめが表面化しにくく、エスカレートする危険性がある。 - 周囲の理解不足:
障害特性やいじめのサインに対する周囲の理解不足により、適切な対応が遅れることがある。 - 支援体制の不備:
いじめへの対応や、被害者・加害者への適切な支援体制が整っていない場合がある。 - 複合的な要因:
いじめは、単一の要因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生していることが多い。
これらの問題点を踏まえ、障害者同士のいじめに対して、より効果的な対策を講じる必要があります。
障害者同士のいじめが発生する背景

障害者同士のいじめは、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。
共通の困難を抱えているからこそ理解し合えるという期待とは裏腹に、なぜこのような悲しい現実が起こるのでしょうか。
ここでは、障害者同士のいじめが発生する背景にある要因を、いくつかの観点から詳しく見ていきます。
コミュニケーションの難しさ
多くの障害は、コミュニケーションに困難を伴います。
視覚、聴覚、知的、精神、発達など、障害の種類によってコミュニケーションの方法は様々であり、互いの意思疎通が難しい場合があります。
このようなコミュニケーションの行き違いが、誤解や摩擦を生み、いじめにつながる可能性があります。
また、自分の障害特性を相手に理解してもらえず、辛さを抱えている人もいます。
閉鎖的な環境の影響
障害のある人は、健常者に比べて活動範囲が狭く、特定の施設やグループに所属している場合が多いです。
このような閉鎖的な環境は、人間関係が固定化されやすく、いじめが発生した場合、逃げ場がなく深刻化しやすいという問題があります。
また、限られた人間関係の中で、力関係の偏りが生じやすく、弱い立場の人が標的にされる可能性も高まります。
施設やグループ内でのルールや規範が、個々の障害特性に合っていない場合も、ストレスや不満につながり、いじめを誘発する可能性があります。
社会からの偏見や差別の影響
社会全体に根強く残る障害者への偏見や差別も、障害者同士のいじめの背景にあると考えられます。
健常者中心の社会構造の中で、障害のある人は自己肯定感を持ちにくく、劣等感を抱えやすい傾向があります。
このような心理状態は、他者への攻撃やいじめという形で現れる可能性があります。
互いに支え合うべき存在であるにも関わらず、偏見や差別の影響を受けて、競争意識や嫉妬心が芽生え、いじめにつながるケースも少なくありません。
これらの要因は単独で作用するのではなく、複雑に絡み合い、障害者同士のいじめの温床となっています。
障害者同士のいじめにどう対処すべきか

障害者同士のいじめは、複雑な問題であり、その対処には慎重さと多角的なアプローチが必要です。
早期発見と適切な対応が、被害者の更なる苦痛を防ぎ、加害者の更生を促す上で非常に重要です。
周囲の理解と協力が不可欠です。
いじめの早期発見の重要性
障害者同士のいじめは、表面化しにくく、発見が遅れるケースが多く見られます。
そのため、早期発見のための意識的な取り組みが重要です。
普段からのコミュニケーションを密にする、些細な変化も見逃さない注意深い観察、そして信頼関係を築くことで、いじめを早期に発見できる可能性が高まります。
以下に、いじめの兆候を示すサインをまとめました。
これらのサインに気づいたら、注意深く観察し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
| 行動の変化 | 身体的兆候 | 心理的兆候 |
|---|---|---|
| 特定の人物を避けるようになる グループから孤立する 施設への行き渋り | 不眠 食欲不振 原因不明の体調不良 | 不安感の増加 自尊心の低下 情緒不安定 |
いじめのサインを見つけた時の対応
いじめのサインを見つけた時は、まず事実確認を行いましょう。
当事者から話を聞く際には、安全な場所を確保し、落ち着いて話を聞くことが大切です。
一方的な決めつけや責めるような態度は避け、安心して話せる環境を作るよう心がけてください。
周囲のサポートの必要性
障害者同士のいじめは、当事者だけで解決することは困難です。
周囲の理解とサポートが不可欠です。
支援者、家族、施設職員、そして社会全体が連携し、いじめを許さない環境づくりに取り組むことが重要です。
周囲ができるサポート
- 当事者の話を丁寧に聞き、共感する
- いじめに関する相談窓口の情報提供
- 関係機関との連携
- 施設内での啓発活動の実施
- いじめの再発防止策の検討と実施
障害特性を理解し、適切なコミュニケーション方法を学ぶことも重要です。
例えば、知的障害のある方には、簡単な言葉で説明したり、視覚的な資料を用いたりすることで、理解を深めることができます。
聴覚障害のある方には、筆談や手話通訳などを活用することで、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。
いじめの被害者への支援
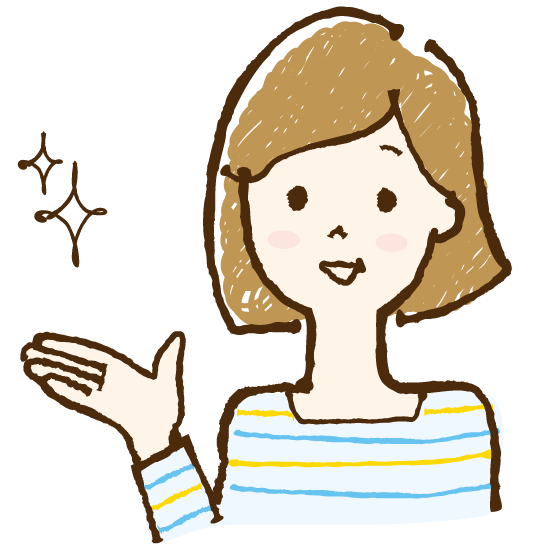
障害のある方がいじめの被害を受けた場合、心身に深い傷を負う可能性があります。
そのため、早期の発見と適切な支援が不可欠です。
被害者への支援は以下の点を重視する必要があります。
相談窓口の活用
一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが重要です。
相談することで、精神的な負担を軽減し、解決策を見つける糸口になります。
下記のような相談窓口を活用しましょう。
| 相談窓口 | 電話番号 | 対応時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| よりそいホットライン | 0120-279-338 | 24時間対応 | 自殺予防、精神的な悩みの相談 |
| 子どもの人権110番 | 0120-007-110 | 平日8:30~17:15 | いじめ、虐待など子どもの人権に関する相談 |
| みんなの人権110番 | 0570-003-110 | 平日8:30~17:15 | あらゆる人権問題に関する相談 |
| 障害者虐待防止センター | 各都道府県に設置 | 各自治体により異なる | 障害者虐待に関する相談 |
上記以外にも、各地方自治体や障害者支援団体などが相談窓口を設けている場合があります。
地域の相談窓口の情報も積極的に活用しましょう。
心理的なケアの重要性
いじめの被害は、被害者の自尊心を傷つけ、不安や抑うつ状態を引き起こす可能性があります。
そのため、心理的なケアが非常に重要です。
専門家によるカウンセリングやセラピーを受けることで、心の傷を癒し、回復への道を歩むことができます。
いじめの加害者への支援

いじめの加害者への支援は、いじめ問題の解決、そして再発防止のために非常に重要です。
加害者自身もまた、何らかの困難を抱えている場合があり、その背景にある問題を理解し、適切な支援を行う必要があります。
安易な罰則を与えるだけでは根本的な解決にはならず、加害者自身の成長を促し、社会全体でいじめをなくしていくためには、加害者への支援も不可欠です。
背景にある問題の理解
障害のある加害者がなぜいじめを行うのか、その背景には様々な要因が考えられます。
- 自己肯定感の低さ:自身の障害に対する劣等感や、周囲からの偏見などにより、自己肯定感が低く、他者を攻撃することで優位に立とうとする。
- コミュニケーション能力の不足:自分の気持ちを適切に表現できなかったり、相手の気持ちを理解することが難しく、結果としていじめにつながる。
- 周囲の環境の影響:家庭環境の問題や、学校などでの人間関係のトラブルなどが、いじめにつながる要因となる場合もある。
- 障害特性による影響:発達障害など、特定の障害特性により、衝動性をコントロールすることが難しく、いじめにつながるケースもある。ただし、すべての発達障害のある方がいじめを行うわけではなく、あくまでも一つの要因として理解する必要がある。
加害者への支援を行う際には、まずこれらの背景にある問題を丁寧に理解することが重要です。
そのためには、加害者本人との面談だけでなく、家族や学校関係者など、周囲の人々からの情報収集も必要となります。
適切な指導と教育
加害者への指導と教育は、いじめの再発防止のために不可欠です。
罰則を与えるだけでなく、加害者自身の成長を促すような支援が必要です。
具体的には、以下のような方法が考えられます。
| 支援方法 | 内容 |
|---|---|
| アンガーマネジメント教育 | 怒りの感情をコントロールする方法を学ぶことで、衝動的な行動を抑制する。 |
| ソーシャルスキルトレーニング | 適切なコミュニケーション方法や、他者との関わり方を学ぶことで、円滑な人間関係を築けるようにする。 |
| ピアサポート | 同じような困難を抱える仲間との交流を通して、共感性や社会性を育む。 |
| 心理カウンセリング | 専門家によるカウンセリングを通して、自己肯定感を高め、心の健康を回復する。 |
これらの支援は、加害者の年齢や発達段階、障害特性などを考慮しながら、適切な方法を選択する必要があります。
また、学校や家庭、関係機関が連携して、継続的な支援を行うことが重要です。
障害者同士のいじめを防ぐための対策

障害者同士のいじめを防ぐためには、個人への支援だけでなく、社会全体の意識改革や環境整備が必要です。
特に、教育現場や福祉施設といった障害のある人が多く集まる場においては、積極的な取り組みが求められます。
以下、具体的な対策を挙げます。
インクルーシブ教育の推進
インクルーシブ教育とは、障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ教育のことです。
多様な個性を受け入れる土壌を育み、相互理解を深めることで、いじめを未然に防ぐ効果が期待できます。
具体的には、以下の取り組みが重要です。
合理的配慮の提供
個々のニーズに合わせた学習環境や支援を提供することで、障害のある子どもが学習に参加しやすくなり、自信や自己肯定感を高めることができます。
これにより、いじめの標的になりにくい環境を作ることができます。
共に学ぶための教材・カリキュラムの開発
障害の有無に関わらず、すべての子どもが共に学べる教材やカリキュラムを開発することで、相互理解を促進し、いじめに対する意識を高めることができます。
教職員の研修の実施
インクルーシブ教育に関する教職員の知識・技能向上のための研修を実施することで、適切な支援や指導を行うことができます。
社会全体の理解促進
障害者に対する理解不足は、偏見や差別につながり、いじめの温床となる可能性があります。
社会全体の理解を促進するためには、以下の取り組みが重要です。
啓発活動の実施
講演会やイベント、メディアなどを活用した啓発活動を通じて、障害に対する正しい知識や理解を広めることが重要です。
特に、障害のある人の体験談や思いを伝えることで、共感や理解を深めることができます。
メディアによる適切な情報発信
テレビや新聞、インターネットなどのメディアは、障害のある人をステレオタイプなイメージで描写するのではなく、多様な姿を伝えることで、偏見の解消に貢献できます。
地域社会との連携
地域住民向けの交流イベントや、障害のある人が地域活動に参加しやすい環境づくりを通じて、相互理解を深め、インクルーシブな社会の実現を目指します。
相談しやすい環境づくり
いじめが発生した場合、早期発見・早期対応が重要です。
そのためには、相談しやすい環境づくりが不可欠です。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 相談窓口の設置と周知 | 学校や福祉施設、地域に相談窓口を設置し、その情報を広く周知することで、いじめに関する相談をしやすくします。 |
| 相談員の育成 | 相談を受けた際に適切な対応ができるよう、相談員の育成に力を入れる必要があります。 |
| ピアサポートの活用 | 同じ障害を持つ仲間同士で支え合うピアサポートは、相談しやすい環境づくりに役立ちます。 |
これらの対策を総合的に推進することで、障害者同士のいじめを減らし、誰もが安心して過ごせる社会の実現を目指していく必要があります。
関連団体・相談窓口一覧
障害者同士のいじめに関する相談や支援を行っている主な団体・相談窓口を以下にまとめました。
困難を抱えている方、またはその周囲の方は、一人で抱え込まずに、これらの窓口に相談することをお勧めします。
いじめに関する相談窓口
| 団体名 | 電話番号 | ウェブサイト | 対応内容 |
|---|---|---|---|
| 子どもの人権110番(文部科学省) | 0120-0-78310 | https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html | 子どもの人権に関する相談全般(いじめを含む) |
| よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター) | 0120-279-338 | https://www.since2011.net/yorisoi/ | 様々な悩みを抱える人への相談支援 |
| いのちの電話 | 地域によって異なります。https://www.inochinodenwa.org/からご確認ください。 | https://www.inochinodenwa.org/ | 自殺予防のための相談 |
障害者支援に関する相談窓口
| 団体名 | 電話番号 | ウェブサイト | 対応内容 |
|---|---|---|---|
| 日本司法支援センター(法テラス) | 0570-078374 | https://www.houterasu.or.jp/ | 法的トラブルに関する相談、弁護士・司法書士の紹介 |
| 都道府県・市区町村の障害者相談支援センター | お住まいの地域によって異なります。 | 障害に関する相談全般 |
上記以外にも、各都道府県や市区町村には、障害者支援に関する様々な相談窓口が設置されています。
お住まいの地域の窓口をご確認ください。
まとめ
障害者同士のいじめは、コミュニケーションの難しさや閉鎖的な環境、社会からの偏見など様々な要因が複雑に絡み合って発生します。
各種調査などを通して、その深刻な実態が明らかになりつつあります。
早期発見、周囲のサポート、被害者・加害者双方への適切な支援が重要です。
インクルーシブ教育の推進や社会全体の理解促進など、根本的な解決に向けた取り組みも必要不可欠です。
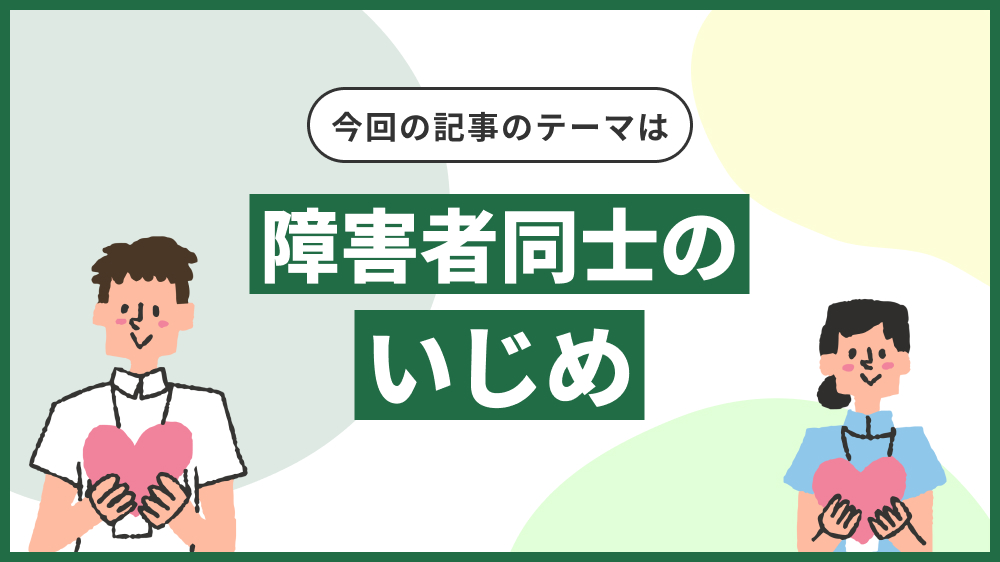









コメント