「障害者 うざい」と感じるのはなぜか、その背景にある心理や状況を理解し、適切な対処法を学びませんか?
この記事では、具体的な事例を通して「うざい」という言葉の持つ意味や無意識の偏見について解説。
多様性を受け入れる社会の実現に向け、共感性を育み、障害者と本音で付き合うための方法を紹介します。
障害者への偏見と差別について

「障害者 うざい」と検索する背景には、障害者に対する偏見や差別意識が存在する可能性があります。
この章では、「うざい」という言葉が持つ意味や、無意識のうちに抱いている偏見について考え、障害のある人と共存する社会の実現に向けて、私たちが持つべき意識について探っていきます。
「うざい」という言葉が持つ意味
「うざい」という言葉は、一般的に「煩わしい」「邪魔だ」「鬱陶しい」といったネガティブな感情を表す俗語です。
この言葉が障害者に向けられるとき、そこには障害そのものへの嫌悪感だけでなく、障害のある人が社会生活を送る上で生じる様々な状況に対する不理解や苛立ちが込められている場合が多いと考えられます。
例えば、公共交通機関での移動に時間がかかったり、コミュニケーションに困難が生じたりする場面を目の当たりにした際に、「うざい」と感じてしまうことがあるかもしれません。
 編集長
編集長しかし、このような感情の背景には、障害に対する偏見や差別意識が潜んでいる可能性があることを認識することが重要です。
無意識の偏見に気づく
私たちは、日常生活の中で無意識のうちに偏見を抱いていることが多々あり、障害者に対する偏見も例外ではありません。
例えば、「障害者は特別な配慮が必要な存在である」「障害者は健常者と同じように生活することはできない」といった固定観念は、無意識の偏見の表れと言えるでしょう。
このような偏見は、障害のある人に対する差別的な言動につながる可能性があります。
障害者と適切に関わるための方法


障害のある方と適切に関わることは、共生社会の実現に向けて非常に重要です。
ここでは、困っている障害者を見かけた時の対処法、コミュニケーションを取る上でのポイント、公共の場でのマナーについて解説します。
困っている障害者を見かけた時の対処法
困っているように見える障害者を見かけた時、まずは「何かお手伝いできることはありますか?」と優しく声をかけましょう。
ただし、必要以上に介入したり、勝手に判断して行動したりすることは避け、本人の意思を尊重することが大切です。
例えば、視覚障害者の方には、行きたい場所を尋ね、安全に誘導する、聴覚障害者の方には、筆談や身振り手振りでコミュニケーションを取るなど、障害の種類に合わせた対応を心がけましょう。



また、状況によっては、駅員や店員など周囲のスタッフに協力を求めることも有効です。
コミュニケーションを取る上でのポイント
障害のある方とコミュニケーションを取る際には、以下のポイントに留意しましょう。
| 状況 | ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 視覚障害者 | 周囲の状況を言葉で伝える | 「右手に階段があります」「3メートル先に信号があります」 |
| 聴覚障害者 | ゆっくり、はっきり話す。 筆談ツールを活用する。 | 口元を隠さず、相手に伝わるように話す。 スマートフォンのメモ機能や筆談アプリを使う。 |
| 知的障害者 | 簡単な言葉で話す。 状況を具体的に説明する。 | 「こっちに並んでください」「このボタンを押すとエレベーターが来ます」 |
| 肢体不自由者 | 目線を合わせる。 本人のペースに合わせて行動する。 | 車いすの方と話す際は、しゃがんで目線を合わせる。 |
| 精神障害者 | 落ち着いて、穏やかに接する。 | 突然の行動変化があっても、慌てず対応する。 |
公共の場でのマナー
公共の場では、障害のある方が安心して過ごせるよう、以下のマナーを心がけましょう。
- 優先席は必要としている方に譲りましょう。
混雑時だけでなく、空席があっても譲る配慮が大切です。 - エレベーターやエスカレーター付近では、邪魔にならないように配慮しましょう。
- 盲導犬や介助犬、聴導犬には、触ったり、話しかけたりせず、静かに見守りましょう。
許可なく写真を撮ることも控えましょう。 - 障害者用トイレや駐車場は、必要としている方が優先的に利用できるようにしましょう
これらの知識とマナーを身につけることで、障害のある方とよりスムーズで円滑なコミュニケーションを図り、共生社会の実現に貢献することができます。
様々なサポート体制を知る


障害のある方が安心して暮らせるよう、様々なサポート体制が整えられています。
行政によるサービスから民間団体による活動、相談窓口まで、幅広い支援が存在します。
自分に合った、あるいは困っている方に合ったサポートを見つけることが重要です。
行政の支援サービス
国や地方自治体では、障害のある方への様々な支援サービスを提供しています。
代表的なものとしては、障害者手帳の交付、自立支援医療制度、障害年金、特別障害者手当、介護給付などがあります。
これらの制度は、障害のある方の生活を経済的、医療的、福祉的に支えるためのものです。
| サービス | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 障害者手帳 | 様々なサービスを受けるための資格証明書。等級に応じてサービス内容が異なる。 | 身体障害、知的障害、精神障害のある方 |
| 自立支援医療(更生医療) | 医療費の自己負担を軽減する制度。 | 身体障害、知的障害のある方 |
| 精神通院医療 | 医療費の自己負担を軽減する制度。 | 精神障害のある方 |
| 障害年金 | 障害のある方の生活を経済的に支えるための年金制度。 | 一定の障害等級のある方 |
| 特別障害者手当 | 在宅の重度の障害のある方に支給される手当。 | 20歳以上の重度の障害のある方 |
| 介護給付 | 日常生活に介護が必要な方に、訪問介護や通所介護などのサービスを提供。 | 要介護認定を受けた方 |
民間団体の活動
様々な民間団体が、障害のある方の支援活動を行っています。
例えば、日本障害者協議会(https://www.jdp.jp/)は、障害者団体の中央組織として、障害のある方の権利擁護や社会参加促進に取り組んでいます。
また、DPI日本会議(https://www.dpi-japan.org/)は、障害当事者による団体で、自立生活運動を推進しています。
相談窓口の活用
障害に関する相談窓口も複数存在します。
各自治体の障害福祉課や保健所、地域障害者相談支援センターなどが、相談に応じてくれます。
また、電話相談サービスも利用可能です。
障害者と「本音」で付き合うために


障害のある方と「本音」で付き合うことは、共生社会の実現に向けて非常に重要です。
しかし、どのように接すれば良いのか、戸惑いを感じる方もいるかもしれません。
本音で付き合うとは、表面的な優しさではなく、お互いを尊重し、理解しようと努める姿勢を持つことです。



それは時に、難しい課題や葛藤を伴う場合もありますが、真の共存のためには不可欠なプロセスです。
お互いを理解するための歩み寄り
障害のある方の置かれている状況や気持ちを理解しようと努めることが大切です。
例えば、視覚障害のある方にとって、音声案内や点字は重要な情報源となり、聴覚障害のある方にとっては、手話や筆談がコミュニケーションの手段となります。
それぞれの障害特性を理解することで、適切なサポートやコミュニケーション方法が見えてきます。
同時に、障害のある方も、自身の状況や気持ちを伝える努力が必要です。
「うざい」と感じた時の適切な行動
「うざい」と感じてしまった時、まずはその感情を否定せずに受け止めましょう。
そして、なぜそう感じたのか、自分の内面と向き合ってみることが重要です。
その上で、感情的に反応するのではなく、冷静に状況を判断し、適切な行動を選びましょう。
例えば、公共交通機関で困っている障害のある方を見かけたら、声をかけずに席を譲る、手助けが必要そうであれば「お手伝いしましょうか?」と声をかける、といった行動が考えられます。
一方的に「うざい」と決めつけるのではなく、相手への配慮を忘れずに、冷静な対応を心がけましょう。
| 状況 | 適切な行動 | 避けるべき行動 |
|---|---|---|
| 電車内で車椅子の方が乗車するのに手間取っている | 「お手伝いしましょうか?」と声をかける、周りの人に協力を呼びかける | 見て見ぬふりをする、舌打ちをする |
| お店で視覚障害のある方が商品を探している | 「何かお探しですか?」と声をかける、商品棚まで案内する | 邪魔そうに避ける、大きな声で話す |
| 聴覚障害のある方とコミュニケーションが取りづらい | 筆談アプリを使う、ゆっくりと話す、ジェスチャーを使う | 大声で話す、諦めて無視する |
より良い共存社会を目指して
障害のある方と「本音」で付き合うことは、より良い共存社会の実現に繋がります。
障害者差別解消法(※)では、障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています。
合理的配慮とは、障害のある方が社会生活を送る上で、他の人と同じように生活できるようにするための必要な変更や調整のことです。
私たち一人ひとりが、障害のある方の立場を理解し、共に生きる社会を目指していくことが重要です。
まとめ
「障害者 うざい」と感じるのは、行き違いや無理解からくる場合が多いです。
何が「うざい」のかを具体的に理解し、背景にある偏見や差別についても認識することが大切です。
困っている障害者を見かけた際は、適切なサポートを心がけ、コミュニケーションのポイントを押さえましょう。
自身の感情を否定せず、共感性を育み、行政や民間団体の支援サービスも活用しながら、より良い共存社会を目指しましょう。
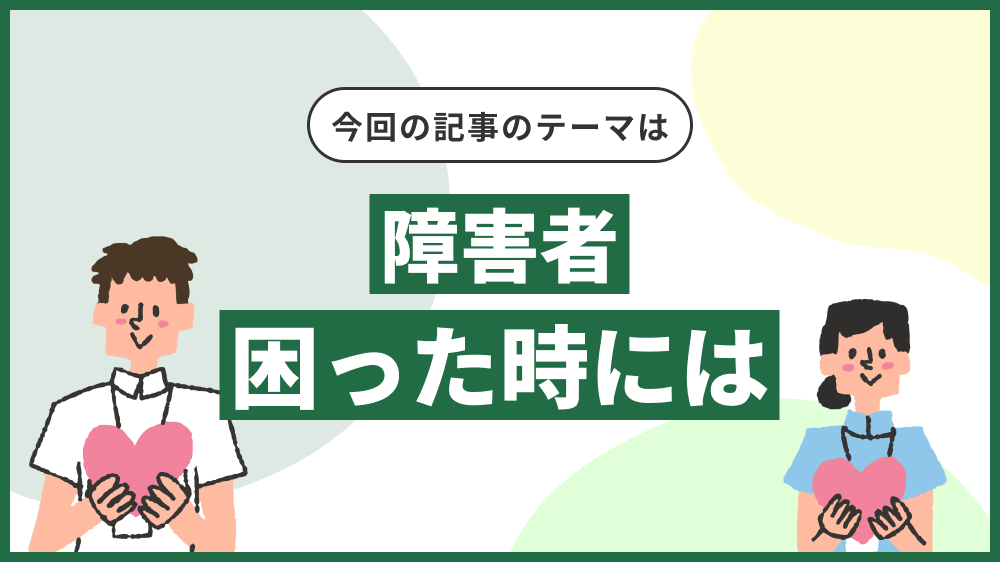









コメント