老人ホーム入居の挨拶に菓子折りは必須ではありませんが、感謝を伝えるため用意するのがおすすめです。
この記事では、失敗しない選び方のポイントから相場、のしの書き方、おすすめ品まで徹底解説します。
老人ホーム入居の挨拶に菓子折りは必要?
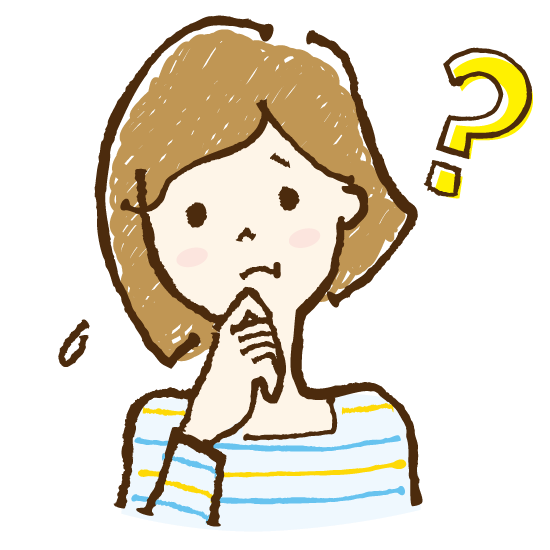
老人ホームへの入居は、ご本人にとってもご家族にとっても、新しい生活のスタートです。
その第一歩として、「お世話になる施設の方々へ挨拶の品として菓子折りは必要なのだろうか?」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、菓子折りは必ずしも必須ではありません。
感謝の気持ちを伝えるために用意するのがおすすめ
菓子折りをお渡しする一番の目的は、「これからお世話になります。どうぞ、よろしくお願いいたします」という感謝と挨拶の気持ちを形にして伝えることです。
スタッフの方々は、大切な家族のケアを日々行ってくれるパートナーです。
最初の挨拶を丁寧に行うことで、ご家族の誠意が伝わり、施設側も安心してご本人を迎え入れることができます。
 編集長
編集長円滑なコミュニケーションの第一歩として、菓子折りは非常に有効なツールと言えるでしょう。
菓子折りは誰に渡すべきか
菓子折りを用意した場合、次に悩むのが「誰に渡せばよいのか」という点です。
渡す相手によって目的や注意点が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
まずは施設長やスタッフの代表者へ
基本的には、施設全体への挨拶として、施設長やケアマネージャー、相談員といった代表者の方へお渡しするのが最も一般的です。
入居手続きの際などに、「皆様で召し上がってください」と一言添えてお渡しするとスムーズです。
特定のスタッフ個人に渡すのではなく、スタッフステーション(職員室)で皆さんが分け合えるように、施設全体への贈り物とするのがマナーです。



これにより、日々のケアに関わるすべてのスタッフへ感謝の気持ちを伝えることができます。
他の入居者様へ配る場合は事前に施設へ確認を
「これからご近所付き合いが始まる他の入居者様にも挨拶した方が良いのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、他の入居者様へ菓子折りを配る際は、必ず事前に施設側へ確認が必要です。
高齢者施設には、様々な健康状態の方が入居されています。
- 食事制限:
糖尿病や腎臓病などの持病により、食事制限を受けている方がいます。
- アレルギー:
特定の食品にアレルギーがある方も少なくありません。
- 嚥下(えんげ)機能:
食べ物を飲み込む力が低下している方にとって、お菓子の硬さや形状が誤嚥(ごえん)のリスクにつながる可能性があります。
- 公平性:
特定の個人から品物を受け取ることを禁止し、入居者間のトラブルを未然に防ぐ方針の施設もあります。



良かれと思って行ったことが、かえってご迷惑になったり、トラブルの原因になったりすることを避けるためにも、自己判断で配るのは絶対にやめましょう。
施設によっては菓子折りを受け取れない場合もあるので注意
近年、コンプライアンス(法令遵守)や衛生管理の観点から、外部からの差し入れや贈り物を一切辞退する方針の老人ホームも増えています。
これは、職員と利用者家族との間で金品の授受を禁止し、サービスの質を公平に保つためのルールです。
せっかく用意した菓子折りを受け取ってもらえないと、気まずい思いをするかもしれません。



そうした事態を避けるためにも、見学時や契約時、あるいは入居日前の電話連絡の際に、「入居の際、皆様へのご挨拶の品をお持ちしてもよろしいでしょうか?」とさりげなく確認しておくのが最も確実な方法です。
| 渡す相手の候補 | 判断のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 施設長・スタッフ代表者 | 施設全体への挨拶として渡すのが一般的。 | 「皆様でどうぞ」と一言添える。スタッフ全員に行き渡るよう、個包装で数の多いものが喜ばれる。 |
| 他の入居者 | 原則として自己判断で渡さない。 | 必ず事前に施設へ相談・確認する。アレルギー、食事制限、誤嚥リスク、公平性の問題があるため、禁止されていることが多い。 |
失敗しない老人ホーム向け菓子折りの選び方 5つのポイント


老人ホームへの入居挨拶で渡す菓子折りは、感謝の気持ちを伝える大切な贈り物です。
しかし、誰に、どのようなものを贈れば良いか悩む方も多いでしょう。
スタッフの方々や他の入居者様に喜んでいただくためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
ポイント1 日持ちがして常温で保存できるもの
菓子折りを選ぶ上で最も重要なポイントの一つが、日持ちがして常温で保存できることです。
老人ホームのスタッフは日々の業務で非常に忙しく、いただいた菓子折りをすぐに開封できるとは限りません。
また、施設の冷蔵庫や冷凍庫は、入居者様の食事や薬などを保管するために使われており、スペースに限りがあります。



そのため、賞味期限が少なくとも1ヶ月以上あり、直射日光を避けて常温で保管できる焼き菓子やせんべい、羊羹などを選ぶのがマナーです。
ポイント2 スタッフが分けやすい個包装タイプ
菓子折りは、スタッフの方々が休憩時間などに手軽につまめるよう、個包装になっているものを選びましょう。
一本もののカステラやホールのケーキなどは、切り分けるために包丁やお皿を用意する必要があり、忙しい業務の合間では手間になってしまいます。
個包装であれば、手を汚さずに衛生的に分け合うことができ、休憩室などに置いておけば各自が好きなタイミングで受け取れます。



スタッフの人数は施設によって様々ですが、少し多めの個数が入った詰め合わせを選ぶと「足りなかったらどうしよう」という心配もありません。
ポイント3 高齢者でも食べやすい柔らかいお菓子
菓子折りを召し上がる方の中には、ご高齢のスタッフや他の入居者様もいらっしゃることを忘れてはいけません。
年齢を重ねると、噛む力(咀嚼機能)や飲み込む力(嚥下機能)が低下している方が多くなります。
硬すぎるお菓子は、歯を痛めたり、喉に詰まらせたりする危険性があるため避けるのが賢明です。



具体的には、硬いせんべいやナッツがぎっしり詰まったフロランタン、歯にくっつきやすいキャラメルなどは避け、カステラやバウムクーヘン、どら焼き、ボーロ、ゼリー、水ようかんといった、柔らかく口溶けの良いお菓子がおすすめです。
ポイント4 アレルギーや健康に配慮した原材料
多くの方が口にする可能性があるため、アレルギーや健康状態への配慮も欠かせません。
スタッフや入居者様の中には、特定の食物アレルギーをお持ちの方や、糖尿病などの持病で食事制限をされている方がいる可能性も考慮しましょう。
購入の際には、アレルギー表示がはっきりと記載されている商品を選ぶことが大切です。



特に、アレルギーを引き起こしやすい特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)が含まれているかどうかは必ず確認しましょう。
| 表示義務(特定原材料) | 表示推奨(特定原材料に準ずるもの) |
|---|---|
| えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
ポイント5 好き嫌いが分かれにくい定番の味
感謝の気持ちを伝える贈り物ですから、できるだけ多くの方に「美味しい」と感じてもらえるものを選びたいものです。
そのためには、個性的すぎるフレーバーや、奇をてらったお菓子は避け、誰からも愛される定番の味を選ぶのが良いでしょう。
例えば、バニラ、チョコレート、プレーン、抹茶、小豆といった、昔から馴染みのある風味のお菓子は、好き嫌いが分かれにくく、安心して贈ることができます。



スパイスが強く効いたものや、酸味・苦味が際立つもの、珍しいリキュールが使われているものなどは、好みが分かれる可能性があるため避けた方が無難です。
老人ホーム入居で渡す菓子折りの相場は3,000円から5,000円


老人ホームへ入居する際の挨拶で渡す菓子折りの相場は、一般的に3,000円から5,000円程度とされています。
これは、これからお世話になる施設への感謝の気持ちを示しつつ、相手に過度な気を遣わせないための、ちょうど良い価格帯だからです。
もちろん、これはあくまで目安であり、施設の規模や方針、ご自身の予算に合わせて柔軟に考えることが大切です。
高価すぎる菓子折りはかえって相手の負担に
感謝の気持ちが強いあまり、1万円を超えるような高価な品物を選んでしまうと、かえって施設側に気を遣わせてしまう可能性があります。
「何かお返しをしなければならないのでは」「特別な対応を期待されているのだろうか」といった心理的な負担を与えてしまうかもしれません。
相手への配慮として、高価すぎる品物は避けるのが賢明な判断と言えるでしょう。
安すぎるものは失礼にあたる可能性も
一方で、あまりに安価すぎる品物も、挨拶の品としては避けた方が無難です。
例えば1,000円未満の菓子折りなど、極端に安いものだと、感謝の気持ちが十分に伝わらず、かえって失礼な印象を与えてしまう恐れがあります。
これから長いお付き合いになるかもしれない施設への最初の挨拶ですから、ある程度の礼儀をわきまえた品物選びが求められます。



菓子折り選びで迷った際の金額の目安を、以下の表にまとめましたので、参考にしてみてください。
| 価格帯 | 評価とポイント |
|---|---|
| 1,000円~2,000円 | 個人へのお礼など、少しカジュアルな場面では問題ありませんが、施設全体への挨拶としては少し物足りない印象を与える可能性があります。 |
| 3,000円~5,000円 | 【推奨】 感謝の気持ちが伝わり、相手に気を遣わせすぎない最もバランスの取れた価格帯です。 品物の選択肢も豊富で、定番の有名店の菓子折りも選べます。 |
| 5,000円~10,000円 | 丁寧な印象を与えますが、相手によっては少し気を遣わせてしまう可能性も出てきます。 特別な感謝を伝えたい場合などに適しています。 |
| 10,000円以上 | 相手に大きな心理的負担をかけてしまう可能性が高いため、基本的には避けた方が良いでしょう。 施設の方針で受け取ってもらえないこともあります。 |
【種類別】老人ホーム入居の挨拶におすすめの菓子折り


老人ホームへの入居挨拶で贈る菓子折りを選ぶ際、具体的にどのような商品が良いか迷う方も多いでしょう。
ここでは、前章で解説した「失敗しない選び方の5つのポイント」を踏まえ、実際に多くの方に選ばれており、施設スタッフや他の入居者様にも喜ばれやすいお菓子を種類別に厳選してご紹介します。
定番の和菓子から人気の洋菓子、食べやすさに配慮したお菓子まで、感謝の気持ちが伝わる品々を集めました。
定番で安心感のある和菓子のおすすめ
ご年配の施設長やスタッフ、他の入居者様にも馴染み深く、きちんとした印象を与えられるのが和菓子です。
特に、全国的に名の知れた老舗の和菓子は、高級感と安心感があり、お世話になる方々への敬意を表現するのに最適です。
上品な甘さの和菓子は、緑茶などにもよく合い、休憩時間を豊かにしてくれます。
とらやの小形羊羹
室町時代後期に京都で創業した老舗和菓子店「とらや」。
その名は、品質と格式の高さの証として広く知られています。
大切な場面での贈り物として、とらやの羊羹を選べばまず間違いありません。
特におすすめなのが、一切れずつ丁寧に包装された「小形羊羹」です。
手を汚さずに封を切ってすぐに食べられる手軽さは、忙しいスタッフの方々にとって大変ありがたい配慮となります。
また、製造から1年という非常に長い賞味期限も、贈答品として優れたポイントです。
伝統的な小倉羊羹「夜の梅」をはじめ、黒砂糖入りの「おもかげ」、抹茶入りの「新緑」など、複数の味が楽しめる詰め合わせは、選ぶ楽しみも提供できます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | 高い知名度と高級感。 手を汚さずに食べられる。 味のバリエーションが豊富。 |
| 価格帯の目安 | 3,000円~6,000円程度(10本入~18本入) |
| 日持ち | 製造から1年(常温) |
| 個包装 | あり |
文明堂のカステラ
「カステラ一番、電話は二番」のキャッチフレーズで世代を問わず親しまれている「文明堂」。
ふんわり、しっとりとした食感のカステラは、卵と砂糖の優しい甘さが特徴で、高齢の方にも好まれやすい定番のお菓子です。
施設への手土産として選ぶ際は、あらかじめ食べやすい大きさにカットされている商品がおすすめです。
個包装タイプの「おやつカステラ」も、より手軽で配りやすいため人気があります。
底に敷かれたザラメの食感がアクセントですが、硬いものが苦手な方もいる可能性を考慮し、オーソドックスなプレーン味を選ぶのが無難でしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | 馴染みのある優しい味わい。 柔らかく食べやすい食感。 カット済みの商品が便利。 |
| 価格帯の目安 | 2,000円~4,000円程度(カット済み商品や詰め合わせ) |
| 日持ち | お届け日から10日前後(常温) |
| 個包装 | 商品による(個包装タイプもあり) |
幅広い世代に人気の洋菓子のおすすめ
若い世代のスタッフにも喜ばれやすいのが、クッキーやバームクーヘンなどの洋菓子です。
個包装で日持ちがするものが多く、コーヒーや紅茶と一緒に休憩時間につまむのにぴったりです。
デパ地下などで手軽に購入できる有名店の洋菓子は、見た目もおしゃれで、感謝の気持ちを伝える贈り物として大変人気があります。
ヨックモックのシガール
バターをふんだんに使った生地を葉巻状に焼き上げたクッキー「シガール」は、洋菓子ギフトの定番中の定番です。
サクッとした軽い歯触りと、口の中でほろりと溶けるような繊細な食感が特徴で、硬いものが苦手な方でも比較的安心して召し上がれます。
上品なデザインの缶に入っており、贈答品としての見栄えも十分。
もちろん一つひとつが個包装になっているため、分けやすく衛生的です。
賞味期限も長く、常温で保存できるため、施設への手土産として非の打ち所がない一品と言えるでしょう。
チョコレートが中に入った「シガール オゥ ショコラ」との詰め合わせも人気です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | 軽い食感と上品な甘さ。 個包装で分けやすい。 高級感のあるパッケージ。 |
| 価格帯の目安 | 2,000円~5,000円程度(20本入~48本入) |
| 日持ち | 製造日から120日(常温) |
| 個包装 | あり |
ユーハイムのバウムクーヘン
日本で初めてバウムクーヘンを焼き上げたブランドとして知られる「ユーハイム」。
その伝統的な製法でつくられるバウムクーヘンは、しっとりとした食感と、甘さ控えめで飽きのこない味わいが魅力です。
木の年輪のような見た目から「長寿」や「繁栄」を連想させる縁起の良いお菓子としても知られており、挨拶の品にぴったりです。
大きなホールタイプは切り分ける手間がかかるため、一口サイズにカットされ個包装になった「リーベスバウム」や「デア バウムクーヘン」を選ぶのが賢明です。
常温で保存でき、日持ちもするため安心して贈ることができます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | しっとりとした食感と優しい甘さ。 縁起の良いお菓子。 個包装タイプが便利。 |
| 価格帯の目安 | 2,000円~4,000円程度(個包装10個入~21個入) |
| 日持ち | 製造日より60日(常温) |
| 個包装 | 商品による(個包装タイプがおすすめ) |
銀座ウエストのリーフパイ
東京・銀座に本店を構える老舗洋菓子店「銀座ウエスト」。
その看板商品である「リーフパイ」は、東北地方の原乳からつくられたフレッシュバターと小麦粉を256層に折りたたんだ、職人の手仕事が光る逸品です。
サックリとした独特の歯触りと、表面にまぶされたザラメ糖の素朴な甘さが特徴で、好き嫌いが分かれにくい定番の美味しさです。
一つひとつが個包装になっており、日持ちもするため、挨拶の品として安心して選べます。
誰にでも知られている有名店の安心感と、手作りならではの温かみが、感謝の気持ちをしっかりと伝えてくれるでしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | サックリとした食感と素朴な甘さ。 知名度が高く安心感がある。 個包装で衛生的。 |
| 価格帯の目安 | 2,000円~5,000円程度(12枚入~36枚入) |
| 日持ち | 製造日より40日(常温) |
| 個包装 | あり |
食べやすさで選ぶならゼリーや水ようかん
噛む力や飲み込む力(嚥下機能)が低下している高齢者の方への配慮を特に重視したい場合に最適なのが、のど越しの良いゼリーや水ようかんです。
つるんとした食感で食べやすく、特に暑い季節には喜ばれるでしょう。
見た目も涼やかで、食欲が落ちている時でも口にしやすいのが利点です。
新宿高野のフルーツゼリー
1885年創業のフルーツ専門店「新宿高野」。
選び抜かれたフルーツを贅沢に使用したゼリーは、果物本来の豊かな風味とみずみずしさを存分に味わえる逸品です。
マンゴーやピーチ、アップルなど様々な種類のフルーツを使ったゼリーは、彩りも豊かで見た目にも華やか。
贈り物として大変喜ばれます。
常温で保存でき、賞味期限も比較的長いため、施設への手土産に適しています。
ただし、大きな果肉が入っているものは、人によっては食べにくい場合もあります。
ピューレ状のなめらかなタイプのゼリーを選ぶか、詰め合わせの中から食べやすそうなものを選んでいただくよう一言添えるなどの配慮があると、より親切な印象になります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴 | フルーツ専門店の贅沢な味わい。 のど越しが良く食べやすい。 見た目が華やか。 |
| 価格帯の目安 | 3,000円~5,000円程度(8個入~12個入) |
| 日持ち | 製造日より120日(常温) |
| 個包装 | あり |
これで完璧 老人ホーム入居時の菓子折りの渡し方マナー


心を込めて選んだ菓子折りも、渡し方のマナーが伴わなければ、かえって失礼な印象を与えてしまう可能性があります。
感謝の気持ちを正しく伝えるためには、適切なタイミングや渡し方、そして「のし」の知識が欠かせません。
ここでは、老人ホームへ入居する際の菓子折りの渡し方について、のしの書き方から渡すタイミング、挨拶の言葉まで、知っておくべきマナーを詳しく解説します。
のし(熨斗)の正しい書き方
菓子折りには、感謝の気持ちを正式に伝えるために「のし紙」をかけるのが丁寧なマナーです。
しかし、のしには様々な種類があり、用途によって選び方や書き方が異なります。
間違いのないよう、老人ホームへの挨拶に適したのしの選び方と書き方をしっかり確認しておきましょう。
水引は紅白の蝶結びを選ぶ
のし紙にかける飾り紐を「水引(みずひき)」と言います。
老人ホームへの入居挨拶では、お祝い事全般に使われる「紅白の蝶結び」を選びましょう。
蝶結びは、何度でも結び直せることから「何度あっても良いお祝い事やお付き合い」に使われます。



これから始まる施設での生活が素晴らしいものであるように、そして施設の方々と末永く良好な関係を築けるように、という願いを込めるのに最適です。
表書きは「御挨拶」または「御礼」
水引の上部中央に書く目的を「表書き(おもてがき)」と言います。
入居時の挨拶としては、「御挨拶」と書くのが最も一般的で無難です。
すでに見学や手続きなどで何度かお世話になっており、感謝の気持ちをより強く表したい場合は「御礼」としても良いでしょう。



一方で、「粗品(そしな)」という言葉は、へりくだりすぎた表現であり、目上の方への贈り物にはふさわしくないとされていますので、避けるのが賢明です。
名前は入居する本人のフルネームを記載
水引の下部中央には、贈り主の名前を記載します。
この場合、これから施設でお世話になる「入居者様ご本人のフルネーム」を書きましょう。
ご家族が代理で菓子折りを持参する場合でも、名前は入居者様本人のものにします。



表書きや名前を書く際は、黒の毛筆や筆ペンを使い、楷書で丁寧に書くのが正式なマナーですので、ボールペンや万年筆は避けましょう。
| 項目 | 書き方 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 水引 | 紅白の蝶結び | 「末永いお付き合い」を願う意味があります。「結び切り」は使わないようにしましょう。 |
| 表書き | 「御挨拶」または「御礼」 | 水引の上部中央に、毛筆や筆ペンで濃い墨で書きます。「粗品」は避けましょう。 |
| 名入れ | 入居者本人のフルネーム | 水引の下部中央に、表書きより少し小さめに書きます。家族が渡す場合でも本人の名前を記載します。 |
菓子折りを渡すタイミングは入居当日が基本
菓子折りを渡す最適なタイミングは、入居日当日の手続きや挨拶の時です。
多くの施設では、入居当日に施設長や生活相談員、ケアマネージャーといった責任者や担当者から説明や挨拶がありますので、その際に渡すのが最もスムーズです。
相手が書類の確認や荷物の搬入などで忙しくしている最中は避け、少し落ち着いたタイミングを見計らうのが心遣いです。



万が一、入居当日に責任者の方へ会えなかった場合は、受付のスタッフの方に「施設長様(または皆様)へお渡しください」とお願いして預けても問題ありません。
渡す際に添える挨拶の言葉と例文
菓子折りは、品物だけを黙って渡すのではなく、心のこもった挨拶を添えることで、より一層気持ちが伝わります。
感謝の気持ちと、これからお世話になるということを簡潔に、そして誠意を込めて伝えましょう。
渡す際は、品物を購入した際の紙袋や風呂敷から取り出し、のしの表書きが相手から見て正面になるように向きを変え、両手で差し出すのが丁寧な渡し方です。
以下に、状況別の挨拶の例文をご紹介します。
【本人と家族が一緒に渡す場合の挨拶例文】
「本日よりお世話になります、〇〇(入居者名)です。こちらは息子の〇〇です。これから何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。心ばかりの品ですが、職員の皆様で召し上がってください。」
【家族が代理で渡す場合の挨拶例文】
「本日より入居いたします〇〇(入居者名)の長男の〇〇と申します。母(父)が大変お世話になります。不慣れな点が多く、ご面倒をおかけするかもしれませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。ささやかですが、皆様で召し上がっていただけますと幸いです。」
【渡す相手が複数人いる場合の挨拶例文】
「皆様、本日からお世話になります〇〇です。これからどうぞよろしくお願いいたします。つまらないものですが、皆様でどうぞ。」
まとめ
老人ホーム入居時の菓子折りは、これからお世話になる施設への感謝の気持ちです。
3,000円~5,000円を目安に、日持ちし個包装で食べやすいものを選びましょう。
のしのマナーや事前の確認を忘れず、良い関係を築きましょう。
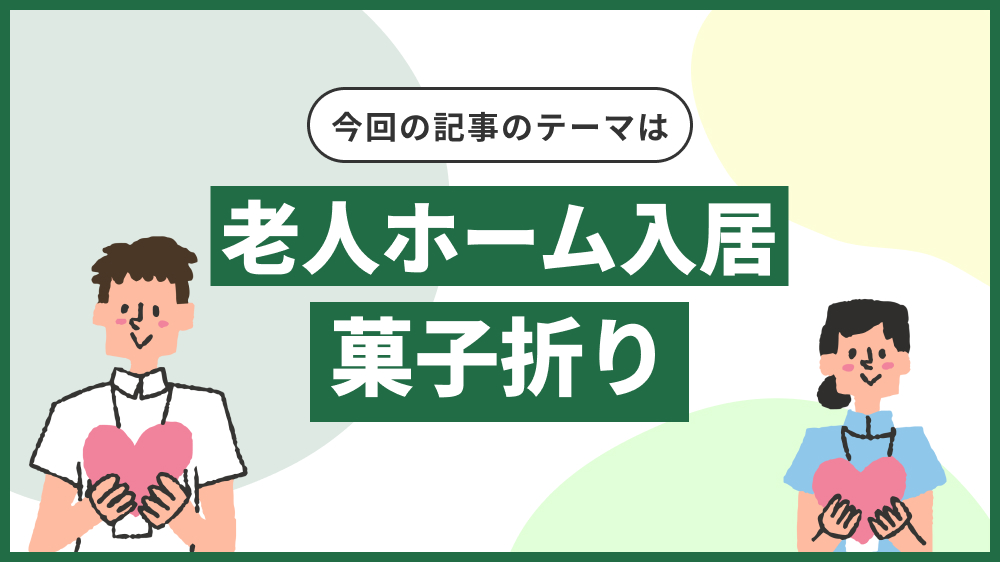









コメント