障害者からの暴力対応に悩んでいませんか?
本記事では暴力の原因から、予防・緊急時・再発防止の3ステップ対応、支援者を守る法的知識まで解説。
正しい知識で、利用者もあなた自身も守る具体的な方法が分かります。
これはNG 障害者からの暴力に対する間違った対応
障害のある方からの暴力に直面したとき、パニックになったり、どうすれば良いか分からなくなったりするのは当然のことです。
しかし、良かれと思って取った行動が、かえって状況を悪化させ、利用者の方との信頼関係を損なうだけでなく、法的に「虐待」と見なされてしまうケースも少なくありません。
ここでは、支援の現場で陥りがちな、絶対に避けるべき間違った対応を具体的に解説します。
感情的に叱責し恐怖で押さえつけようとする
暴力という予期せぬ事態に、思わずカッとなり大声で叱責してしまう。
その気持ちは理解できますが、感情的な対応は最も避けるべき行為の一つです。
なぜなら、暴力の背景には、利用者本人の不安や混乱、不快感といった、言葉で表現できないSOSが隠れていることが多いからです。
 編集長
編集長大声での叱責や威圧的な態度は、その場では一時的に行動を抑制できるかもしれませんが、利用者にとっては恐怖体験となり、支援者への不信感を増大させます。
力ずくでの不適切な身体拘束
利用者や周囲の安全を守るため、やむを得ず身体を抑える場面もあるかもしれません。
しかし、力ずくでの安易な身体拘束は「身体的虐待」そのものであり、法律で原則として禁止されています。
不適切な身体拘束は、利用者に身体的な怪我を負わせるリスクがあるだけでなく、深刻な精神的苦痛(トラウマ)を与えます。



その結果、支援者への恐怖心から問題行動がさらにエスカレートする可能性も否定できません。
| 不適切な対応の具体例 | 該当する可能性のある虐待の種類とリスク |
|---|---|
| 興奮している利用者を落ち着かせるために、部屋に鍵をかけて閉じ込める。 | 身体的虐待・心理的虐待 本人の意思に反して特定の場所に閉じ込める行為。 閉鎖空間での恐怖や不安を煽り、パニックを助長する危険性がある。 |
| 食事中に席を立つため、車椅子や椅子にひもやベルトで体を縛り付ける。 | 身体的虐待 本人の行動を抑制するために、ひも等で身体を拘束する典型的な虐待行為。 血行障害や怪我のリスクも伴う。 |
| 緊急性の要件を満たさない状況で、複数人の職員が力で押さえつける。 | 身体的虐待 組織的な検討や記録なく、安易に複数人で押さえつける行為。 利用者と職員双方の怪我のリスクが非常に高い。 |
| 自傷行為を防ぐという名目で、つなぎ服やミトン(手袋)を本人の意思に反して着用させる。 | 身体的虐待 行動を制限する衣類を本人の意思を無視して着せる行為。 根本的な原因解決にはならず、他の問題行動を誘発する可能性がある。 |
見て見ぬふりや問題を放置する対応
「関わると自分も危ない」「またいつものことだ」と、暴力行為を見て見ぬふりをしたり、問題そのものを放置したりすることも、実は深刻な対応の一つです。
これは、障害者虐待防止法で定められている「ネグレクト(介護・世話の放棄・放任)」という虐待に該当する可能性があります。
暴力は、利用者からの「困っている」「助けてほしい」という最後のコミュニケーション手段である場合も少なくないため、それを無視するということは、利用者のSOSを拒絶するのと同じです。



問題を放置すれば、暴力行為はさらにエスカレートし、利用者本人、他の利用者、そして支援者自身の安全が脅かされる事態につながりかねません。
【実践】障害者からの暴力への正しい対応を3ステップで解説
障害のある方からの暴力行為は、支援者にとって非常に深刻な問題です。
しかし、適切な知識と手順を身につけることで、リスクを大幅に軽減し、利用者と支援者双方の安全を守ることが可能になります。
ここでは、暴力を「予防」「緊急対応」「再発防止」の3つのステップに分け、具体的な実践方法を詳しく解説します。
ステップ1 暴力を未然に防ぐための予防的アプローチ
最も重要なのは、暴力が発生する前にいかに防ぐかという視点です。
利用者の行動の背景を理解し、安心して過ごせる環境を整えることが、暴力の未然防止に繋がります。
利用者の行動を観察し背景を読み解くアセスメント
暴力という行動には、必ず何らかの原因や背景が存在します。
そのサインを早期に発見し、適切に評価(アセスメント)することが予防の第一歩です。
具体的なアセスメント手法として「ABC分析」が有効です。
これは、行動を「先行事象(Antecedent)」「行動(Behavior)」「結果(Consequence)」の3つに分けて記録・分析する方法です。
これにより、どのような状況で暴力が起きやすいのか、その行動によって本人が何を得ているのか(要求の達成、不快な状況からの回避など)を客観的に把握できます。
記録する際は、感情的な記述(「わざとやった」「反抗的だった」など)を避け、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのようにしたか」という5W1Hを意識して、客観的な事実のみを記載することが重要です。
安心できる環境づくりと刺激の調整
利用者にとって、環境からの過度な刺激がストレスとなり、暴力の引き金(トリガー)になるケースは少なくありません。
本人が見通しを持って安心して過ごせるよう、物理的・人的環境を調整することが求められます。
- 物理的環境の調整:
感覚過敏に配慮し、照明の明るさや音の大きさを調整します。
また、人の往来が激しい場所が苦手な方には、静かで落ち着けるパーソナルスペースを確保することも有効です。
危険になりうる物品(ハサミや重い置物など)は、手の届かない場所に保管するなどの安全対策も徹底しましょう。
- スケジュールの構造化:
一日の活動内容や流れを、絵カードや写真、ホワイトボードなどを使って視覚的に提示することで、利用者は次に行うことを予測でき、安心して活動に取り組めます。
急な予定変更は不安を煽るため、やむを得ない場合でも、事前に本人に伝わる方法で説明することが大切です。
- クールダウンスペースの確保:
興奮しそうになった時に、一人で静かに気持ちを落ち着けられる場所(クールダウンできる部屋やスペース)をあらかじめ用意しておくことも、暴力へのエスカレーションを防ぐために効果的です。
本人に伝わるコミュニケーション方法の模索
自分の意思や感情をうまく言葉で伝えられないことが、もどかしさや混乱に繋がり、暴力という形で表出することがあります。
支援者は、本人の特性に合わせたコミュニケーション方法を見つけ、意思疎通を図る努力を続ける必要があります。
例えば、抽象的な表現(「ちゃんとして」「いい子にして」)は避け、「椅子に座りましょう」「手を洗いましょう」のように、具体的で短い言葉で伝えることを心がけます。



言葉での指示が通りにくい場合は、ジェスチャーや絵カード、写真、筆談など、非言語的な手段を積極的に活用しましょう。
ステップ2 緊急時の安全確保とクールダウンへの対応
予防策を講じても、暴力が発生してしまうことはあります。
その際は、パニックにならず、冷静に、かつ迅速に安全を確保し、利用者の興奮を鎮める対応が求められます。
まず自分と周囲の安全を最優先する
暴力が発生した際、最も優先すべきは「支援者自身と、周囲にいる他の利用者の安全確保」です。
支援者が怪我をしてしまっては、その後の対応も、他の利用者への支援もできなくなります。
- 距離を取る:
まずは本人から1.5m〜2m以上の安全な距離を確保します。
腕が届かない距離を保つことが基本です。
- 周囲を避難させる:
他の利用者がいる場合は、速やかにその場から避難させ、安全な場所に誘導します。
- 障害物をなくす:
周囲に投げられる可能性のある物や、ぶつかると危険な物があれば、可能な範囲で片付けます。
- 応援を呼ぶ:
一人で対応しようとせず、すぐに他の職員に助けを求めます。
大声で「〇〇さん、応援をお願いします!」と具体的に名前を呼ぶと、より確実に伝わります。
興奮状態を鎮めるための具体的な声かけと誘導
安全を確保したら、次に行うのは利用者の興奮を鎮めるためのクールダウンへの働きかけです。
高圧的な態度や叱責は、さらなる興奮を招き、事態を悪化させるだけですので、重要なのは、冷静に、共感的な姿勢で接することです。
声かけのポイントは、「低く、ゆっくり、穏やかなトーン」です。



本人の視界の真正面に立つと威圧感を与えるため、少し斜めに立ち、穏やかな表情を意識します。
| 不適切な声かけ(NG) | 適切な声かけ(OK) |
|---|---|
| 「やめなさい!」「何してるの!」(否定・詰問) | 「大丈夫だよ」「びっくりしたね」(安心感を与える) |
| 「どうしてそんなことするの?」(理由を問う) | 「〇〇が嫌だったんだね」(気持ちを代弁・共感) |
| 「いい加減にしなさい!」(感情的な叱責) | 「少し落ち着こうか」「静かな場所に行こうか」(行動を提案) |
| 「そんなことしたら、おやつ抜きだよ」(罰を示唆) | 「終わったら、好きな〇〇をしようか」(見通しを示す) |
複数人で対応するチームプレイの重要性
暴力への緊急対応は、決して一人で行うべきではありません。
必ず複数人で対応する「チームプレイ」を徹底してください。
事前に役割分担を決めておくと、いざという時にスムーズに行動できます。
- 対応役:
主に本人と対峙し、声かけや誘導を行う。
最も経験のある職員が担当するのが望ましい。
- 周辺対応役:
他の利用者を避難させたり、危険物を片付けたりして、周囲の安全を確保する。
- 記録・連絡役:
状況を客観的に観察・記録し、必要に応じて管理者や家族へ連絡を入れる。
ステップ3 再発を防ぐための事後対応と支援計画
暴力行為が収まった後、「一件落着」で終わらせてはいけません。
なぜ暴力が起きたのかを振り返り、次に繋げるプロセスが不可欠です。
この事後対応が、再発防止の鍵を握ります。
客観的な事実を記録し次に活かす
緊急対応が落ち着いたら、速やかに関わった職員全員で事実関係を記録に残します。
これは、誰かを責めるためではなく、次の支援に活かすための重要なデータとなります。
ヒヤリハット報告書やインシデントレポートなどの様式を用い、以下の点を客観的に記載します。
- 発生日時、場所
- 暴力行為の具体的な内容(誰に、何を、どの程度の強さで、何分続いたか)
- 暴力前の状況(先行事象、本人の様子、周囲の環境)
- 緊急時の対応内容(誰が、どのように対応したか)
- 暴力後の本人の様子、周囲の状況
支援チームでの振り返りと計画の見直し
記録をもとに、支援チーム(施設の職員、サービス管理責任者、相談支援専門員など)でカンファレンス(ケース会議)を開き、対応を振り返ります。
カンファレンスを通じて、ステップ1で実施したアセスメントを再評価し、暴力の引き金となった要因を改めて分析します。
その結果に基づき、個別支援計画を見直し、より本人に合った環境調整やコミュニケーション方法、日中活動などを具体的に計画に盛り込みます。



この「PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)」を回し続けることが、支援の質を高め、暴力の再発を防ぐことに繋がります。
支援者自身のメンタルヘルスケアを怠らない
暴力に対応した支援者は、身体的な危険だけでなく、精神的にも大きなストレスを受けます。
その気持ちに蓋をせず、自分自身の心をケアすることを忘れないでください。
まずは、信頼できる上司や同僚に、対応時の気持ちや現在の心境を話すこと(デブリーフィング)が大切です。



暴力対応は支援者のバーンアウト(燃え尽き症候群)に繋がりやすい問題ですので、自分を守ることも、質の高い支援を継続するための重要な仕事の一部だと認識しましょう。
一人で抱え込まない 障害者からの暴力に関する相談窓口一覧


障害のある方からの暴力行為への対応は、支援者一人で抱え込むべき問題ではありません。
精神的な負担が大きくなる前に、また、問題が深刻化する前に、適切な場所に相談することが極めて重要です。
相談することは、あなた自身の心と身体を守るだけでなく、結果として利用者の方へのより良い支援にも繋がります。
市町村の障害福祉担当課や障害者虐待防止センター
事業所内部での解決が難しい場合、行政機関という中立的な第三者に相談することが有効です。
お住まいの市区町村には、障害福祉に関する専門の窓口が設置されています。
市町村の障害福祉担当課
地域の障害福祉サービス全般を管轄する部署です。
事業者への指導権限を持つ立場から、適切な対応について助言を求めたり、事業所の運営体制について相談したりすることができます。
個別の対応方法だけでなく、事業所全体の支援体制に課題があると感じた場合に相談する窓口の一つです。
障害者虐待防止センター(市町村)
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に基づき、各市町村に設置されている専門機関です。
このセンターの役割は、虐待の通報や届出の受付だけではありません。
施設従事者などが「不適切な支援かもしれない」と悩んだ際の相談にも応じています。



支援者による暴力が「障害者虐待」と判断されることを防ぐためにも、対応に迷った時点で相談することが重要です。
都道府県運営適正化委員会や労働組合
より専門的な第三者機関や、労働者の権利を守るための組織も、あなたの力になります。
特に、事業者との関係性や労働環境に問題がある場合に頼りになる相談先です。
都道府県運営適正化委員会
社会福祉法に基づき各都道府県の社会福祉協議会に設置されている、福祉サービスに関する苦情を解決するための第三者機関です。
主な役割は利用者からの苦情対応ですが、事業所の運営に著しい問題があり、職員の訴えにもかかわらず改善されないようなケースでは、情報提供や相談先として機能する場合があります。
福祉サービスの質の向上と適正な運営を目的としているため、中立・公正な立場から問題を調査し、事業者への助言や改善のあっせんを行ってくれます。
労働組合
障害者からの暴力への対応は、職員の安全を守るという観点から「労働問題」でもあります。
事業者が職員の安全を守るための対策(安全配慮義務)を怠っている場合、労働組合に相談することで、職場環境の改善を要求することができます。
暴力による精神的ストレスで休職に至った場合の労災申請の相談や、人員配置の見直し、研修の実施などを会社側に交渉する際に、強力な後ろ盾となります。



勤務先に労働組合がない場合でも、個人で加入できる地域の合同労組(ユニオン)がありますので、諦めずに相談してみてください。
| 相談窓口の種類 | 主な相談内容 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 職場の上司・同僚 | 日々の具体的な対応方法、緊急時の応援要請、チームでの支援方針の検討 | 最も身近で迅速な相談先。組織としての対応を促す第一歩。 |
| 市町村の障害福祉担当課 | 事業所の運営や支援体制に関する相談、事業者への指導・助言の依頼 | 行政の立場から事業者への働きかけが期待できる。 公的な窓口。 |
| 市町村障害者虐待防止センター | 支援が虐待にあたらないかの確認、不適切な支援に関する専門的な相談 | 障害者虐待防止法に基づく専門機関。 匿名での相談も可能な場合が多い。 |
| 都道府県運営適正化委員会 | 事業所の運営に関する苦情、福祉サービスの質の改善に関する相談 | 社会福祉法に基づく第三者機関。 中立・公正な立場からの調査や助言。 |
| 労働組合(企業内組合・合同労組) | 安全配慮義務違反、ハラスメント、労災など労働問題に関する相談・交渉 | 労働者の権利を守るための組織。 団体交渉など法的な手段も視野に入る。 |
まとめ
障害者からの暴力対応は、背景にある原因の理解が不可欠です。
感情的な対応を避け、予防から再発防止までの体系的アプローチを実践しましょう。
支援者自身の安全を守る知識を持ち、一人で抱え込まず専門機関に相談することが、利用者と支援者双方にとってより良い支援の実現につながります。
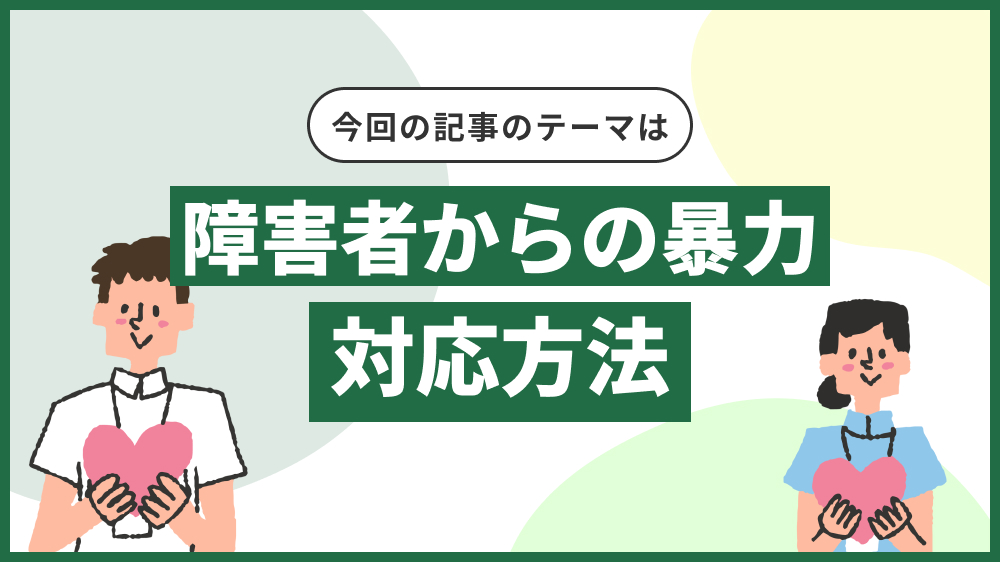








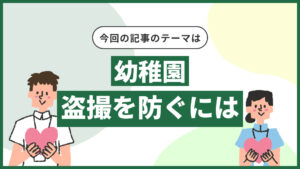
コメント