「園長からのパワハラかもしれない」と感じていませんか?
その言動は単なる指導ではなく、違法と判断される可能性があります。
この記事では、実際にあった園長のパワハラ事例から、パワハラと認められる判断基準、効果的な証拠の集め方、そして具体的な対処法までを徹底解説します。
パワハラの定義と法的側面を理解する

園長によるパワハラ問題は、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、園全体の運営や子どもたちの保育環境にも悪影響を及ぼしかねません。
この章では、まずパワハラが法的にどのように定義されているのか、そしてどのような場合に園長の行為が「パワハラ」として認められ、さらには「違法」と判断されるのかについて、その基礎となる知識を解説します。
パワハラとは?労働施策総合推進法による定義
「パワハラ」という言葉は広く使われていますが、その法的な定義は、2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)によって明確に定められました。
この法律では、職場におけるパワハラを以下の3つの要素全てを満たすものと定義しています。
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
- 業務の適正な範囲を超えて行われる言動
- 労働者の就業環境が害されるもの
園長は、その職務上の地位から、保育士や事務職員といった園の職員に対して常に「優越的な関係」にあると見なされることが多いため、その言動がパワハラに該当しないよう、より一層の注意が求められます。
園長のパワハラが違法と判断されるケース
パワハラ防止法は、事業主(園)にパワハラ防止措置を義務付けるものですが、パワハラ行為自体が直ちに刑法上の「違法」行為として罰せられるわけではありません。
しかし、パワハラ行為が民法上の「不法行為」(民法第709条)に該当すると判断された場合、被害者は加害者である園長個人や、園(使用者責任:民法第715条)に対して損害賠償請求を行うことが可能となり、この意味で「違法」と判断されます。
また、園がパワハラ防止措置を怠ったり、パワハラを放置したりした場合には、労働契約法第5条に定める「安全配慮義務」に違反したとして、園が損害賠償責任を負う可能性もあります。
- 行為の悪質性・態様: 暴行、脅迫、名誉毀損、侮辱など、社会通念上許容されない著しく不適切な言動であったか。
- 継続性・反復性: 一度きりの言動ではなく、反復継続して行われたか。継続性があるほど悪質性が高いと判断されやすい。
- 被害者の心身の状況: パワハラによって被害者が精神疾患を発症したり、身体的な不調を訴えたりしているか。医師の診断書などが重要な証拠となる。
- 行為者の意図・目的: 業務上の正当な指導を逸脱し、嫌がらせや苦痛を与える意図があったと推測されるか。
- 行為の場の状況: 密室で行われたのか、衆人環視の中で行われたのかなど、行為の状況も判断材料となる。
- 業務上の必要性・相当性: その言動が業務上本当に必要であったのか、またその手段や程度が適切であったのか。
 編集長
編集長これらの要素を総合的に考慮し、裁判所や労働審判委員会などがパワハラの有無と違法性を判断することになります。
実際にあった園長のパワハラ事例とその特徴


園長によるパワハラは、その立場からくる優位性を背景に、多様な形で発生します。
ここでは、実際に報告されている事例を類型化し、それぞれの特徴と被害の実態について詳しく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、園長の言動がパワハラに該当する可能性がないかを確認してください。
指導の範疇を超えた精神的な攻撃
園長の「指導」という名のもとに、職員の人格や尊厳を傷つける精神的な攻撃が行われるケースは少なくありません。
これは、時に被害者の精神状態を深刻なものにし、職場への適応を困難にさせます。
人格否定や侮辱的な言動の事例
人格否定や侮辱的な言動は、職員の自信を奪い、精神的な苦痛を与える代表的なパワハラです。
園長という立場からの一言は、他の職員にも影響を与え、職場全体の雰囲気を悪化させることもあります。
| 言動の種類 | 具体的な事例 | 被害者の声(例) |
|---|---|---|
| 能力否定 | 「お前は保育士失格だ」「給料泥棒」「こんなこともできないのか」 | 「自分は本当にダメな人間だと毎日思い知らされた」 |
| 人格攻撃 | 「性格が悪いから園児にも保護者にも嫌われる」「そんな人間だから結婚できないんだ」 | 「自分の存在価値まで否定されたように感じた」 |
| 容姿への言及 | 「その恰好は保育士としてふさわしくない」「もっと痩せたらどうだ」 | 「プライベートな部分まで踏み込まれ、常に監視されているようだった」 |
| 他の職員の前での罵倒 | 他の職員や園児、保護者の前で大声で叱責し、見せしめにする | 「恥ずかしくて顔を上げられず、職場にいるのが苦痛になった」 |
過度な叱責や長時間の説教の事例
業務上のミスに対する叱責は必要ですが、その内容や方法が適切でない場合、パワハラに該当します。
特に、執拗に長時間にわたる説教や、反論を許さない一方的な叱責は、精神的な攻撃とみなされます。
- 些細なミスへの執拗な追及:
連絡帳の記載ミスや園児の些細な喧嘩など、業務上の軽微なミスに対し、数時間にわたって延々と責任を追及し続ける。
他の職員がいる前で、まるで犯罪者扱いのように問い詰める。
- 終業後や休憩中の呼び出し:
定時を過ぎた後や休憩時間中に、園長室や人気のない場所に呼び出し、長時間にわたり説教を続ける。
これにより、職員は休息を取ることもできず、精神的な疲弊が蓄積する。
- 反論を許さない一方的な説教:
職員が自身の意見や状況を説明しようとしても、一切耳を傾けず、「言い訳をするな」「私の言う通りにしろ」などと一方的に自身の主張を押し付ける。
これにより、職員は精神的に追い詰められ、自己肯定感を失う。
- 他の職員との比較による叱責:
「〇〇先生はできるのに、なぜあなたはできないのか」「〇〇先生を見習え」などと、他の職員と比較して能力の低さを強調し、劣等感を抱かせる。
業務の強制や不当な要求
園長が自身の立場を利用し、職員に不当な業務を強制したり、業務範囲を超えた要求をしたりすることもパワハラの典型的な形態です。
これは、職員の労働条件を著しく悪化させ、健康被害にもつながることがあります。
サービス残業や休日出勤の強要事例
保育園では、行事準備や書類作成など、持ち帰り仕事やサービス残業が発生しやすい環境にあります。
しかし、これらを園長が強要することは明確なパワハラであり、労働基準法違反にも該当します。
- 「自主的な」残業や休日出勤の強要:
「みんなやっていることだから」「園のために当然だ」といった精神的な圧力をかけ、タイムカードを切った後の業務継続や、無給での休日出勤を事実上強制する。
- 過度な業務量の割り当て:
一人の職員では到底処理しきれない量の業務を割り当て、時間内に終わらないことを理由にサービス残業を促す。
これにより、職員は常に業務に追われ、心身ともに疲弊する。
- 持ち帰り仕事の強制:
行事の飾り付けや教材作成など、本来業務時間内に行うべき作業を「自宅でやってくるように」と指示し、無償で労働を強いる。
拒否すると、評価を下げたり、叱責したりする。
- 有給休暇取得の妨害:
職員が有給休暇を申請すると、「人手が足りない」「時期が悪い」などの理由をつけて却下したり、申請自体を諦めさせるような圧力をかけたりする。
プライベートへの過度な干渉や不当な業務指示の事例
園長が職員のプライベートにまで踏み込んだり、業務とは無関係な個人的な用事を押し付けたりすることも、パワハラに該当します。
これは、職員の私生活の自由を侵害し、精神的な負担を増大させます。
- 恋愛関係や結婚への口出し:
職員の交際相手や結婚の予定について執拗に尋ねたり、「保育士としてふさわしくない」「園に迷惑がかかる」などと批判したりする。
時には、結婚や出産を理由に退職を促す。
- 家族構成や私生活への詮索:
職員の家族構成、住居、経済状況など、業務とは無関係なプライベートな情報を執拗に聞き出そうとする。
また、個人的な事情を理由に業務上の不利益を与える。
- 個人的な用事の押し付け:
園長の私的な買い物や送迎、自宅の掃除など、業務とは全く関係のない個人的な用事を職員に指示し、強制的に行わせる。
- 不当な配置転換や業務内容の変更:
特定の職員に対し、その能力や経験を無視して、意図的に不適切な部署への配置転換を命じたり、嫌がらせ目的で専門外の雑務ばかりを指示したりする。
人間関係からの切り離しや無視
職場における人間関係からの切り離しや無視は、精神的な孤立を生み出し、被害者に大きな苦痛を与えます。
これは、目に見えにくいハラスメントですが、職場での居場所を失わせる深刻な行為です。
特定の職員を孤立させる事例
園長が意図的に特定の職員を孤立させることで、その職員は職場でのコミュニケーションを奪われ、精神的な負担を強いられます。
これは、いじめの一種とも言えます。
- 他の職員への指示・扇動:
他の職員に対し、「〇〇先生とは話すな」「〇〇先生を無視しろ」などと指示し、特定の職員を意図的に孤立させるよう仕向ける。
これにより、職場全体がその職員を避けるようになる。
- 会議や研修からの意図的な排除:
重要な会議や園内研修、職員間の交流イベントなどから特定の職員だけを意図的に外す。
これにより、その職員は情報や経験を得る機会を失い、疎外感を感じる。
- 集団での無視・仲間外れ:
園長自身が率先して、特定の職員への挨拶を無視したり、話しかけられても返事をしなかったりする。
他の職員もそれに追随し、集団で無視する状況を作り出す。
情報共有からの除外や無視の事例
業務上必要な情報が共有されないことは、業務遂行に支障をきたすだけでなく、その職員がチームの一員として認められていないというメッセージにもなり、精神的な苦痛を与えます。
- 重要な連絡事項の伝達漏れ:
園児や保護者に関する重要な情報、行事の変更点、業務手順の変更など、業務遂行に不可欠な情報を特定の職員にだけ意図的に伝えない。
これにより、その職員はミスを誘発されやすくなる。
- 業務に関する質問への無視:
職員が業務内容について質問しても、園長が返事をしなかったり、不機嫌な態度で無視したりする。
これにより、職員は疑問を解消できず、業務に不安を抱える。
- 業務日報や報告書の閲覧拒否:
職員が作成した業務日報や報告書を、正当な理由なく閲覧を拒否したり、内容を確認せずに突き返したりする。
これにより、職員は自身の業務が評価されていないと感じる。
過小な要求や過大な要求
園長が職員に対し、その能力に見合わない過度に少ない、または過度に多い業務を割り当てることもパワハラの一種です。
これは、職員のモチベーションを低下させ、キャリア形成を阻害する可能性があります。
達成不可能な目標設定や業務量の事例
達成が困難な目標設定や、物理的に不可能な業務量の割り当ては、職員を精神的に追い詰め、失敗を前提とした状況を作り出すことで、自信を喪失させます。
- 短期間での無理な行事準備:
通常数ヶ月を要する大規模な行事の準備を、特定の職員に数週間で完成させるよう指示する。
達成できないと、その責任をすべて職員に押し付ける。
- 一人では処理不可能な書類作成:
膨大な量の書類作成やデータ入力を、他の業務と並行して一人で行うよう指示する。
残業をしても終わらないほどの業務量を課し、心身を疲弊させる。
- 意図的に失敗を誘発する業務割り振り:
経験の浅い職員に、高度な専門知識や経験が必要な業務を割り当て、失敗することを前提に監視する。
失敗すると、能力不足として厳しく叱責する。
能力に見合わない単純作業への配置転換事例
職員の専門性や経験を無視し、意図的に能力に見合わない単純作業や雑務ばかりを割り当てることは、その職員の成長機会を奪い、職場での存在意義を失わせる行為です。
- 専門性のある保育士を清掃業務のみに:
経験豊富な保育士や特定の資格を持つ職員に対し、保育業務から外して、園内の清掃や備品の整理など、単純な雑務ばかりを指示する。
これにより、その職員の専門性を活かす場を奪う。
- 保育補助業務からの除外と雑務集中:
担任や正規の保育補助として働いていた職員を、意図的に保育現場から外し、コピー取り、お茶出し、備品の発注など、誰にでもできる雑務ばかりを集中して行わせる。
- 研修機会の剥奪:
職員がスキルアップのための研修参加を希望しても、正当な理由なく却下し、他の職員だけを参加させる。
これにより、その職員のキャリア形成を阻害する。
セクハラやモラハラを伴う複合的な事例
園長のパワハラは、単一の形態で発生するとは限りません。
セクハラ(性的嫌がらせ)やモラハラ(精神的な嫌がらせ)と複合的に絡み合い、より深刻な被害をもたらすことがあります。
これらの複合的なハラスメントは、被害者の心身に多大な影響を与え、職場環境を極めて悪化させます。
- 容姿への執拗な言及と業務上の不当な扱い:
園長が特定の女性職員に対し、その容姿や服装について執拗に品定めするような発言を繰り返す。
同時に、その職員に対してだけ業務上の重要な情報を伝えない、不当に業務量を増やす、他の職員の前で侮辱するといったパワハラ行為を行う。
- 性的な冗談や身体的接触と孤立化:
園長が職員に対し、不快な性的な冗談を言ったり、不必要な身体的接触を試みたりする。
その一方で、この行為を拒否した職員に対しては、他の職員に「あいつは協調性がない」などと吹き込み、職場内で孤立させるようなパワハラを行う。
- プライベートへの過度な干渉と精神的攻撃:
職員の私生活、特に恋愛関係や結婚について執拗に詮索し、自身の価値観を押し付ける。
それに従わない職員に対しては、「保育士として失格だ」「園の評判を落とす」といった人格否定の言葉を浴びせ、精神的に追い詰める。
- 特定の職員への集団的な精神的攻撃:
園長が主導し、他の職員を巻き込んで特定の職員を無視したり、陰口を叩いたりするモラハラ行為が行われる。
同時に、その職員に対しては、業務上達成不可能な目標を設定したり、不当な異動を命じたりするパワハラも複合的に発生する。
園長のパワハラ被害に遭った際の具体的な対処法と相談先


園長によるパワハラ被害に直面した場合、その状況は非常に困難で精神的な負担も大きいものです。
しかし、適切な対処法を知り、一歩踏み出すことで、状況を改善し、ご自身の心身を守ることが可能になります。
ここでは、具体的な行動ステップと、頼れる相談先について詳しく解説します。
まずは冷静に状況を記録する
パワハラ被害に遭った際、感情的になるのは当然ですが、冷静に状況を記録することが、その後の解決に向けた最も重要な第一歩となります。
この記録は、園内での相談、外部機関への相談、さらには法的な手続きを進める上での強力な証拠となり得ます。
- 日時と場所:いつ、どこでパワハラ行為があったのかを具体的に記録します。
- 行為の内容:園長がどのような言動を行ったのか、できる限り詳細に記録します。発言内容を正確に書き起こし、行為の様子(怒鳴りつけた、物を投げつけたなど)も具体的に記述しましょう。
- 行為の状況:その時の前後の状況、他の職員の有無、目撃者がいた場合はその氏名なども記録します。
- 自身の心身の状態:パワハラ行為によって、どのような精神的・身体的苦痛を感じたのかを記録します。例えば、不眠、食欲不振、吐き気、動悸、精神的な落ち込みなど、具体的な症状を書き留めておきましょう。
- 証拠の確保:可能な限り、録音・録画データ、メールやチャットのやり取り、業務日報、手書きのメモなども保存しておきましょう。
園内の相談窓口や人事部への相談
園内にハラスメント相談窓口や人事部、あるいは信頼できる上司がいる場合は、まずはそこに相談することを検討しましょう。
園内での解決が図れれば、比較的早期に問題が解決する可能性があります。
相談時のポイント
- これまでに記録した事実に基づき、冷静かつ具体的に状況を説明します。
- 感情的にならず、客観的な事実を伝えることに徹しましょう。
- 「どのような解決を望むか」を明確に伝える準備をしておくと良いでしょう。
- 相談内容が外部に漏れないよう、秘密保持の確認も忘れずに行いましょう。
注意点
- 相談窓口が形骸化している場合や、園長が経営者であるなど、園内で解決が難しいケースもあります。
- 相談したことで、かえって状況が悪化する可能性もゼロではないため、慎重に判断する必要があります。
外部の専門機関への相談
園内での解決が難しい場合や、最初から外部の専門機関に相談したい場合は、以下のような機関が頼りになります。
それぞれの機関には役割と得意分野がありますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法令に違反する事業主に対して指導・監督を行う行政機関です。
パワハラ行為そのものが直接的に労働基準法違反となるケースは少ないですが、パワハラに起因する労働時間管理の不適切さ、賃金未払い、解雇などの問題には対応できます。
相談できること
- 長時間労働の強要、残業代の未払いなど、労働基準法違反に関する相談。
- 解雇に関する不当性や、退職勧奨に関する相談。
- 安全衛生上の問題(過度なストレスによる健康被害など)に関する相談。
注意点
- パワハラ行為そのものの解決や、慰謝料請求などの民事的な問題には直接介入できません。
- あくまで労働基準法に違反する事柄に対して指導を行う機関です。
弁護士・法テラス
弁護士は法律の専門家であり、法的なアドバイス、代理交渉、訴訟手続きなど、幅広いサポートを提供してくれます。
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方でも弁護士や司法書士に相談できるよう、無料相談や費用立て替え制度を設けています。
相談できること
- パワハラ行為が不法行為に該当するかどうかの判断。
- 損害賠償請求(慰謝料、治療費、休業補償など)に関する具体的なアドバイス。
- 加害者や園との示談交渉、和解あっせん、調停、訴訟手続きの代理。
- 退職後の手続きや、退職に伴う不利益に対する法的支援。
弁護士に相談するメリット
- 法的な観点から最適な解決策を提案してもらえる。
- 相手方との直接交渉を任せられるため、精神的負担が軽減される。
- 証拠の収集方法や法的文書の作成をサポートしてもらえる。
法テラスの利用
- 経済的な理由で弁護士費用が心配な場合でも、無料で法律相談を受けたり、弁護士費用の立て替え制度を利用したりできます。
- まずは法テラスに相談し、弁護士紹介を受けることも可能です。
労働組合
労働組合は、労働者の権利と利益を守るために活動する団体です。
園に労働組合がある場合は、その組合に相談することができます。
また、園に労働組合がない場合でも、個人で加入できる「ユニオン」(合同労働組合)に相談することも可能です。
相談できること
- 園との団体交渉を通じて、パワハラ問題の解決や職場環境の改善を求める。
- パワハラ行為に対する是正勧告や、加害者への処分を求める。
- 労働者の立場に立って、具体的な解決策を共に検討し、行動してくれる。
労働組合のメリット
- 個人では難しい園との交渉を、組織の力で行ってくれる。
- 組合員として、継続的なサポートを受けられる。
- 労働問題に関する専門知識を持つ担当者が対応してくれる。



これらの外部機関への相談は、ご自身の状況や望む解決の形によって最適な選択肢が異なるため、複数の機関に相談し、それぞれの特徴を理解した上で、最も適した方法を選ぶことが重要です。
損害賠償請求や民事訴訟の可能性
園長によるパワハラ行為によって精神的・身体的な苦痛を受け、損害が発生したと認められる場合、加害者である園長個人や、使用者責任を負う園(学校法人など)に対して、損害賠償請求や民事訴訟を提起することが可能です。
損害賠償請求の対象
- 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償金です。パワハラの期間、内容、被害の程度によって金額が異なります。
- 治療費:パワハラが原因で通院・治療が必要となった場合の医療費。
- 休業損害:パワハラが原因で休職を余儀なくされ、収入が減少した場合の損失。
- 弁護士費用:訴訟にかかる弁護士費用の一部も、損害として認められる場合があります。
請求の条件
- パワハラの事実が明確であり、その行為と損害の間に因果関係があること。
- 十分な証拠(記録、診断書、第三者の証言など)が揃っていること。
手続きの流れ
- まずは弁護士に相談し、法的な見地から請求の可能性や妥当性を判断してもらいます。
- 弁護士を通じて、加害者や園に対して内容証明郵便などで損害賠償請求を行います。
- 交渉で解決しない場合は、調停や訴訟へと移行することになります。
注意点
- 損害賠償請求や民事訴訟は、時間と費用、そして精神的な負担が伴う手続きです。
- 必ず弁護士と連携し、専門的なアドバイスを受けながら進めるようにしましょう。
- 請求できる損害賠償額は、個別の事案によって大きく異なります。
まとめ
園長によるパワハラは、労働施策総合推進法で定義される違法行為です。
もし被害に遭ったら、証拠を確実に集め、労働基準監督署や弁護士など専門機関へ早期に相談することが重要です。
全ての園でパワハラのない、安心して働ける職場環境の実現を強く願います。
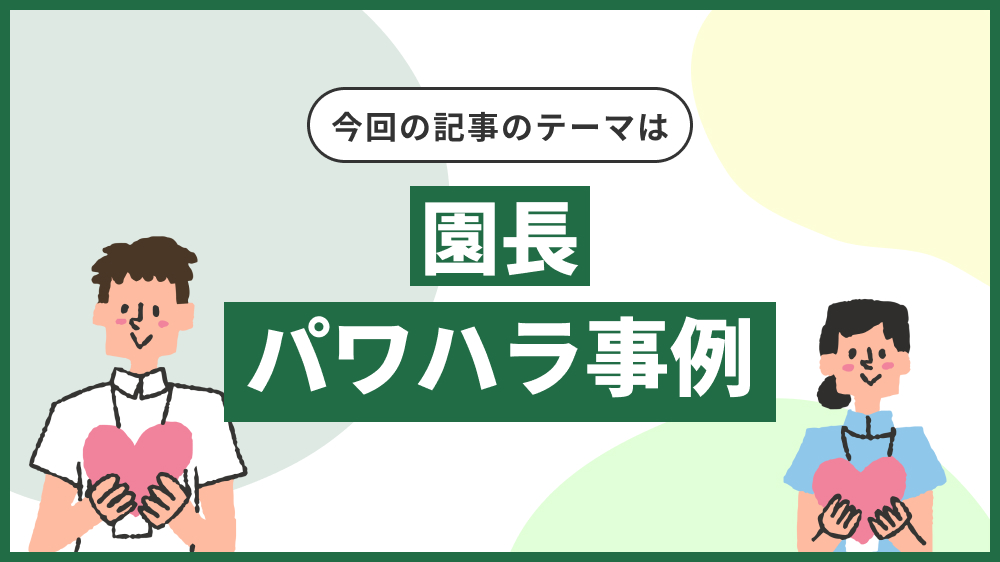








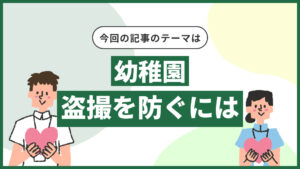
コメント