利用者を好きになったという複雑な感情は、福祉従事者として抱える自然な悩みです。
この記事では、その感情の正体を理解し、倫理と境界線を保ちながら、専門職として健全に働き続けるための具体的な整理法と対処法、そして相談の重要性をお伝えします。
はじめに 複雑な感情を抱くあなたへ

福祉の現場は、人と人との深い関わりの中で成り立っています。
日々の支援やケアを通じて、利用者様との間に特別な絆が生まれることは少なくありません。
しかし、その絆が、予期せぬ「好き」という感情へと発展し、心の中で複雑な葛藤を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
福祉の現場で生まれる特別な感情
福祉の仕事において、利用者様との信頼関係を築く過程で、感謝や尊敬、親愛の情が芽生えることは自然なことです。
しかし、時にはそれが「好き」という、個人的な感情へと発展してしまうこともあります。
利用者様の笑顔や成長を間近で見守り、その喜びを分かち合う中で、特別な感情が育まれることは、決して珍しいことではありません。
 編集長
編集長しかし、この感情をどのように捉え、どのように対処していくかが、福祉従事者としてのプロ意識と倫理を保つ上で非常に重要になります。
なぜこの感情は複雑なのか
「利用者を好きになった」という感情が複雑なのは、それが専門職としての役割と、一人の人間としての自然な感情との間で大きな乖離を生むからです。
この感情は、以下のような複数の要因によって、より一層複雑なものとなります。
専門職としての倫理と人間としての感情
福祉従事者は、利用者様の尊厳を守り、公平な支援を提供するという倫理的義務を負っています。
個人的な感情が支援の判断に影響を与えることは、専門職として許されません。
しかし、感情は理性でコントロールできるものではなく、時に倫理と感情の板挟みとなり、深い葛藤を生み出します。
周囲に相談しにくい孤立感
このような感情は、同僚や上司に打ち明けることへのためらいや、誤解されることへの恐れから、一人で抱え込みがちです。
その結果、孤立感や罪悪感が強まり、精神的な負担が増大してしまうことがあります。
誰にも話せない状況は、感情の整理をさらに困難にし、心の疲弊を招く原因にもなります。
| 側面 | 特徴 | 抱きやすい感情・葛藤 |
|---|---|---|
| 専門職としての役割 | 客観的な支援、倫理綱領の遵守、公平性、守秘義務 | 責任感、プロ意識、使命感、感情の抑制、倫理的ジレンマ |
| 一人の人間としての感情 | 共感、感情移入、親愛、個人的な好意、愛情 | 戸惑い、罪悪感、混乱、喜び、悲しみ、孤立感 |
この記事があなたの力になるために
この複雑な感情を乗り越え、より健全な形で専門職としての役割を全うするためには、まず自身の感情を深く理解し、適切に整理することが不可欠です。
この記事では、感情の正体を探ることから始まり、福祉専門職としての倫理と境界線の重要性を再確認します。
福祉専門職としての倫理と境界線の重要性


福祉従事者が利用者に特別な感情を抱くことは、人間として自然な反応である一方で、専門職としての倫理と境界線の維持が極めて重要になります。
この章では、福祉専門職として活動する上での基盤となる倫理綱領を再確認し、境界線が曖昧になることで生じるリスクについて深く掘り下げていきます。
福祉従事者の倫理綱領を再確認する
福祉専門職は、利用者とその家族の尊厳を守り、質の高いサービスを提供するための明確な倫理的指針を持っています。
日本国内の主要な福祉関連団体、例えば日本ソーシャルワーカー協会、日本介護福祉士会、日本精神保健福祉士協会などが定めている倫理綱領は、私たちの日々の実践における羅針盤となります。
特に重要な原則として、以下の点が挙げられます。
| 倫理原則 | 内容と「利用者を好きになった」感情との関連性 |
|---|---|
| 利用者の尊厳の尊重 | 利用者を一人の人間として尊重し、その自己決定権を最大限に尊重すること。 感情が介入することで、利用者の意向よりも自身の感情や願望を優先してしまうリスクを避けます。 |
| 専門的関係の維持 | 利用者との関係は、あくまで専門的な援助関係であり、個人的な関係や私的な感情を持ち込まないこと。 恋愛感情は専門的関係を逸脱する可能性を秘めています。 |
| 秘密保持の原則 | 利用者のプライバシーと秘密を守り、得られた情報を適切に管理すること。 感情に流され、個人的な情報を不適切に共有したり、利用者の秘密を侵害したりしないよう注意が必要です。 |
| 公正・公平なサービス提供 | 特定の利用者に対してのみ特別な配慮をしたり、個人的な感情に基づいてサービスの内容を変えたりしないこと。 全ての利用者に等しく、質の高いサービスを提供することが求められます。 |
| 利益相反の回避 | 専門職としての立場を利用して、個人的な利益を得たり、利用者との間で不適切な関係を築いたりしないこと。 感情が深まることで、この原則が揺らぐ可能性があります。 |
| 専門職としての責務 | 自身の専門性を常に高め、利用者にとって最善の利益を追求すること。 感情の混乱が、専門的な判断力や客観性を損なうことがないよう、自己管理が求められます。 |



好きという感情は自然なものですが、その感情が専門職としての行動や判断に影響を与えないよう、常に倫理綱領に立ち返ることが重要です。
境界線が曖昧になることのリスク
利用者との間に健全な境界線を設定し、それを維持することは、倫理的なサービス提供の根幹をなします。
この境界線が曖昧になることは、利用者、福祉従事者自身、そして所属する組織の全てに深刻なリスクをもたらす可能性があります。
境界線が曖昧になることで生じる主なリスクは以下の通りです。
| 対象 | 具体的なリスク |
|---|---|
| 利用者へのリスク | ・依存関係の深化と混乱: 専門職の個人的な感情が介入することで、利用者が不必要な依存を深めたり、関係性の性質を誤解したりする可能性があります。 ・自己決定権の侵害: 専門職の感情がサービス提供に影響し、利用者の真のニーズや自己決定が尊重されなくなる恐れがあります。 ・精神的負担の増大: 専門職の個人的な感情を受け止めることになり、利用者に精神的な負担や混乱を与える可能性があります。 ・不適切な関係性の発生: 恋愛感情がエスカレートし、利用者との間で倫理的に許されない私的な関係に発展するリスクがあります。 これはハラスメント行為とみなされる可能性もあります。 ・不信感の醸成: 他の利用者や家族から見て、特定の利用者への対応が不公平に映り、組織全体への不信感につながる可能性があります。 |
| 福祉従事者自身へのリスク | ・プロ意識の喪失: 個人的な感情が専門職としての客観性や判断力を曇らせ、プロフェッショナリズムを損なう可能性があります。 ・燃え尽き症候群(バーンアウト): 感情的な負荷が過剰になり、精神的・肉体的な疲弊につながり、最終的に燃え尽きてしまうリスクがあります。 ・ストレスと自己葛藤: 倫理と感情の板挟みになり、強いストレスや罪悪感、自己葛藤を抱え込むことになります。 ・人間関係の悪化: 感情的な問題が同僚や上司との関係にも影響を及ぼし、チームワークを阻害する可能性があります。 ・法的・倫理的責任問題: 境界線を逸脱した行為は、懲戒処分や資格停止、さらには法的責任を問われる事態に発展する可能性があります。 |
| 組織・チームへのリスク | ・組織の信頼失墜: 従業員の不適切な行為が明るみに出た場合、組織全体の信頼性や評判が大きく損なわれます。 ・チームワークの阻害: チーム内で不公平感が生じたり、情報共有が滞ったりすることで、チーム全体の機能が低下します。 ・法的・倫理的責任の発生: 組織は従業員の行動に対して監督責任を負うため、不適切な行為があった場合には、組織も法的・倫理的な責任を問われる可能性があります。 ・職員の離職: 職場環境の悪化や倫理的な問題が原因で、他の職員のモチベーション低下や離職につながることもあります。 |



これらのリスクを回避するためには、自身の感情を客観的に認識し、専門職としての倫理と責任を常に意識することが不可欠です。
「利用者を好きになった」感情を整理する具体的なステップ


利用者を好きになったという感情は、誰にとっても複雑で、時に戸惑いや罪悪感を伴うものです。
しかし、この感情を無視したり、抑圧したりするだけでは、心に負担がかかり、かえって問題が深刻化する可能性があります。
ここでは、その感情と向き合い、専門職として適切に整理するための具体的なステップを解説します。
自分の感情と向き合うための内省
感情を整理する第一歩は、その感情を「良い」「悪い」と判断せず、ただ認識し、受け止めることです。
まずは、自分の心の中で何が起こっているのかを客観的に見つめ直しましょう。
感情の種類を特定する
「好き」という言葉で表現される感情には、さまざまな種類があります。
それが純粋な恋愛感情なのか、それとも尊敬、親愛、保護欲、あるいは自己の承認欲求が満たされることへの喜びなのかを深く掘り下げてみましょう。
「好き」の種類
- 恋愛感情: 異性または同性として魅力的に感じる、個人的な関係を望む気持ち。
- 親愛・友情: 人として尊敬し、大切に思う気持ち、仲間意識。
- 保護欲・共感: 困難な状況にある利用者への深い共感からくる「守ってあげたい」という気持ち。
- 承認欲求の充足: 利用者から感謝され、必要とされることで、自己の存在価値が満たされる感覚。
- 孤独感の解消: 自身の私生活での孤独感が、利用者との親密な関係によって一時的に埋められる感覚。
これらの感情が単独で存在することもあれば、複数絡み合っていることもあります。



それぞれの感情がどのような状況で、どのように芽生えたのかを具体的に振り返ることが重要です。
感情と行動を区別する
感情は自然に湧き上がるものであり、それ自体をコントロールすることは難しいかもしれません。
しかし、その感情に基づいてどのような行動をとるかは、私たち自身の選択です。
福祉専門職として、感情と行動を明確に区別する意識を持つことが極めて重要です。
感情は自然、行動は選択
「利用者を好きになった」という感情を抱くこと自体は、人間として自然な反応であり、必ずしも悪いことではありません。
大切なのは、その感情に流されず、専門職としての倫理と責任に基づいた適切な行動を選択することです。
感情があるからといって、すぐにその感情を行動に移す必要はありません。
不適切な行動を避けるための自己チェック
感情が強くなると、無意識のうちに不適切な行動に繋がりかねません。
以下のような兆候に気づいたら、一度立ち止まり、自分の行動を客観的にチェックしましょう。
- 特定の利用者に対して、他の利用者よりも多くの時間や注意を割いている。
- 業務とは関係のない個人的な会話が増えている。
- 利用者から個人的な情報を聞き出そうとする、あるいは自分の個人的な情報を話してしまう。
- 業務時間外に利用者との連絡を試みる、または連絡に応じてしまう。
- 利用者に対して、他の同僚には見せないような特別な態度をとっている。
- 利用者の個人的な問題を、過度に自分の問題として抱え込んでいる。
これらの行動は、境界線が曖昧になっているサインです。



もし該当する行動があれば、すぐに軌道修正を図る必要があります。
誰かに相談する ひとりで抱え込まない勇気


「利用者を好きになった」という感情は、福祉従事者にとって非常にデリケートで、ひとりで抱え込むと精神的な負担が大きくなります。
このような複雑な感情を健全に整理し、プロとしての職務を継続するためには、信頼できる第三者に相談することが不可欠です。
ひとりで悩みを抱え込まず、適切なサポートを求める勇気を持つことが、自己を守り、より良い支援へと繋がります。
信頼できる同僚や上司への相談
同じ職場で働く同僚や上司は、福祉現場の特殊性や感情労働の困難さを理解しているため、共感を得やすく、具体的なアドバイスやサポートが期待できます。
彼らもまた、同様の感情に直面した経験があるかもしれません。
同僚や上司に相談するメリット
- 職場の状況や文化を理解しているため、具体的な状況に応じたアドバイスが得られやすいです。
- 感情労働の経験者として、あなたの苦悩に共感し、精神的な支えとなってくれる可能性があります。
- 上司に相談することで、必要に応じて業務調整やスーパービジョンの機会が設けられることもあります。
- 組織として問題解決に取り組むきっかけとなり、職場全体の倫理意識向上や支援体制強化に繋がることもあります。
専門機関やカウンセリングの利用
職場内の人間関係に配慮したり、より客観的で専門的な視点からの助言を求めたりする場合は、外部の専門機関やカウンセリングの利用が有効です。
専門家は守秘義務を徹底し、あなたの感情を安全な環境で深く探求し、整理する手助けをしてくれます。
専門機関の活用が推奨されるケース
- 職場内で相談できる相手がいない、あるいは相談することに抵抗がある場合。
- 感情が複雑で、自分自身では整理しきれないと感じる場合。
- 感情が原因で、日常生活や業務に支障が出始めている場合。
- 倫理的な問題について、より専門的な見解や指導を必要とする場合。
主な相談先とその特徴
以下に、利用できる主な専門機関や相談窓口の種類と特徴をまとめました。
| 相談先 | 特徴 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 精神保健福祉センター | 各都道府県・指定都市に設置されている公的な相談機関。 精神科医、精神保健福祉士、臨床心理士などが相談に応じます。 | 無料で利用でき、精神的な健康に関する幅広い相談が可能です。 地域の医療機関や支援サービスの情報も得られます。 | 予約が必要な場合が多く、相談まで時間がかかることがあります。 |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 厚生労働省が設置している、全国共通の電話相談窓口。 | 匿名で、気軽に電話で相談できます。 緊急性の高い状況にも対応しています。 | 一般的な助言が中心で、継続的なカウンセリングには向きません。 |
| 民間のカウンセリングルーム | 臨床心理士や公認心理師などの専門家が運営するカウンセリングサービス。 | 個別のニーズに応じた継続的なカウンセリングが受けられます。 守秘義務が徹底され、安心して感情を話せます。 | 費用がかかります。カウンセラーとの相性も重要です。 |
| 産業医・EAP(従業員支援プログラム) | 企業や団体が従業員向けに提供する健康相談窓口。 産業医や外部の専門家が対応します。 | 職場に特化した問題にも対応可能で、費用は会社負担の場合が多いです。 | 利用できるかどうかは所属する組織によります。 職場内での利用履歴が気になる場合もあります。 |
| 福祉関係団体・職能団体 | 社会福祉士会、介護福祉士会などの職能団体が、倫理相談窓口を設けている場合があります。 | 福祉専門職の倫理に特化した相談が可能です。 | 団体によって提供サービスが異なります。 |
相談する際のポイントと心構え
誰かに相談することは、感情を整理し、解決策を見つけるための第一歩です。
安心して相談に臨むためのポイントと心構えを理解しておきましょう。
- 正直に感情を伝える勇気を持つ:
恥ずかしい、または倫理に反すると感じるかもしれませんが、正直な感情を伝えることで、専門家は適切なサポートを提供できます。
- 相談の目的を明確にする:
「感情を整理したい」「具体的なアドバイスが欲しい」「誰かに話を聞いてほしい」など、相談を通じて何を得たいのかを考えておくと良いでしょう。
- 具体的な状況を整理する:
いつから、どのような状況で、どんな感情を抱いているのかなど、できる範囲で具体的に話せるように準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
- 相手の守秘義務を確認する:
安心して話すためにも、相談相手があなたの話をどのように扱うのか、守秘義務について事前に確認しておきましょう。
- 一度で解決しないことを理解する:
複雑な感情の整理には時間がかかることがあります。
一度の相談で全てが解決しなくても、焦らず継続的なサポートを検討しましょう。
- 自分を責めすぎない:
利用者への好意は、人間として自然に生じる感情の一部です。
自分を責めすぎず、感情と向き合うプロセスを大切にしましょう。
- 他者の意見を柔軟に受け止める:
相談相手からの客観的な意見やアドバイスは、新たな視点を与えてくれることがあります。
批判と捉えずに、自身の成長の機会として受け止めましょう。
- 自分自身の心と体を大切にする:
感情労働は心身に大きな負担をかけます。
相談すること自体が、自己ケアの一環であることを忘れずに、自分を労わる時間も確保しましょう。
まとめ
「利用者を好きになった」という感情は複雑ですが、専門職として倫理と境界線を意識することは不可欠です。
感情を整理し、健全な関係性を築くことは、あなた自身を守り、利用者への質の高い支援へと繋がります。
一人で悩まず、信頼できる人に相談し、プロとしてさらに成長していきましょう。
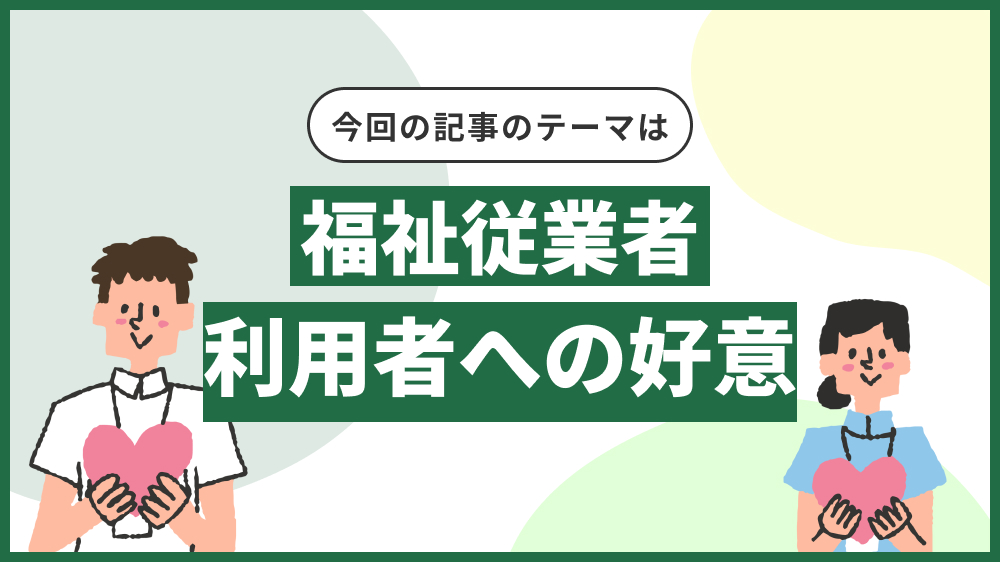








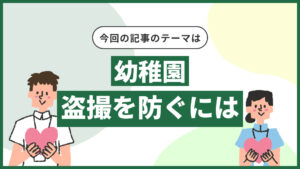
コメント