高次脳機能障害の暴力は本人の意思ではなく、脳の損傷による症状です。
この記事では、逆効果な対応を避け、当事者と家族を守る正しい対処法を解説。
暴力の予防策から相談先までわかり、明日からの関わり方が変わります。
高次脳機能障害による暴力的な言動 なぜ起こるのか

ご家族が突然、些細なことで激しく怒ったり、時には手を出したりする姿を目の当たりにし、「なぜこんなことに…」「昔はあんな人ではなかったのに」と、深く傷つき、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その暴力的な言動は、ご本人の人格が変わってしまったからでも、あなたへの悪意からでもありません。
それは、脳の損傷によって引き起こされる「症状」なのです。
本人の意思ではない 脳の損傷が引き起こす症状
高次脳機能障害は、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害、あるいは交通事故などによる頭部外傷で脳が物理的にダメージを受けることによって発症します。
私たちの脳は、思考、記憶、感情、行動など、人間らしい活動のすべてをコントロールする司令塔です。
特に、理性や判断力、感情のコントロール、行動の抑制などを司る「前頭葉(ぜんとうよう)」という部分が損傷を受けると、感情のブレーキが効きにくくなります。
 編集長
編集長まるで、アクセルは踏めるのにブレーキが壊れてしまった車のように、自分では止めたいと思っていても感情の爆発をコントロールできなくなってしまうのです。
暴力の引き金となる主な症状
暴力的な言動は、単一の原因で起こるわけではありません。
高次脳機能障害の様々な症状が複雑に絡み合い、引き金となって現れます。
ここでは、特に暴力につながりやすい代表的な症状を3つご紹介します。
感情コントロールの低下(易怒性)
易怒性(いどせい)とは、文字通り「怒りやすくなる」症状のことです。
以前は穏やかだった人が、テレビの音が少し大きい、話しかけるタイミングが悪かった、探し物が見つからないなど、ごく些細な出来事をきっかけに、まるでスイッチが入ったかのように激しい怒りを爆発させることがあります。
これは、感情の「沸点」が極端に低くなっている状態です。



脳の前頭葉の機能が低下し、不快な刺激やストレスに対する感情のブレーキが利かなくなっているために起こります。
欲求を抑えられない(脱抑制)
脱抑制(だつよくせい)とは、社会的なルールやその場の状況(TPO)を考慮せず、自分の欲求や感情をそのまま行動に移してしまう症状です。
「あれが欲しい」「こうしたい」という欲求や、「嫌だ」「不快だ」という感情を我慢することができません。
これも、理性のフィルターである前頭葉の抑制機能がうまく働かないために起こります。



例えば、自分の要求が通らないと分かると、子どものように大声でわめいたり、物を投げたりといった直接的な行動で不満を表現してしまうことがあります。
状況が理解できない(遂行機能障害・注意障害)
物事の段取りを考えたり、周囲の状況を正しく認識したりすることが難しくなることも、暴力の引き金になります。
代表的なものに「遂行機能障害」と「注意障害」があります。
ご自身の混乱や焦り、不安といった内的なストレスが、どう表現していいか分からず、結果的に怒りや暴力という形で外に現れてしまうのです。



ご本人にとっては、うまくできないことへのもどかしさや、周りから理解されないことへの孤立感が、さらなる興奮を招く悪循環に陥ることもあります。
| 障害の種類 | 具体的な困難さ | 暴力につながるメカニズム |
|---|---|---|
| 遂行機能障害 | 計画を立てて行動できない物事を順序立てて実行できない間違いに気づいて修正できない | 目的を達成できないことへの強いフラストレーションや混乱が、パニックや怒りを引き起こし、暴力・暴言につながる。 |
| 注意障害 | 一つのことに集中し続けられない周りの音や光など、多くの刺激に気を取られる会話の内容を正確に聞き取れない | 情報が多すぎて脳が疲弊し、不快感から興奮状態になる。 また、会話を誤解し「馬鹿にされた」「責められた」と感じて突然怒り出すこともある。 |
その対処は逆効果?高次脳機能障害の暴力でやってはいけない対応


高次脳機能障害のある方からの暴力的な言動に直面したとき、ご家族は心身ともに大きな負担を感じます。
なんとか状況を収めようと、良かれと思って取った行動が、実は症状を悪化させる引き金になっているケースは少なくありません。
ここでは、当事者とご家族の双方を守るために知っておくべき、避けるべき対応について具体的に解説します。
感情的に言い返してしまう
当事者から理不尽な言葉を浴びせられたり、突然怒鳴られたりすると、ついカッとなって感情的に言い返したくなる気持ちは誰にでも起こり得ます。
しかし、これは最も避けたい対応の一つです。
高次脳機能障害による「易怒性(いどせい)」は、感情のブレーキが効きにくくなる脳の損傷が原因であり、本人の意図や性格の問題ではありません。



こちらが感情的になると、相手の興奮をさらに煽ってしまい、暴力的な言動がエスカレートする悪循環に陥ります。
力で押さえつけようとする
暴力行為を止めようとして、腕を掴んだり体を押さえつけたりすることも逆効果です。
もちろん、自傷や他害の危険が差し迫っている緊急時には、安全確保のためにやむを得ない場合もあります。
しかし、力で押さえつけられると、当事者は恐怖やパニックを感じ、抵抗するためにさらに強い力で反撃してくる可能性があり、双方にとって怪我のリスクが高まります。



また、このような体験は当事者にとって強い恐怖記憶となり、介護者への不信感を募らせ、その後の関係構築を著しく困難にする恐れがあります。
原因を問いただし本人を責める
暴力的な言動が収まった後、「なぜあんなことをしたの?」「どうして約束を守れないの?」などと原因を問い詰め、本人を責めてしまうことはありませんか。
この対応も、問題解決には繋がりません。
高次脳機能障害のある方は、遂行機能障害や記憶障害によって、自分自身の行動の理由を客観的に理解したり、順序立てて説明したりすることが困難な場合があります。



本人もなぜそうなったのか分からず、混乱していることが多いため、そのような状態で問い詰められると、強いプレッシャーや罪悪感を感じ、自信を失ってしまいます。
見て見ぬふりをして無視する
どう対応して良いか分からず、あるいは疲れ果ててしまい、暴力的な言動を見て見ぬふりをしてしまうケースもあります。
その場を離れてクールダウンを促すことは有効な場合もありますが、完全に無視することは危険です。
当事者にとって、無視されることは「見捨てられた」「理解してもらえない」という強い孤独感や不安感に繋がり、注目を引くためにさらに問題行動をエスカレートさせる可能性があります。



関わりを完全に断つのではなく、安全な距離を保ちながらも「あなたのことを見守っている」という姿勢を示すことが重要です。
これらのやってはいけない対応をまとめると、以下のようになります。
| やってはいけない対応 | なぜ逆効果なのか(障害特性との関連) | もたらされる悪影響 |
|---|---|---|
| 感情的に言い返す | 感情コントロールが低下している相手の興奮を煽ってしまうため。 | 暴力のエスカレート、介護者のストレス増大、悪循環の形成。 |
| 力で押さえつける | パニックや恐怖を引き起こし、さらなる抵抗や攻撃を誘発するため。 | 双方の怪我のリスク、当事者の恐怖記憶、信頼関係の破壊。 |
| 原因を問いただし本人を責める | 遂行機能障害や記憶障害により、本人も行動の理由を説明できないことが多いため。 | 当事者の混乱、罪悪感や無力感の増大、自信の喪失。 |
| 見て見ぬふりをして無視する | 「見捨てられた」という孤独感や不安を強め、問題行動を悪化させる可能性があるため。 | 問題行動の悪化、自傷・他害行為の放置による危険、当事者の孤立。 |
大切なのは、暴力的な言動は「症状」の一つであり、本人の人格を否定するものではないと理解することです。
これらの逆効果な対応を避け、次の章でご紹介する正しい対処法を実践することが、当事者とご家族、双方の心と体を守る第一歩となります。
当事者と家族を守る 高次脳機能障害の暴力への正しい対処法


高次脳機能障害による暴力的な言動は、ご本人にとってもご家族にとっても辛いものです。
しかし、それは病気の症状の一つであり、決して本人の人格によるものではありません。
ここでは、いざという時に当事者とご家族の双方を守るための具体的な対処法を「緊急時」「予防」「事後」の3つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1 緊急時の対処 安全を確保する
暴力的な言動が始まってしまったら、何よりもまず安全の確保が最優先です。
議論や説得を試みる前に、ご自身とご本人の身体的な安全を守る行動をとりましょう。
まずは物理的な距離をとる
興奮している状態のご本人と同じ空間に居続けることは、さらなる興奮を招いたり、ご家族が怪我をしたりするリスクを高めます。
まずは冷静に、そして静かにその場を離れ、物理的な距離を確保してください。
このとき、慌てて背中を見せて逃げると、かえって相手を刺激してしまう可能性もあります。



「少し頭を冷やしてくるね」などと短い言葉をかけ、落ち着いて距離をとることが大切です。
刺激の少ない静かな場所へ誘導する
興奮の原因の一つに、周囲からの過剰な刺激があります。
テレビの音、人の話し声、明るすぎる照明などが、脳に負担をかけ、混乱やいら立ちを増幅させてしまうのです。
もし可能であれば、ご本人を刺激の少ない静かな場所へ誘導しましょう。



普段から「クールダウンできる場所」として、静かで落ち着ける寝室や和室などを決めておくとスムーズです。
ステップ2 暴力や興奮を予防する関わり方
緊急時の対応も重要ですが、より大切なのは、そもそも暴力や興奮が起きにくい状況を作ることです。
日々の関わり方や環境を少し工夫するだけで、暴力的な言動の頻度を減らすことができます。
暴力の引き金(トリガー)を特定し避ける
暴力的な言動には、その引き金(トリガー)となる特定の状況や出来事が存在することが多くあります。
何がご本人のストレスになっているのかを注意深く観察し、記録することで、トリガーが見えてきます。
「いつ、どこで、誰が、何をしたときに、どうなったか」をメモしておくと良いでしょう。



トリガーが特定できれば、それを避けるための具体的な対策を立てることができます。
| トリガーの例 | 具体的な回避策・工夫 |
|---|---|
| 特定の言葉や話題 | 「早くして」「なんでできないの?」といった急かしたり否定したりする言葉を避け、肯定的な表現を心がける。 過去の失敗など、本人が不快に感じる話題は避ける。 |
| 騒がしい場所 | 人混みや大きな音がする場所(スーパーの混雑時、工事現場の近くなど)での長時間の滞在を避ける。 外出時は比較的空いている時間帯を選ぶ。 |
| 複数のことを同時に頼まれる | 一度に多くの指示を出すのをやめる。 「着替えて、歯を磨いて、ゴミを出して」ではなく、「まず着替えをしよう」と一つずつ伝える。 |
| 予定の急な変更 | 可能な限り、急な予定変更は避ける。 変更が必要な場合は、事前に、分かりやすく、繰り返し伝える。 ホワイトボードなどで一日の予定を視覚的に共有するのも有効。 |
疲れさせない環境調整とスケジュールの工夫
高次脳機能障害のある方は、脳が疲れやすいという特徴があります。
疲労は、注意力の低下や感情のコントロール不全を招き、暴力の大きな原因となります。
ご本人が心身ともに疲れすぎないように、環境とスケジュールを調整することが極めて重要です。
- 環境調整のポイント
- 部屋の中は整理整頓し、物を少なくしてすっきりとさせる。
- テレビやラジオをつけっぱなしにせず、静かな時間を作る。
- 照明が眩しすぎないか、不快な臭いはないかなど、五感への刺激を確認する。
- スケジュールの工夫
- 活動と休息のバランスを考え、スケジュールに必ず休憩時間を組み込む。
- 一日の予定を詰め込みすぎず、余裕を持った計画を立てる。
- デイケアやリハビリから帰宅した後は、ゆっくり過ごせる時間を確保する。
分かりやすいコミュニケーションを心がける
言われたことをすぐに理解できなかったり、自分の気持ちをうまく言葉にできなかったりすることも、混乱や苛立ちにつながります。
ご家族がコミュニケーションの方法を少し変えるだけで、ご本人のストレスを大きく軽減できます。
- 短く、具体的に伝える:
「あれ取って」ではなく、「テーブルの上の緑のコップを取って」のように、具体的で短い言葉を選びましょう。
- 一度に一つずつ:
複数の指示を同時に出すと混乱の原因になります。
一つのことが終わってから、次のことを伝えましょう。
- 肯定的な表現を使う:
「走らないで」ではなく「歩こうね」、「大声を出さないで」ではなく「静かに話そうか」のように、してほしい行動を具体的に伝える方が理解しやすくなります。
- 視覚情報を活用する:
言葉だけでなく、メモや絵、写真、ジェスチャーなどを活用すると、より伝わりやすくなります。
- 時間を与える:
質問したり何かを頼んだりした後は、ご本人が理解し、反応するまで焦らずに待ちましょう。
沈黙を恐れず、考える時間を与えることが大切です。
ステップ3 暴力が起きてしまった後の対応
万が一、暴力が起きてしまった場合、その後の対応が今後の関係性や再発防止に大きく影響します。
興奮が収まった後、どのように関わるかが重要です。
本人が落ち着いてから冷静に話す
暴力や興奮の直後は、ご本人も混乱しており、何を言っても耳に入りません。
お互いに感情的になっている状態で話し合っても、事態が悪化するだけです。
まずはご本人とご家族、双方がクールダウンする時間をとりましょう。



ご本人の呼吸が穏やかになり、表情が和らぐなど、落ち着きを取り戻したサインが見られたら、静かな場所で冷静に話す機会を持ちます。
気持ちを受け止め共感を示す
暴力という「行動」は決して容認できませんが、その背景にあるご本人の「気持ち」に寄り添うことが、再発防止の鍵となります。
なぜ腹が立ったのか、何に混乱したのか、その原因となった感情を理解しようと努める姿勢が大切です。
ご本人がうまく言葉にできない場合は、「〇〇が分からなくて、悔しかったのかな?」「〇〇と言われて、悲しかったんだね」など、気持ちを代弁してあげるように問いかけてみましょう。



自分の気持ちを理解してもらえたと感じることで、ご本人は安心感を得て、信頼関係が再構築されます。
一人で抱え込まないで 高次脳機能障害の暴力に関する相談窓口


高次脳機能障害のあるご本人の暴力的な言動に、ご家族だけで対応し続けることには限界があります。
精神的にも身体的にも追い詰められてしまう前に、専門家や支援機関に相談することが、ご本人とご家族の双方を守るために不可欠です。
ここでは、具体的な相談窓口とその特徴について解説します。
かかりつけの主治医やリハビリテーション専門職
まず最初に相談すべきは、ご本人の状態を最もよく理解している医療の専門家です。
診断を受けた病院の主治医(脳神経外科、リハビリテーション科、精神科など)や、リハビリを担当している専門職は、最も身近な相談相手となります。
医療的な観点から、暴力的な言動が症状の変化によるものなのか、あるいは薬の影響や他の身体的な問題が隠れていないかを判断してもらえます。
- いつ、どのような状況で暴力的な言動が起きたか
- 言動の具体的な内容(大声を出す、物を投げる、叩くなど)
- 考えられる引き金(トリガー)
- その時のご家族の対応と、ご本人のその後の様子
- 暴力が起きる頻度の変化



リハビリを担当する理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)や、心理的なサポートを行う臨床心理士・公認心理師も、日々のリハビリテーションの様子からご本人の状態を把握しており、関わり方のヒントを提供してくれる心強い存在です。
全国の高次脳機能障害支援拠点機関
各都道府県や指定都市には、高次脳機能障害に特化した専門的な相談支援機関として「高次脳機能障害支援拠点機関」が設置されています。
ここは、ご本人やご家族が地域で安心して生活できるよう、多岐にわたるサポートを提供する中心的な役割を担っています。
拠点機関では、専門の相談支援コーディネーターが配置されており、以下のような支援を無料で受けることができます。
- 専門相談:
暴力への具体的な対処法、利用できる福祉サービス、就労に関する悩みなど、幅広い相談に対応します。
- 支援計画の作成:
ご本人やご家族の状況に合わせて、医療、福祉、就労などの関係機関と連携し、個別の支援計画(サポートプラン)の作成を手伝います。
- 情報提供:
地域の医療機関、福祉サービス事業所、当事者家族会などの情報を提供します。
- 研修会の開催:
ご家族や支援者向けに、高次脳機能障害の理解を深めるための研修会や交流会を開催しています。



お住まいの地域の拠点機関がどこにあるかは、インターネットで「(お住まいの都道府県名) 高次脳機能障害支援拠点機関」と検索するか、国立障害者リハビリテーションセンターのウェブサイトで確認することができます。
地域の保健所や精神保健福祉センター
市町村に設置されている保健所や、都道府県・指定都市が設置する精神保健福祉センターも、公的な相談窓口として活用できます。
これらの機関は、高次脳機能障害に限りませんが、地域住民の心と体の健康に関する様々な問題に対応しています。
特に、ご家族が介護疲れや精神的なストレスで追い詰められている場合、ご自身のメンタルヘルスに関する相談ができる点が大きな特徴です。
| 機関名 | 主な役割と特徴 |
|---|---|
| 保健所 | 地域住民の健康に関する身近な相談窓口。 保健師などが家庭訪問に応じてくれる場合もあります。 ご本人の健康問題と合わせて、ご家族の介護負担についても相談できます。 |
| 精神保健福祉センター | 心の健康問題に関する専門的な相談機関。 高次脳機能障害に伴う精神的な症状(うつ、不安など)や、ご家族の精神的負担が深刻な場合に、専門的な助言や医療機関の紹介が受けられます。 |
当事者家族会への参加
専門家への相談と並行して、同じ悩みや経験を持つ他の家族と繋がることも、大きな支えとなります。
当事者家族会は、お互いの体験を語り合い、情報を交換し、共感し合える貴重な場です。
「こんなに辛いのは自分だけではなかった」と感じることで孤立感が和らぎ、他の家族がどのように困難を乗り越えてきたかを知ることで、具体的な対処法のヒントを得られることも少なくありません。



また、公的な支援だけでは得られない、日々の生活に根差した実践的な情報を共有できるのも大きなメリットです。
家族会の情報は、前述の高次脳機能障害支援拠点機関や、市町村の障害福祉担当課などで得ることができます。
ご家族自身の心と体を守るために大切なこと


高次脳機能障害のあるご本人への対応と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、ご家族自身の心と体の健康を守ることです。
暴力的な言動に日々向き合うことは、想像を絶するストレスや疲労を伴います。
「自分が頑張らなくては」と一人で抱え込まず、ご自身のケアを最優先に考える時間を持ってください。
介護者のストレスケアとセルフケア
介護による精神的・身体的な負担が積み重なると、「介護疲れ」や「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥る危険性があります。
そうなる前に、ご自身のストレスサインに気づき、意識的にセルフケアを行うことが不可欠です。
日々の生活の中で、少しでも心と体を休ませる習慣を取り入れましょう。
まずは、以下のようなサインに心当たりはないか、ご自身の状態を客観的にチェックしてみてください。
| 分類 | 具体的なストレスサインの例 |
|---|---|
| 身体的なサイン | 頭痛、肩こり、不眠、食欲不振または過食、疲労感がとれない、風邪をひきやすい |
| 精神的なサイン | イライラする、不安感が強い、気分の落ち込み、何事にも興味が持てない、集中力の低下 |
| 行動面のサイン | ため息が増える、飲酒や喫煙量が増える、人に会うのが億劫になる、ささいなことで涙が出る |
レスパイトケアを活用して休息をとる
「レスパイト(respite)」とは、「一時的な休息」「息抜き」を意味する言葉です。
レスパイトケアとは、介護を一時的に代替してもらうことで、介護者が心身をリフレッシュするためのサービスを指します。
介護保険や障害福祉サービスなどを活用し、積極的に休息をとりましょう。
利用できる主なレスパイトケアのサービスには、以下のようなものがあります。
| サービスの種類 | サービス内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 数日間、施設に宿泊し、生活全般の介護を受けるサービスです。 | 冠婚葬祭や旅行、あるいは介護者の休息のために計画的に利用できます。 |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 医療的なケアが必要な場合に、病院や介護老人保健施設などに短期間入所するサービスです。 | 看護師が常駐しており、医療的な管理が必要な方も安心して利用できます。 |
| 通所介護(デイサービス)/通所リハビリテーション(デイケア) | 日中、施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けます。 | 日中の数時間だけでも介護から解放される時間ができ、精神的な余裕が生まれます。 |
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 | ご本人が自宅で過ごしながら、ご家族が外出したり休息したりする時間を確保できます。 |
まとめ
高次脳機能障害による暴力は本人の意思ではなく脳の症状です。
感情的な対応は避け、安全確保と予防的な関わりを心がけましょう。
当事者とご家族、双方を守るために、一人で抱え込まず専門機関へ相談することが大切です。
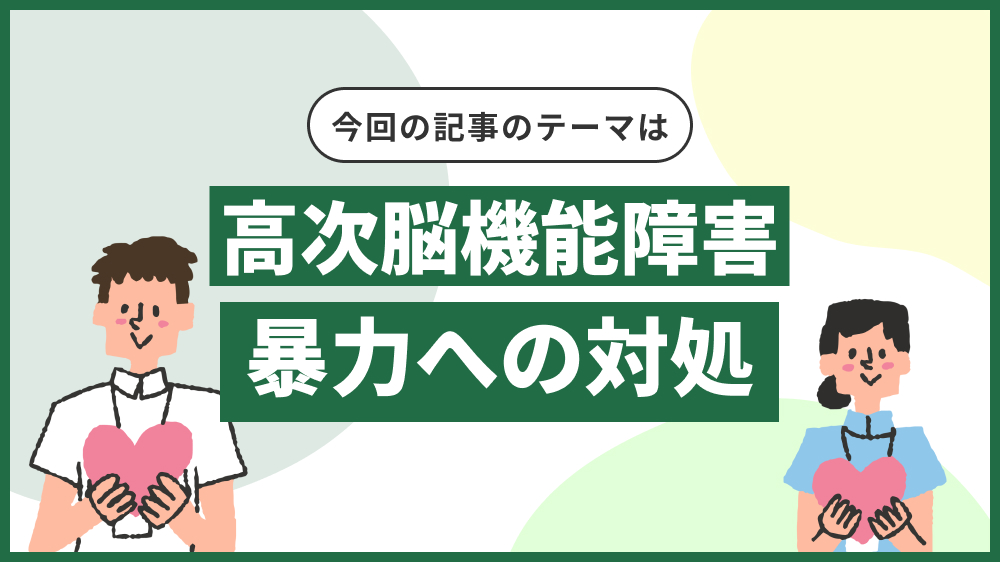









コメント