利用者とスタッフの恋愛は、立場の不均衡から深刻なトラブルに繋がりうるため、原則禁止です。
この記事では、禁止の理由や規則、立場別のリスクと具体的な対処法を解説。
トラブルを未然に防ぎ、健全な関係を築く方法がわかります。
利用者とスタッフの恋愛はなぜ問題になるのか?基本的な規則と倫理観
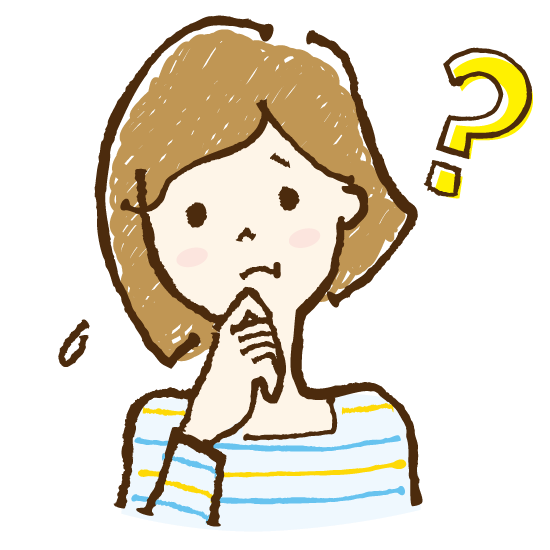
介護施設や福祉施設、病院などの現場で、利用者さんとスタッフが恋愛関係に発展することは、個人の自由な恋愛として単純に片付けられない、多くの深刻な問題をはらんでいます。
なぜ、これらの関係は原則として禁止され、問題視されるのでしょうか。
その背景には、単なるルール以上の、専門職としての基本的な倫理観や法律上のリスクが存在します。
 編集長
編集長この章では、その根本的な理由を多角的に解説します。
多くの施設で恋愛が禁止されている根本的な理由
ほとんどの施設で利用者とスタッフの恋愛が明確に禁止されているのには、当事者双方と施設全体を守るための、合理的で重要な理由があります。
それは感情論ではなく、支援の質と安全性を確保するための根幹に関わる問題です。
パワーバランスの不均衡と依存関係
利用者とスタッフの間には、構造的に「力の差(パワーバランスの不均衡)」が存在します。
利用者は心身の不調や生活上の困難を抱え、専門的な支援を必要とする「ケアを受ける側」です。
一方、スタッフは専門知識や技術を持ち、利用者の生活や個人情報を把握し、サービスを提供する「ケアをする側」です。



この非対称な関係性が、恋愛において以下のような問題を生み出します。
- 対等な同意の難しさ:
利用者はスタッフに「お世話になっている」という意識や、今後のサービスに影響が出るかもしれないという不安から、スタッフからのアプローチを断りにくい心理状況にあります。
そのため、一見合意の上に見える関係でも、利用者の真の自由意思に基づいているとは限りません。
- 依存の助長:
支援関係は、利用者の自立を促すことが目的です。
しかし、恋愛感情が介在すると、利用者はスタッフ個人への情緒的な依存を深めてしまい、本来目指すべき自立から遠ざかってしまう危険性があります。
それは健全な支援関係とは言えません。
このような力関係の中で生まれる恋愛は、対等なパートナーシップではなく、搾取や依存といった不健全な関係に陥りやすいのです。
職業倫理と信頼の毀損
介護福祉士や看護師、カウンセラーといった対人援助職には、すべての利用者に対する「公平性」と、築き上げてきた「信頼関係」が求められます。
特定の利用者と恋愛関係になると、どうしてもその利用者を優先したり、特別な扱いをしたりする「えこひいき」が生まれがちです。
周囲の利用者やそのご家族は、「あのスタッフは特定の人とだけ親密だ」と感じ、不信感を抱くでしょう。



また、同僚のスタッフもプロフェッショナルでない行動に困惑し、チームワークの乱れや職場全体の雰囲気の悪化につながります。
服務規程や契約書に定められた禁止事項
倫理的な問題だけでなく、多くの施設では、就業規則の一部である「服務規程」や雇用契約書において、利用者との私的な関係を明確に禁止しています。
これはトラブルを未然に防ぎ、職員と利用者の双方を守るための具体的なルールです。
禁止される行為は、恋愛関係や肉体関係だけでなく、より広い範囲に及ぶことが一般的です。
| 項目 | 具体的な内容 | 禁止される理由 |
|---|---|---|
| 個人的な連絡先の交換 | LINE、メールアドレス、電話番号、SNSアカウントなどの交換 | 公私の区別を曖昧にし、勤務時間外の不適切な関係に発展する入り口となるため。 |
| 私的な面会 | 勤務時間外や休日に、業務とは関係なく二人きりで会うこと | 特別な関係性を生み出し、公平なサービス提供の妨げとなるため。 |
| 金銭・物品の授受 | 個人的な金銭の貸し借り、プレゼントのやり取り(特に高価なもの) | 金銭トラブルや、見返りを期待する関係につながるリスクがあるため。 |
| 恋愛・性的関係 | 交際や肉体関係を持つこと | パワーバランスの不均衡から生じる搾取や依存のリスクが極めて高いため。 |
守秘義務違反など法律に抵触するリスク
利用者とスタッフの恋愛は、服務規程違反にとどまらず、法律違反という重大な事態に発展するリスクもはらんでいます。
対人援助職の多くは、その資格を定める法律によって厳格な「守秘義務」が課せられています。
恋愛関係というプライベートな間柄になると、会話の中でつい気が緩み、担当している利用者の病状や家庭環境、あるいは他の利用者やスタッフに関する内部情報などを話してしまう危険性が格段に高まります。



これは明確な守秘義務違反であり、発覚すれば資格剥奪や罰則の対象となる可能性もある犯罪行為です。
【立場別】利用者とスタッフの恋愛で実際に起こりうるトラブル事例


利用者とスタッフという立場を超えた恋愛は、一見すると素敵な出会いに思えるかもしれません。
しかし、その関係性の裏には、個人の問題だけでは済まされない、深刻なトラブルが数多く潜んでいます。
ここでは、介護施設、障害者支援施設、フィットネスクラブ、病院など、様々な現場で起こりうるトラブルを「スタッフ側」「利用者側」「施設全体」の3つの立場から具体的に解説します。
スタッフ側に起こる深刻なトラブル
まず、恋愛関係になったスタッフ側にどのようなリスクが降りかかるのでしょうか。
軽い気持ちで始めた関係が、自身のキャリアや私生活を根底から揺るがす事態に発展するケースは少なくありません。
懲戒処分や解雇のリスク
ほとんどの施設では、就業規則や服務規程において、利用者との私的な関係、特に恋愛関係を明確に禁止しています。
この規則を破った場合、発覚すれば厳しい処分は免れません。
処分の重さは、関係性の悪質さや施設への影響度合いによって異なりますが、一般的に次のようなものが考えられます。
- 譴責(けんせき)・戒告:
始末書を提出させ、将来を戒める最も軽い処分。
しかし、人事評価には記録が残ります。
- 減給:
一定期間、給与の一部が減額される処分。
- 出勤停止:
一定期間、出勤を禁じられ、その間の給与は支払われません。
- 諭旨解雇・懲戒解雇:
最も重い処分。
解雇に至るだけでなく、再就職の際にも重大な障害となる可能性があります。



「相手も同意の上だった」「誰にも迷惑はかけていない」という言い分は通用しません。
他の利用者や同僚との人間関係の悪化
まず、他の利用者から「えこひいき」と見なされることは避けられません。
これが他の利用者の不満や嫉妬を招き、「あのスタッフは信用できない」というレッテルを貼られてしまいます。
また、同僚からの信頼も失います。
チームで利用者をサポートしている現場において、一人のスタッフの個人的な感情は、チームワークを著しく乱します。



「プロ意識が低い」「報告・連絡・相談が疎かになるのではないか」といった疑念を抱かれ、孤立してしまうでしょう。
ストーカー被害や過度な要求
恋愛感情は、時として危険な執着に変わることがあります。
関係が順調なうちは問題なくても、もし関係がこじれたり、スタッフ側が別れを切り出したりした場合、相手がストーカー化するリスクが常に伴います。
- 勤務時間外の執拗な電話やメッセージ
- 自宅や通勤経路での待ち伏せ
- SNSでの監視や誹謗中傷
- 他の異性の利用者やスタッフとの関係を邪推し、攻撃的になる
また、恋愛関係を盾に「もっと特別なサービスをしてほしい」「個人的な頼み事を聞いてほしい」といった過度な要求がエスカレートすることもあります。
利用者側が被る不利益とトラブル
恋愛関係は、スタッフだけでなく利用者側にも大きな不利益をもたらします。
本来受けるべきサポートを得られなくなるばかりか、精神的な安定を損なうことにもつながりかねません。
適切なサービスを受けられなくなる可能性
スタッフとの恋愛が発覚した場合、施設側は公平性を保つために、そのスタッフを担当から外すのが一般的です。
信頼していた担当者が突然いなくなることは、利用者にとって大きな精神的ショックとなります。
最悪の場合、施設全体のルール違反と見なされ、施設自体の利用継続が困難になる可能性もゼロではありません。
精神的な不安定と依存の深化
「自分だけが特別」という感情は、スタッフ個人への過度な期待と依存を生み出します。
そのスタッフの言動一つひとつに一喜一憂し、本来の生活目標やリハビリへの集中力が削がれてしまいます。
特に、スタッフの異動や退職は、利用者にとって「見捨てられた」という強烈な喪失感(見捨てられ不安)を引き起こし、精神状態を著しく不安定にさせる原因となります。



支援される側と支援する側というアンバランスな関係性から始まる恋愛は、健全な対等関係を築きにくく、結果的に利用者の精神的な自立を妨げ、依存をより一層深めてしまう危険性をはらんでいるのです。
施設全体に及ぶ悪影響
一組の利用者とスタッフの恋愛問題は、当事者だけの問題では収まりません。
施設全体の信頼や運営基盤を揺るがす、重大な経営リスクに直結します。
以下の表は、施設全体に及ぶ主な悪影響をまとめたものです。
| 影響の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 信用の失墜 | 他の利用者やその家族から「職員の管理ができていない施設」「利用者の安全より職員の恋愛を優先するのか」といった不信感を持たれ、施設全体の信頼が大きく損なわれます。 |
| 風評被害の拡大 | 問題が外部に漏れた場合、SNSや地域の口コミサイトなどで「あの施設は危ない」といった悪評が瞬く間に拡散します。 一度ついた悪いイメージを払拭するのは極めて困難です。 |
| 利用者離れと経営悪化 | 施設の評判が悪化すれば、既存の利用者が退所したり、新規の利用希望者が減少したりすることに直結します。 これは施設の経営に深刻なダメージを与えます。 |
| 訴訟リスク | 関係が悪化した場合、利用者側から「不適切な関係を強要された」「精神的苦痛を受けた」として、施設が安全配慮義務違反などで訴えられる可能性があります。 |
| 職員の離職 | 職場の風紀が乱れ、人間関係が悪化することで、真面目に働いていた他の優秀な職員が職場環境に嫌気がさし、離職してしまう「モラルハザード」を引き起こす可能性があります。 |
このように、利用者とスタッフの恋愛は、当事者だけでなく、周囲の多くの人々や組織全体を巻き込む深刻なトラブルに発展する可能性を秘めているのです。
【スタッフ向け】利用者を好きになった・好意を寄せられた時の対処法


福祉施設、介護施設、医療機関などで働くスタッフが、利用者に対して特別な感情を抱いたり、逆に好意を寄せられたりすることは、決して珍しいことではありません。
しかし、その感情に流されてしまうと、ご自身のキャリアだけでなく、利用者や施設全体に深刻なトラブルを招く可能性があります。
ここでは、スタッフの立場から、冷静かつ適切に対処するための具体的な方法を解説します。
まずは自分の感情を客観的に分析する
利用者に対して「好きかもしれない」と感じた時、まず行うべきは、その感情の正体を冷静に分析することです。
支援者という立場は、利用者の人生に深く関わるため、特別な感情が芽生えやすい環境にあります。
その気持ちが本当に恋愛感情なのか、あるいは別の感情と混同していないか、一度立ち止まって考えてみましょう。
- その感情は、一人の人間としての魅力に対するものですか?
それとも、支援が必要な相手を守りたいという「保護欲」や「同情」から来ていますか? - 特定の業務(例えば、マンツーマンでのリハビリや相談業務など)を通じて、一時的に距離が近くなったことで生まれた感情(吊り橋効果など)ではありませんか?
- 仕事の悩みやストレスから逃れるため、利用者の存在に精神的に依存していませんか?
- もし相手が利用者でなかったとしても、同じように惹かれたでしょうか?
- その利用者だけでなく、他の利用者にも同じようにプロフェッショナルな関心や思いやりを向けられていますか?
利用者からアプローチされた時の適切な断り方
利用者から好意を伝えられたり、連絡先の交換を求められたりした場合、その対応は非常に重要です。
曖昧な態度は相手に期待を持たせ、問題をこじらせる原因になります。
相手の気持ちを尊重しつつも、プロとして明確に、そして誠実に断る必要があります。



断る際は、個人の感情ではなく「施設の規則」や「職業倫理」を理由にすると、相手を不必要に傷つけず、かつ個人的な拒絶ではないことを伝えやすくなります。
| 状況 | 避けるべき対応(悪い例) | 推奨される対応(良い例) |
|---|---|---|
| 連絡先を聞かれた時 | 「えーっと、ちょっと…」と口ごもる。 「今は無理だけど、いつか…」と期待させる。 | 「お気持ちは大変嬉しいのですが、規則で利用者様と個人的な連絡先の交換は禁止されているんです。申し訳ありません。」 |
| 食事などに誘われた時 | 「忙しいのでまた今度」とごまかす。 (社交辞令のつもりでも、相手は本気にする可能性がある) | 「お誘いありがとうございます。ですが、仕事以外で利用者様と個人的にお会いすることはできない決まりになっています。ご理解いただけると嬉しいです。」 |
| 「好きです」と告白された時 | 無視したり、笑ってごまかしたりする。 「私もですよ」と冗談で返す。 | 「そう思っていただけて、支援者として光栄です。ありがとうございます。しかし、私はあくまでスタッフという立場ですので、そのお気持ちにはお応えできません。これからも専門職として、〇〇さんをしっかりサポートさせていただきますね。」 |
一人で抱え込まず上司や同僚に相談する重要性
利用者との恋愛感情に関する悩みは、非常にデリケートな問題であり、一人で抱え込んでしまいがちです。
しかし、孤立することは最も危険な選択です。
問題が大きくなる前に、信頼できる上司や先輩、同僚に相談してください。
- 客観的な視点の獲得:
第三者の視点から、冷静なアドバイスをもらえます。
- 組織としての対応:
人的な問題ではなく、組織全体の問題として対応策を講じてもらえます(担当の変更など)。
- 精神的負担の軽減:
悩みを共有することで、一人で抱え込む精神的なストレスが軽くなります。
- トラブルの予防:
万が一、ストーカー行為などのトラブルに発展した場合でも、事前に相談していれば組織的なサポートを得やすくなります。
どうしても気持ちが抑えられない場合の最終手段
自己分析を重ね、上司にも相談した上で、それでも利用者への恋愛感情が抑えきれない、あるいは利用者からのアプローチが続き業務に支障をきたす、という状況に陥る可能性もゼロではありません。
その場合は、利用者とご自身、そして施設全体を守るための最終手段を検討する必要があります。
これは「逃げ」ではなく、プロフェッショナルとしての「責任ある決断」です。
- 担当の変更を正式に申し出る:
まずは、その利用者との物理的な距離を置くことが最も効果的です。
上司に事情を説明し、担当から外してもらうよう正式に依頼します。
- 部署異動を願い出る:
担当変更が難しい場合や、同じフロアにいるだけで気持ちが揺らいでしまう場合は、部署の異動を検討します。
- 退職・転職を検討する:
異動も叶わず、このままでは職業倫理を守れない、あるいは精神的に限界だと感じた場合は、退職するという選択肢も考えなければなりません。
利用者との関係がサービス期間中のみで終わるものであれば、退職後に改めて関係を築くという可能性も理論上はありますが、その場合でも慎重な判断が求められます。
【利用者向け】スタッフを好きになった時の心構えと注意点


介護施設や福祉サービス、ジム、病院などで親身に接してくれるスタッフに対し、特別な感情を抱くことは決して珍しいことではありません。
しかし、その好意が恋愛感情に発展したとき、すぐに行動に移すのは非常に危険です。
ご自身の気持ちと向き合い、相手の立場を深く理解することが、無用なトラブルを避ける第一歩となります。
その好意は本当に恋愛感情か
まず立ち止まって、ご自身の胸にある感情が本当に「恋愛」なのかを冷静に分析してみましょう。
支援を受ける立場にある利用者は、スタッフに対して特別な感情を抱きやすい心理状況にあります。
これを心理学では「転移(てんい)」と呼ぶことがあります。
自分の気持ちを確かめるチェックリスト
以下の表を参考に、ご自身の感情を客観的に見つめ直してみてください。
| 感情の種類 | 特徴的な考え方や感情 | 具体例 |
|---|---|---|
| 恋愛感情 | 相手を一個の人間として尊重し、対等な関係を望む。 相手のプライベートな側面も知りたいと思う。 | 「仕事以外のあの人はどんな人だろう」「相手の幸せを心から願っている」「もし付き合えたら、対等なパートナーとして支え合いたい」 |
| 転移感情(感謝・憧れ・依存) | 「スタッフ」という役割に対して強い感謝や安心感を抱いている。 保護されたい、もっと構ってほしいという気持ちが強い。 | 「この人がいないとダメになってしまう」「いつも優しいのは自分に気があるからだ」「もっと自分だけを見てほしい」 |
もしご自身の感情が「転移感情」に近いと感じたなら、それは特別なことではありません。
多くの人が経験する自然な心理です。
しかし、それを恋愛と信じて行動すると、あなた自身もスタッフも苦しむ結果になりかねません。
軽率な行動がスタッフを追い詰めることを理解する
たとえあなたの気持ちが本物の恋愛感情だったとしても、それを軽率に伝える行動は、スタッフを深刻な状況に追い込む可能性があります。
スタッフは職業倫理と施設の規則に縛られており、利用者と私的な関係を持つことは固く禁じられているのが一般的です。
あなたの善意の行動が、相手にとっては大きなプレッシャーやリスクになることを理解しておく必要があります。
利用者の行動がスタッフに与える影響
| 利用者の具体的な行動 | スタッフが直面するリスク・精神的負担 |
|---|---|
| 個人的な連絡先を聞く・渡す | 服務規程違反と見なされ、懲戒処分の対象になる可能性があります。 断る際にも多大な精神的エネルギーを使います。 |
| 高価なプレゼントを渡す | 受け取れば規則違反、断れば利用者を傷つけてしまうというジレンマに陥ります。 他の利用者との公平性も保てなくなります。 |
| 「好きです」と告白する | 明確に断らなければなりませんが、それによって今後のサービス提供に支障が出ることを恐れます。 ハラスメントと受け取られる可能性もあります。 |
| 二人きりになろうとする・身体的な接触を試みる | 深刻なハラスメント行為であり、スタッフに恐怖心を与えます。 最悪の場合、警察沙汰や解雇につながることもあります。 |
スタッフは「すべての人に平等なサービスを提供する」という使命を負っています。
あなたへの対応に困ることで、他の利用者へのサービス品質が低下したり、職場の人間関係が悪化したり、精神的に疲弊して退職に追い込まれたりするケースさえあるのです。
あなたの行動が、お世話になったスタッフのキャリアや人生を左右する可能性があることを、どうか忘れないでください。
退所後やサービス終了後の関係性について
「では、利用者でなくなれば問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
確かに、施設やサービスの利用契約が完全に終了すれば、あなたとスタッフは「一般人」同士となり、恋愛が規則によって禁止されることはなくなります。
しかし、だからといってすぐに恋愛関係に発展できると考えるのは早計です。



いくつか注意すべき点があります。
サービス終了後にアプローチする際の注意点
- 冷却期間を置くこと:
サービス終了直後は、まだ「利用者と元スタッフ」という関係性の名残が強く残っています。
お互いが冷静になり、対等な個人として向き合えるようになるまで、最低でも数ヶ月は時間を置くべきです。
- 相手の意思を最大限に尊重すること:
スタッフは、あなたをあくまで「大切な利用者の一人」としか見ていない可能性が高いです。
サービス終了後にプライベートな関係を望んでいるとは限りません。
しつこいアプローチは相手にとって迷惑行為となります。
- 偶然を装った接触は避けること:
相手の勤務終了を待ち伏せしたり、SNSで探し出してメッセージを送ったりする行為は、ストーカーと見なされる危険性が高く、絶対に避けるべきです。
- 対等な立場で出会い直す意識を持つこと:
もしご縁があれば、全く別の場所で、対等な個人として再会する機会があるかもしれません。
その時まで、自分磨きをしながら待つくらいの心構えが大切です。
利用者とスタッフという特殊な関係性で芽生えた感情は、非常にデリケートで複雑です。
ご自身の気持ちを大切にしつつも、相手の立場と職業倫理を尊重し、冷静に行動することが、あなた自身と相手を守る最善の方法と言えるでしょう。
トラブルを未然に防ぐ利用者とスタッフの健全な関係性の築き方


利用者とスタッフとの間で起こる恋愛トラブルは、その多くが専門的な支援関係における適切な距離感を見失うことから始まります。
しかし、冷たく突き放すことが正しい関係性ではありません。
ここでは、トラブルを未然に防ぎ、利用者とスタッフ双方が安心して過ごせるための、健全な関係性の築き方について具体的に解説します。
プロとして守るべき境界線(バウンダリー)の保ち方
福祉や医療の現場で使われる「境界線(バウンダリー)」とは、支援者と利用者の間に引かれるべき、プロフェッショナルとして適切な関係性を保つための見えない線のことです。
この境界線を意識し、守ることが、信頼関係を損なわず、お互いを守ることに繋がります。
具体的には、物理的、感情的、社会的な境界線が存在します。
物理的・社会的な境界線の維持
物理的・社会的な境界線は、行動として明確に現れるため、特に意識して守る必要があります。
- 私的な連絡先の交換は行わない:
個人の電話番号やLINE、SNSアカウントの交換は、公私混同の第一歩です。
連絡は必ず事業所や施設のルールに則った方法で行いましょう。
- 勤務時間外の私的な接触を避ける:
業務とは関係のない個人的な食事や面会は、特別な事情がない限り避けるべきです。
- 個人的な贈り物や金銭のやり取りは原則禁止:
高価な贈り物や金銭の貸し借りは、関係性を不健全にし、他の利用者との不公平感を生む原因となります。
施設で定められた規定を遵守してください。
- 不必要に二人きりの状況を作らない:
特に密室など、誤解を招きやすい状況は意識的に避ける配慮が求められます。
感情的な境界線の維持
利用者に寄り添うことは重要ですが、感情移入しすぎるとプロとしての客観的な判断が難しくなります。
「共感」と「同情」は異なります。
利用者の感情や状況を理解しようと努める「共感」は必要ですが、自分の感情まで一体化させてしまう「同情」や過度な自己開示は、依存関係を生むリスクを高めます。
境界線侵害(バウンダリー・クロッシング)の具体例
日々の業務の中で、意図せず境界線を越えてしまうことがあります。
以下に具体的な例を挙げ、適切な行動との違いを明確にします。
| 状況 | 適切な行動(OK) | 境界線を越えた不適切な行動(NG) |
|---|---|---|
| 連絡方法 | 施設のルールに従い、事業所の電話から連絡する。 | 自分のスマートフォンから個人のLINEで連絡する。 |
| 利用者への呼称 | 「〇〇さん」など、敬意を払った丁寧な呼び方をする。 | 馴れ馴れしくあだ名で呼んだり、タメ口で話したりする。 |
| 悩み相談 | 利用者の悩みや不安を傾聴し、支援計画に沿った助言を行う。 | 自分の恋愛や家庭の悩みを打ち明け、利用者に聞いてもらう。 |
| 感謝の表現 | 利用者からの「ありがとう」という言葉を素直に受け取る。 | 高価な贈り物や金品を受け取ってしまう。 |
| 身体的接触 | 介助など、業務上必要な範囲での身体的接触に留める。 | 必要以上に肩を組んだり、頭を撫でたりする。 |
信頼を深める適切なコミュニケーションとは
境界線を守ることは、利用者と機械的に接することではありません。
むしろ、プロフェッショナルな範囲で質の高いコミュニケーションを重ねることが、真の信頼関係を構築します。
恋愛感情とは異なる、人としての温かい信頼関係は、支援の質を向上させます。
- 傾聴と受容の姿勢:
利用者の話を途中で遮ったり、否定したりせず、まずは最後まで真摯に耳を傾けましょう。
「そう感じていらっしゃるのですね」と一度受け止める受容の姿勢が、利用者の安心感に繋がります。
- 肯定的な言葉を選ぶ:
「でも」「だって」といった否定的な接続詞を避け、「〇〇ということですね」「それなら、こうしてみるのはどうでしょう?」など、前向きで分かりやすい言葉を選んで対話を進めます。
- えこひいきをしない:
全ての利用者に対して公平・公正な態度で接することが、スタッフ個人、ひいては施設全体の信頼に繋がります。
特定の利用者とだけ長く話し込むといった行動は、周囲に不信感を与えます。
- 守れない約束はしない:
安易に「何でもやりますよ」「大丈夫です」といった言葉を使うのは避けましょう。
できないことは正直に伝え、代替案を一緒に考える誠実な姿勢が信頼を生みます。
公私の区別を明確にする意識
利用者と接する時間は、あくまで「業務」です。
自分は専門的なサービスを提供するプロフェッショナルであるという自覚を常に持つことが、公私混同を防ぐための最も重要な心構えです。
自分の役割を常に意識する
制服や名札は、単なる服装や道具ではありません。
それは、あなたが「施設のスタッフ」という公的な役割を担っている証です。
利用者から見れば、あなたは「〇〇さん」という個人である前に、支援を提供してくれる「職員」です。



この役割意識が、個人的な感情の暴走にブレーキをかけます。
オンとオフの切り替えを徹底する
勤務が終われば、自分自身のプライベートな時間です。
利用者のことを過度に考えすぎたり、業務外で連絡を取ったりすることは、公私の境界線を曖昧にします。
仕事の悩みは職場内で解決し、家に持ち帰らない習慣をつけましょう。



趣味や休息の時間をしっかり確保し、心身をリフレッシュさせることが、結果的に良い支援にも繋がります。
過度な自己開示は慎む
信頼関係を築くためにある程度の自己開示は有効ですが、その範囲には注意が必要です。
出身地や好きな食べ物といった当たり障りのない話題は問題ありません。
しかし、過去の恋愛遍歴や詳細な家族構成、経済状況といった極めてプライベートな情報を話すことは、利用者に過度な親近感を抱かせ、恋愛感情の引き金となる可能性があります。
まとめ
利用者とスタッフの恋愛は、立場の違いから深刻なトラブルに発展しやすいため、原則として禁止されています。
専門職としての倫理観と境界線を守り、公私の区別を徹底することが、双方の信頼関係と安全を守る上で最も重要です。
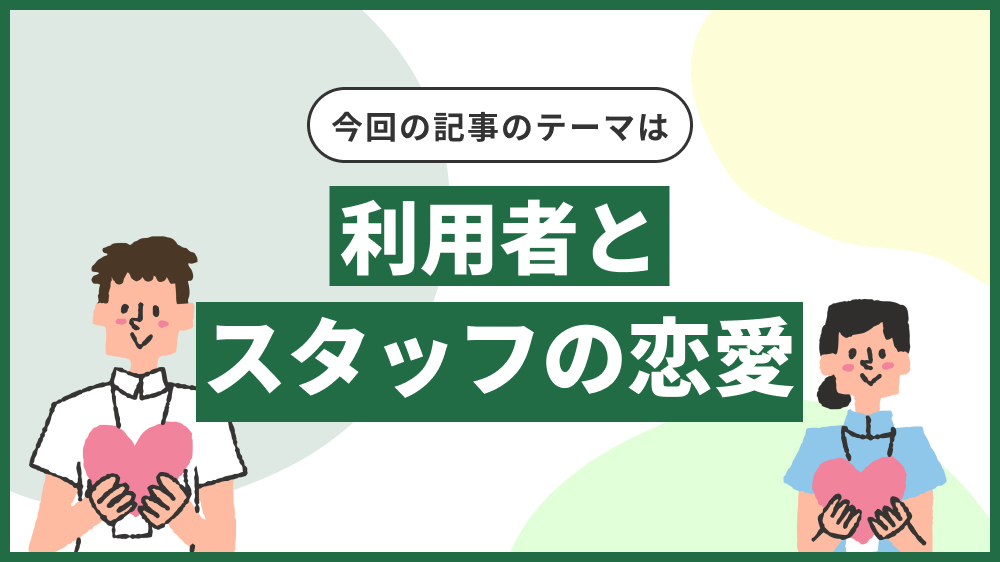









コメント