障害者からの暴力に悩んでいませんか。
暴力は障害特性や環境が原因で起こります。
この記事では、具体的な事例から原因を紐解き、ご自身の安全を守る対処法、限界になる前に頼れる相談先までを網羅的に解説します。
障害者からの暴力 具体的な事例

障害のある方から受ける暴力と一言でいっても、その背景にある障害の特性や状況は様々です。
ここでは、障害種別ごとに、実際にどのような状況で暴力が発生するのか、具体的な事例をみていきましょう。
知的障害・発達障害のある方からの暴力事例
知的障害や発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)のある方は、言葉で自分の気持ちや要求を伝えることが苦手だったり、感覚が過敏であったり、特定の物事への強いこだわりを持っていたりすることがあります。
これらの特性が、意図せず暴力という形で表出してしまうケースは少なくありません。
コミュニケーションの齟齬からくるパニック
自分の意思や不快感をうまく言葉で伝えられないもどかしさが、パニックや暴力の引き金になることがあります。
本人に悪意はなく、助けを求めるサインが歪んだ形で現れている場合も多いのです。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| 障害者支援施設(通所) | いつもと違う活動プログラムに不安を感じたが、その気持ちを職員にうまく伝えられなかった。 職員が次の活動を促したことで、不安が限界に達しパニックに陥った。 | 突然大声を出し、制止しようとした職員の腕を強くつねる、噛みつく。 |
| 家庭内 | 体調が悪いことを親に伝えたかったが、言葉が出なかった。 親がそれに気づかず普段通りに接したため、「分かってくれない」という絶望感から感情が爆発した。 | 泣き叫びながら自分の頭を壁に打ち付ける(自傷行為)。 止めに入った親を突き飛ばす。 |
こだわりを妨げられた際の他害行為
特定の手順や物の配置、日課などへの強いこだわりは、発達障害のある方にとって、混乱しやすい世界で安心感を得るための大切な術です。
このこだわりが予期せず崩されると、激しい不安や怒りを感じ、自分を守るために他者への攻撃という形で反応してしまうことがあります。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| グループホーム | 毎日同じ席で食事をすることが日課の利用者が、その日に限って別の利用者に席を取られてしまった。 職員が「今日だけ別の席で」と説得したが、受け入れられなかった。 | 椅子を蹴り倒し、近くにあった食器を床に叩きつける。 止めに入った職員に殴りかかる。 |
| 訪問介護 | 利用者の自宅で、ヘルパーがいつもと違う手順で掃除をしてしまった。 利用者は手順の変更に耐えられず、「やり直せ」と激しく抗議した。 | ヘルパーの手から掃除用具を奪い取り、壁に向かって投げつける。 大声で罵倒し続ける。 |
精神障害のある方からの暴力事例
精神障害のある方からの暴力は、病気の症状そのものが大きく影響しているケースが少なくありません。
特に、幻覚や妄想、激しい気分の波などは、本人の意思とは関係なく、暴力的な言動を引き起こす要因となり得ます。
症状による不安や恐怖心からくる暴力や暴言
統合失調症などの症状である幻聴や妄想は、本人にとっては紛れもない現実です。
「誰かに攻撃されている」「悪口を言われている」といった切迫した恐怖心から、自分を守るために防衛的に暴力を振るってしまうことがあります。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| 家庭内(親子間) | 「母親が食事に毒を入れている」という妄想にとらわれている息子。 母親が心配して食事を勧めたところ、攻撃されると思い込み、恐怖心から抵抗した。 | 食事の乗ったお盆をひっくり返し、「殺す気か!」と叫びながら母親を突き飛ばす。 |
| 精神科病院 | 「看護師は自分を監視する敵だ」という被害妄想を抱いている入院患者。 検温に来た看護師の行動を敵対行為と誤認し、身の危険を感じた。 | すれ違いざまに看護師の背中を殴り、「こっちを見るな」と暴言を吐く。 |
人間関係のストレスが引き金となるケース
感情のコントロールが難しくなる症状がある場合、対人関係のストレスが暴力の引き金になることもあります。
相手の些細な言動を、自分への否定や攻撃だと過敏に受け取ってしまい、感情が爆発してしまうのです。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| 就労移行支援事業所 | 他の利用者とのトラブルについて職員に相談したが、期待した対応が得られなかった。 「自分の気持ちを分かってくれない」という思いが怒りに変わり、職員に矛先が向いた。 | 面談室の机を強く叩き、「あんたのせいでめちゃくちゃだ!」と職員を長時間にわたって罵倒する。 |
高次脳機能障害のある方からの暴力事例
交通事故や脳卒中など、脳の損傷によって生じる高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい障害です。
感情のコントロールが難しくなる「感情失禁」や「易怒性(いどせい)」、新しいことを覚えられない「記憶障害」などが、暴力的な言動につながることがあります。
感情のコントロールが困難な場合の暴力
脳の損傷により、感情のブレーキが効きにくくなることがあります。
本人も怒りたくないのに、些細なきっかけで怒りが爆発してしまい、後から「なぜあんなことをしてしまったんだ」と深く後悔するケースも少なくありません。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| リハビリ施設 | 理学療法士とのリハビリ中、うまくできない課題が続いた。 療法士からの「もう少し頑張りましょう」という励ましの言葉を、自分を追い詰める言葉だと感じてしまった。 | 突然「うるさい!」と怒鳴り、リハビリ用のボールを壁に投げつける。 |
| 家庭内(夫婦間) | 妻から「さっき言ったことをまた忘れたの?」と何気なく言われた一言に、自分の障害を責められたように感じ、感情のコントロールを失った。 | テーブルを拳で殴りつけ、大声で妻を威嚇する。 |
記憶障害や注意障害が関連するケース
「何度も同じことを聞く」「約束を忘れる」といった記憶障害や注意障害の症状は、周囲との摩擦を生みやすくなります。
本人も失敗を繰り返すことに劣等感や焦りを感じており、それを指摘されることで追い詰められ、暴力という形で反応してしまうことがあります。
| 場所・状況 | 暴力に至る経緯 | 具体的な行動例 |
|---|---|---|
| 介護施設 | 記憶障害のある入所者が、数分前に食事を終えたことを忘れ、「まだ食事が出てこない」と何度もナースコールを押す。 対応した職員に「さっき食べましたよ」と言われ、嘘をつかれていると思い込んだ。 | 「私をだますのか」と怒り、職員の腕をつかんで離さない。 |
暴力に直面した時に今日からできる初期対応と対処法

障害のある方からの暴力に直面した時、頭が真っ白になり、どうすれば良いか分からなくなるのは当然のことです。
しかし、パニックはさらなる事態の悪化を招きかねません。
大切なのは、あなた自身と相手の安全を守り、事態を鎮静化させるための知識を事前に得ておくことです。
まずは自分の安全を確保する
何よりも優先すべきは、あなた自身の安全です。
支援者や家族としての責任感から自分を危険に晒してしまうケースがありますが、あなたが怪我をしてしまっては、その後の対応も支援もできません。
- 物理的な距離を取る:
相手が手を伸ばしても届かない距離、最低でも2メートル以上は離れることを意識しましょう。
いつでも逃げられるように、ドアや出口を背にしない、壁際に追い詰められない立ち位置を確保します。
- 障害物を間に置く:
テーブルや椅子、ソファなどを挟んで対峙するだけでも、直接的な暴力を防ぐことができます。
- 部屋から出る・避難する:
身の危険を感じたら、ためらわずにその場を離れましょう。
別室に避難し、ドアを閉めてください。
- 周囲に助けを求める:
一人で対応しようとせず、大声で助けを求めたり、防犯ブザーやアラームを鳴らしたりして、周囲に緊急事態であることを知らせましょう。
- 防御の姿勢をとる:
咄嗟に避けられない場合は、腕で顔や頭部、首などの急所を守る姿勢をとってください。
興奮を鎮めるクールダウンのテクニック
安全を確保した上で、次に行うべきは相手の興奮を鎮めることです。
暴力やパニックの背景には、本人の不安や混乱、不快感があります。
高圧的な態度や叱責は逆効果ですので、相手の感情に寄り添い、安心できる環境を整えることを目指しましょう。
| アプローチの種類 | 具体的な方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 言葉かけ(バーバルコミュニケーション) | ・穏やかで低いトーンの声で話す ・「〇〇しようか」と短い言葉で具体的に提案する ・「やめて」「だめ」といった否定語を避ける ・「嫌だったんだね」「びっくりしたね」と気持ちを代弁する | 興奮している相手に長い説明は届きません。 安心感を与える声で、分かりやすい言葉を選びましょう。 |
| 環境調整 | ・静かで刺激の少ない場所に移動する(クールダウンコーナーなど) ・テレビを消す、照明を少し暗くするなど感覚刺激を減らす ・本人が落ち着ける物(クッション、お気に入りのタオルなど)を渡す | 音や光、人の多さなどがパニックの原因になることがあります。 刺激源から遠ざけることで、落ち着きを取り戻しやすくなります。 |
| 非言語的コミュニケーション | ・真正面ではなく、少し斜めに立つ ・威圧感を与えないよう、目線を合わせすぎない ・ゆっくりとした動作を心がける ・腕を組んだり、仁王立ちしたりしない | 言葉以上に、態度や仕草が相手に伝わります。 敵意がないこと、落ち着いてほしいというメッセージを体全体で示しましょう。 |
組織で対応するための体制づくりと情報共有
特に介護施設や福祉事業所、学校などの組織において、暴力への対応を個人のスキルや責任に帰結させるのは極めて危険です。
職員の心身の安全を守り、支援の質を担保するためにも、組織全体で対応する体制を構築することが不可欠です。
暴力に関する対応マニュアルの作成
場当たり的な対応を防ぎ、誰でも一定水準の対応ができるように、事前にマニュアルを作成し、全職員で共有しておくことが重要です。
- 暴力・ハラスメントの定義:
どのような行為(暴言、威嚇、身体的暴力など)を問題行動として扱うか、組織内で共通認識を持ちます。
- 発生時の対応フロー:
暴力が発生した際の、初期対応からクールダウン、事後報告までの流れを時系列で具体的に定めます。
- 役割分担:
第一対応者、応援者、記録者、管理者への報告者など、緊急時の役割を明確にしておきます。 - 報告・記録の書式と手順:
「いつ、どこで、誰が、誰に、何をしたか」を客観的に記録するためのフォーマットを準備し、報告ルートを定めます。
この記録は、再発防止策の検討や、労災申請の際に重要な証拠となります。
- 緊急連絡先リスト:
管理職、本人の家族、相談支援専門員、市区町村の窓口、警察など、関係各所の連絡先を一覧にしておきます。
複数人での対応を徹底する
利用者からの暴力に対応する際は、原則として「複数人での対応」を徹底してください。
1対1の状況は、支援者にとって身体的・精神的リスクが非常に高まります。
応援を呼ぶための合言葉や合図(例:「〇〇さん、Bプランでお願いします」など)を決めておき、周囲の職員が速やかにサポートに入れる体制を整えましょう。
- 職員の安全確保:一人が暴力を受けても、もう一人が助けに入ったり、通報したりできます。
- 客観的な状況把握:複数の視点から状況を見ることで、冷静な判断がしやすくなります。
- 役割分担による効率的な対応:一人が利用者の対応にあたり、もう一人が他の利用者の安全確保や記録を行うなど、分担が可能です。
- 心理的負担の軽減:「一人ではない」という安心感が、対応する職員の精神的な支えになります。
やってはいけないNG対応
良かれと思って取った行動が、かえって相手の興奮を煽り、事態を悪化させてしまうことがあります。
以下に示すのは、暴力に直面した際に避けるべき対応です。
| NG対応 | なぜNGなのか | 代わりにどうするか |
|---|---|---|
| 感情的に叱責する・怒鳴る | 相手の不安や恐怖心を煽り、さらなるパニックや攻撃行動を引き起こす原因になります。 信頼関係も損なわれます。 | あくまで冷静に、低い声で穏やかに話しかける。 まずはクールダウンを優先する。 |
| 力で押さえつける(身体拘束) | 虐待防止法に抵触する可能性が非常に高い行為です。 相手に強い恐怖とトラウマを与え、事態を深刻化させます。 | 物理的な距離を取り、安全な場所へ避難する。 やむを得ない場合でも、組織のルールと法的な要件に従う。 |
| 原因を問い詰める | 興奮状態の相手は、論理的に状況を説明できません。 「なぜ?」という問い詰めは、本人をさらに混乱させるだけです。 | まずは相手の感情(「嫌だったね」など)を受け止め、安心させることに集中する。 原因の聞き取りは、落ち着いてから行う。 |
| 無視する・突き放す | 見捨てられたという絶望感や孤独感が、注目を引くためのより強い問題行動につながることがあります。 | 安全な距離を保ちつつも、「あなたのことを見ているよ」というメッセージを伝える。 落ち着くまで静かにそばにいる。 |
| その場しのぎの安易な約束をする | 「後で〇〇してあげるから」といった守れない約束は、その場は収まっても、後で破られることで不信感を増大させます。 | できない約束はしない。 「落ち着いたら、一緒にお茶を飲もう」など、具体的で実行可能な提案をする。 |
暴力への対応は、決して一人で抱え込むべき問題ではありません。
 編集長
編集長あなた自身の安全と心の健康を守るためにも、これらの対処法を参考に、周囲と連携しながら対応してください。
もう限界と感じる前に 必ず頼りたい専門機関・相談先一覧


障害者からの暴力に一人で耐え続ける必要はありません。
暴力がエスカレートし、あなた自身の心身が壊れてしまう前に、適切な専門機関に相談することが極めて重要です。
職場の悩みを相談できる窓口
介護施設や福祉事業所、特別支援学校などで働く支援者が暴力被害に遭った場合、まずは組織として対応を求めることが基本です。
しかし、職場内での解決が難しいケースも少なくありません。そのような場合に頼れる外部の窓口も知っておきましょう。
勤務先の相談窓口や上司
暴力やハラスメントに関する問題が発生した際、第一の相談先は勤務先の然るべき部署や上司です。
問題を個人で抱え込まず、組織の問題として共有することが、解決への道を拓きます。
報告・連絡・相談を徹底し、正式な記録として残してもらうよう依頼しましょう。



相談することで、複数人での対応体制の構築や、担当の変更、配置転換といった具体的な安全確保策につながる可能性があります。
労働組合や労働基準監督署
職場に相談しても改善が見られない、または相談しづらい環境にある場合は、外部の機関を頼ることを検討してください。
労働者の権利を守るための専門機関が、あなたの力になってくれます。
| 相談先 | 相談できる内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 労働組合 | 職場環境の改善要求、会社との交渉、ハラスメント対策など | 労働者の立場に立ち、団体交渉などを通じて会社側に具体的な改善を求めることができます。 勤務先に労働組合がない場合は、個人で加入できるユニオン(合同労働組合)もあります。 |
| 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内) | 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、あらゆる分野の労働問題 | 専門の相談員が面談もしくは電話で対応してくれます。 予約不要・無料で利用でき、法的なアドバイスや他の専門機関の紹介も受けられます。 |
| 労働基準監督署 | 労働安全衛生法違反(暴力により労働者の安全や健康が脅かされている場合)、労災保険の給付に関する相談など | 事業所に対して、労働安全衛生法などに基づき、調査や指導・是正勧告を行う権限を持っています。 暴力によって怪我をしたり精神疾患を発症したりした場合は、労災認定の相談も可能です。 |
家族が相談できる公的機関
在宅で障害のある家族の介護や支援を行っている場合、社会から孤立し、一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。
しかし、あなたと家族を支えるための公的な支援制度や相談窓口が必ずあります。
市区町村の障害福祉担当窓口
お住まいの市区町村の役所にある障害福祉課や福祉課は、最も身近で基本的な相談窓口です。
障害のある方やその家族が利用できる様々な福祉サービス(居宅介護、短期入所(ショートステイ)、行動援護など)に関する情報提供や利用申請の受付を行っています。
家族の休息を確保する「レスパイトケア」の観点からも、これらのサービスを積極的に活用することが大切です。
障害者相談支援事業所
障害者相談支援事業所は、障害のある方やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う専門機関です。
専門の相談支援専門員が、一人ひとりの状況に合わせた「サービス等利用計画」の作成を支援し、適切な福祉サービスにつながるようサポートしてくれます。
どこに相談すればよいか分からない場合でも、まずはこちらに連絡すれば、適切な機関へつないでもらえます。



お住まいの市区町村の窓口で紹介してもらうことが可能です。
保健所や精神保健福祉センター
特に、精神障害のある家族からの暴力や暴言に悩んでいる場合、保健所や精神保健福祉センターが重要な相談先となります。
これらの機関には、精神保健福祉士や保健師、医師などの専門職が在籍しており、ご本人への適切な医療へのつなぎ方や、家族としての関わり方について具体的なアドバイスを受けることができます。
家族向けの相談会や教室を開催している場合もあります。
法的な対応を考えたい時の相談先
暴力行為がエスカレートし、ご自身の生命や身体に危険が及ぶような深刻な状況では、法的な対応も視野に入れる必要があります。
身を守ることを最優先に行動してください。
緊急時は警察に相談する
暴力によって怪我をさせられた、命の危険を感じるほどの脅迫を受けたなど、明らかに犯罪行為に該当し、緊急の対応が必要な場合は、ためらわずに110番通報してください。
あなたの安全を確保することが何よりも優先されます。
緊急ではないものの、暴力行為について警察に相談したいという場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用する方法もあります。



状況を説明し、今後の対応についてアドバイスを求めることができます。
弁護士への相談(法テラスなど)
暴力行為による損害賠償請求や、相手の判断能力が著しく低下している場合の成年後見制度の利用など、法的な手続きを検討したい場合は、弁護士への相談が有効です。
障害者問題に詳しい弁護士を探すのが望ましいでしょう。
また、経済的な理由で弁護士への相談をためらっている場合は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所である「日本司法支援センター(法テラス)」を利用できます。



収入などの条件を満たせば、無料で法律相談を受けられたり、弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらえたりする制度があります。
まとめ
障害者からの暴力に悩むのはあなた一人ではありません。
暴力の背景には障害特性や環境が複雑に絡み合っており、一人で抱え込まず専門機関へ相談することが解決の第一歩です。
自身の安全と心のケアを最優先し、適切な支援に繋げましょう。
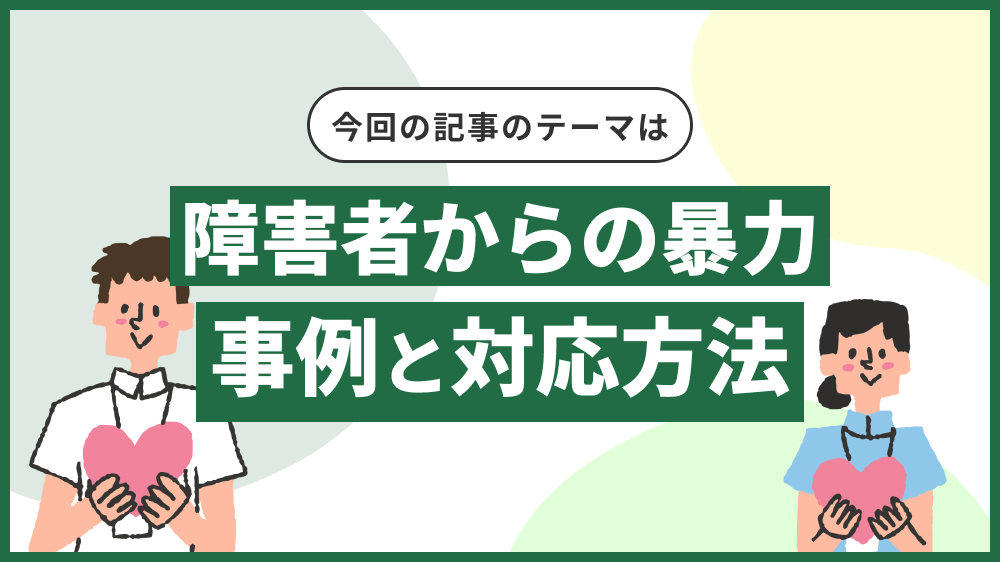








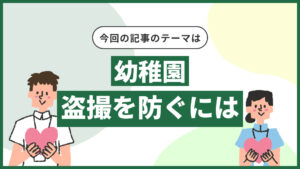
コメント