就労移行支援でのいじめは、適切な対処と相談で解決できます。
この記事では、具体的な対処法、相談窓口、いじめを防ぐ事業所選びのポイントを解説。
一人で悩まず、安心して通うための具体的な方法がわかります。
就労移行支援でのいじめの実態と現状

就労移行支援は、障害や難病のある方が就職に向けて必要なスキルを学び、安心して社会に踏み出すための大切な場所です。
しかし、残念ながら、その中で利用者同士の人間関係のトラブル、特に「いじめ」が発生してしまうケースは決して少なくありません。
本来、支援を受けながら前向きに訓練に取り組むべき環境で、なぜいじめが起きてしまうのでしょうか。
 編集長
編集長この章では、就労移行支援におけるいじめの具体的な種類や、そうした問題が起こりやすい環境的背景、そしてその現状について詳しく解説します。
就労移行支援でよくあるいじめの種類
一口に「いじめ」と言っても、その形は様々です。
就労移行支援の場では、学校や職場で見られるようないじめと同様のものが起こり得ます。
もしあなたが「これって、もしかしていじめ?」と感じているなら、まずはどのような行為がいじめに該当するのかを知ることが大切です。
| いじめの種類 | 具体的な行為の例 |
|---|---|
| 精神的な攻撃 | ・悪口や陰口を言われる、噂を流される ・人格や能力、障害の特性を否定するようなことを言われる ・わざと聞こえるように嫌味を言われる ・威圧的な態度を取られる |
| 人間関係からの切り離し | ・挨拶をしても無視される、会話に入れてもらえない(仲間外れ) ・グループワークなどで意図的に孤立させられる ・連絡事項などを自分だけ知らされない |
| 個の侵害 | ・プライベートなことをしつこく聞かれる ・障害や病気について、根掘り葉掘り質問される ・本人の許可なく持ち物を見たり、触ったりする |
| 物理的な嫌がらせ・攻撃 | ・私物を隠されたり、壊されたりする ・わざとぶつかってきたり、足を出して転ばせようとしたりする ・訓練や作業の邪魔をする |
これらの行為は、一つひとつは些細に見えるかもしれません。
しかし、継続的に行われることで心に大きな傷を残し、訓練への意欲を失わせる深刻な問題となります。
特に、障害特性をからかったり、それを理由に仲間外れにしたりする行為は、個人の尊厳を深く傷つける悪質ないじめと言えるでしょう。
いじめが発生しやすい環境と背景
では、なぜサポートを受けるべき就労移行支援の場で、いじめが発生してしまうのでしょうか。
その背景には、就労移行支援事業所ならではの環境的な要因が複雑に絡み合っています。
- 多様な利用者の集まり
就労移行支援には、年齢、性別、これまでの経歴、そして障害の種類や程度も様々な人々が集まります。
異なる価値観や背景を持つ人々が同じ空間で過ごす中で、コミュニケーションの齟齬や誤解が生じやすく、それが人間関係の摩擦につながることがあります。
- 閉鎖的な人間関係
多くの事業所では、毎日決まったメンバーが同じ場所で長時間過ごします。
このような環境は、一度人間関係がこじれると逃げ場がなく、特定の個人がターゲットにされやすい状況を生み出す可能性があります。
関係性が固定化しやすく、孤立感が深まりやすいのです。
- 就職への焦りやストレス
利用者それぞれが「早く就職したい」という目標と共に、将来への不安や焦り、体調の波といったストレスを抱えています。
こうした精神的な負荷が、他者への不寛容や攻撃的な態度として表れてしまうことがあります。
- コミュニケーションの課題
障害の特性上、対人コミュニケーションに苦手意識を持つ利用者は少なくありません。
自分の意図がうまく伝わらなかったり、相手の言動を誤解してしまったりすることが、意図しないトラブルの引き金になるケースも見られます。
- 事業所スタッフの介入不足
利用者間の微妙な空気の変化や、水面下で起きているいじめの兆候にスタッフが気づけない、あるいは気づいていても「利用者同士の問題」として適切な介入をためらってしまう場合があります。
スタッフの人数不足や対応スキルの問題も、いじめが深刻化する一因となり得ます。
就労移行支援でいじめに遭った時の具体的な対処法


就労移行支援事業所でいじめに遭うことは、心身ともに大きな苦痛を伴います。
しかし、一人で抱え込まず、適切に対処することで状況を改善できる可能性があります。
ここでは、いじめに直面した際に取るべき具体的な行動を4つのステップに分けて詳しく解説します。



あなたの心の安全と平穏を取り戻すため歩として、ぜひ参考にしてください。
冷静に状況を記録する方法
いじめの事実を客観的に示すためには、まず状況を記録することが非常に重要です。
記録は、事業所のスタッフに相談する際の具体的な説明資料となるだけでなく、万が一法的な対応を検討する場合の重要な証拠にもなり得ます。
感情的にならず、事実を淡々と書き留めることを心がけましょう。
記録すべき項目(5W1H)
いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたのか、そして自分がどう感じたのかを具体的に記録します。
以下の表を参考に、ノートやスマートフォンのメモアプリ、パソコンの文書作成ソフトなどを活用して記録を続けてください。
| 記録項目 | 記録内容の具体例 |
|---|---|
| 日時(When) | 2023年10月26日(木)午前10時15分頃 |
| 場所(Where) | 事業所内のPC訓練室、休憩スペースなど |
| 加害者(Who) | 利用者のAさん、Bさんグループなど(複数いる場合は全員の名前) |
| 目撃者(Who) | 利用者のCさん、通りかかった支援員のDさんなど(いる場合のみ) |
| いじめの内容(What/How) | 「そんなこともできないのか」と大きな声で言われた。持ち物を隠された。無視された。LINEグループから外された。など、言動や行為を具体的に記述する。 |
| 心身への影響 | 強い不安を感じた。腹痛がした。夜眠れなくなった。事業所に行くのが怖くなった。など、自分の気持ちや体調の変化を正直に書く。 |
記録する際のポイント
- 継続する:
一度だけでなく、いじめが続く限り記録を続けましょう。
継続的な記録は、いじめの悪質性や常習性を示す証拠となります。
- 客観的に書く:
「むかつく」といった感情的な言葉だけでなく、「〜と言われて悲しかった」「屈辱を感じた」など、事実とそれによって生じた感情を分けて書くと、後から見返したときに状況を整理しやすくなります。
- 証拠を保管する:
暴言が書かれたメモや、SNS・LINEでのやり取りなどは、スクリーンショットを撮って画像として保存しておきましょう。
音声データが録音できる場合は、ボイスレコーダーの利用も有効です。
事業所スタッフへの相談手順
記録がある程度まとまったら、次は事業所のスタッフに相談するステップに進みます。
信頼できるスタッフに勇気を出して声をかけることが、問題解決の大きな一歩となります。
まずは誰に相談するかを決めます。
日頃からよく話す担当の支援員や、事業所全体の責任者であるサービス管理責任者(サビ管)などが主な相談相手になります。
相談する際は、「少しご相談したいことがあるのですが、今お時間よろしいでしょうか?」あるいは「面談の時間を少し長めに取っていただけませんか?」などと切り出し、他の利用者に聞かれない個室などで話せるように依頼しましょう。
相談する前に、作成した記録を見ながら、何を伝え、どうしてほしいのかを整理しておきましょう。
要点をメモにまとめておくと、緊張してもうまく話せます。
感情的になりすぎず、冷静に事実を伝える準備をすることが大切です。
面談では、準備した記録をもとに、いつ、誰から、どのようなことをされているのかを具体的に伝えます。
ここで重要なのは、相手を非難するのではなく、「〜という行為を受けて、自分はこう感じており、訓練に集中できず困っている」という「I(アイ)メッセージ」で伝えることです。
これにより、スタッフも客観的に状況を把握しやすくなります。
相談の最後には、「今後、どのように対応していただけるか」を必ず確認しましょう。
例えば、「加害者への聞き取りや指導」「席の配置変更」「スタッフの巡回強化」など、具体的な対応策を提示してもらうことが重要です。
いつまでに対応してくれるのか、その後の進捗報告はしてもらえるのかなども確認しておくと安心です。
他の利用者との関係改善のアプローチ
いじめの相手と無理に関係を改善しようとすることは、さらなるストレスの原因になる可能性があります。
まずは自分の心の安全を最優先に考え、適切な距離を保つことが基本です。
- 物理的な距離を置く:
可能であれば、いじめの相手とは席を離してもらう、グループワークで別の組にしてもらうなど、スタッフに相談して物理的な距離を確保しましょう。
- 関わりを最小限にする:
挨拶など最低限の礼儀は保ちつつ、必要以上に関わらないように意識します。
相手の言動に過剰に反応せず、冷静に受け流す姿勢も時には必要です。
- アサーションを学ぶ:
就労移行支援のプログラムにコミュニケーションスキル向上の訓練があれば、積極的に参加しましょう。
自分の意見を尊重しつつ、相手のことも配慮しながら主張する「アサーティブ・コミュニケーション」の技術は、今後の人間関係においても役立ちます。
ただし、これらのアプローチは、あくまで自分自身を守るためのものです。
関係改善を強要されたり、自分で解決するように言われたりした場合は、事業所の対応が不適切である可能性も考えられます。
精神的なケアとセルフケアの重要性
いじめは、自尊心を傷つけ、深刻な精神的ダメージを与えます。
問題解決に向けて行動すると同時に、自分自身の心をケアすることも決して忘れないでください。
自分でできるセルフケアの方法
ストレスや不安を少しでも和らげるために、日常生活の中で意識的にリラックスできる時間を取り入れましょう。
- 信頼できる人に話す:
事業所の問題とは別に、家族や親しい友人など、安心して話せる人に気持ちを聞いてもらうだけでも心は軽くなります。
- 趣味に没頭する:
好きな音楽を聴く、映画を見る、散歩をする、絵を描くなど、自分が楽しいと感じることに集中する時間を作りましょう。
- 十分な休息をとる:
心と体はつながっています。
質の良い睡眠をとり、栄養バランスの取れた食事を心がけることが、精神的な回復力を高めます。
- リラクゼーション法を試す:
深呼吸や瞑想、ヨガ、アロマテラピーなど、自分に合ったリラックス方法を見つけるのも効果的です。
専門家のサポートを活用する
「夜眠れない」「食欲がない」「何をしても楽しくない」といった状態が続く場合は、セルフケアだけでは限界かもしれません。
そのような時は、決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してください。
かかりつけの医師や、心療内科・精神科のクリニック、地域のカウンセリング機関などに相談することで、専門的な視点から適切なサポートを受けることができます。
事業所のスタッフに相談し、医療機関との連携を依頼することも可能です。
就労移行支援でのいじめ相談窓口一覧


就労移行支援事業所でいじめに遭った際、一人で抱え込むことは最も避けるべきです。
大切なのは、信頼できる場所に勇気を出して相談することです。
ここでは、状況に応じて選べる相談窓口を「事業所内」「行政機関」「民間機関」「緊急相談窓口」の4つに分けて具体的に解説します。
事業所内での相談体制
まず最初に検討すべきなのが、現在利用している事業所内の相談体制です。
多くの事業所では、利用者からの相談に対応するスタッフが配置されています。
相談する相手としては、主に以下のような職種のスタッフが考えられます。
- 生活支援員:
日常生活や対人関係の悩みを相談しやすい、最も身近な存在です。
- 職業指導員:
訓練中のトラブルや人間関係について相談できます。
- サービス管理責任者(サビ管):
事業所全体の支援計画を管理する責任者です。
支援員に相談しにくい内容や、事業所全体の課題として対応してほしい場合に適しています。
もし事業所内のスタッフに相談しても改善が見られない、または相談しづらい雰囲気がある場合は、外部の機関を頼ることをためらわないでください。
行政機関への相談窓口
事業所内での解決が難しい場合や、事業所の対応に不信感がある場合は、公的な行政機関に相談するのが有効です。
行政機関は事業所に対して指導・監督する権限を持っているため、中立的な立場から問題解決をサポートしてくれます。
| 相談窓口名 | 相談できる内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 市区町村の障害福祉担当課 | 就労移行支援サービスの利用に関する全般的な相談、事業所への苦情、事業所変更の相談など。 | お住まいの市区町村の役所に設置されています。 まずはここへの相談が基本となります。 |
| 都道府県・指定都市の運営適正化委員会 | 福祉サービスに関する苦情解決を専門とする第三者機関。 事業者との話し合いの仲介や助言を行います。 | 中立的な立場で調査や助言を行ってくれるため、客観的な解決が期待できます。 |
| 法務局「みんなの人権110番」 | いじめや嫌がらせが人権侵害にあたると感じる場合の相談。 | 電話番号は「0570-003-110」です。 専門の相談員が対応してくれます。 |
| ハローワーク(公共職業安定所) | 事業所変更を検討している際の相談や、他の就労支援サービスに関する情報提供。 | 障害者専門の相談窓口が設置されているハローワークもあります。 |
民間の相談機関とサポート団体
行政機関だけでなく、民間のNPO法人や支援団体も頼りになる存在です。
同じような悩みを持つ仲間と繋がったり、より専門的な視点からアドバイスを受けられたりするメリットがあります。
| 相談窓口の種類 | 相談できる内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 障害当事者団体・家族会 | 同じ障害のある当事者やその家族からの実体験に基づいたアドバイス、ピアサポート。 | 各障害種別や地域ごとに団体が存在します。共感を得やすく、精神的な支えになります。 |
| 労働問題に取り組むNPO法人 | いじめやハラスメントに関する専門的な相談、解決に向けたサポート。 | 「NPO法人 労働相談センター」など、全国で活動する団体があります。 |
| 地域の障害者支援センター | 障害のある方の地域生活を総合的に支援する拠点。 様々な悩みについて相談できます。 | 事業所だけでなく、生活全般の困りごとについて幅広く相談に乗ってくれます。 |
24時間対応の緊急相談窓口
いじめによる精神的な苦痛が大きく、今すぐに誰かに話を聞いてほしい、気持ちが追い詰められているという場合は、24時間対応の緊急相談窓口を利用してください。
あなたの心を守ることを最優先に考えましょう。
匿名での相談も可能です。
| 相談窓口名 | 特徴 | 連絡先 |
|---|---|---|
| こころの健康相談統一ダイヤル | 厚生労働省が支援する公的な電話相談窓口。 全国どこからでも地域の相談機関に繋がります。 | 0570-099-777(曜日・時間は都道府県によって異なります) |
| いのちの電話 | ボランティアが運営する無料・匿名の電話相談。 24時間対応している地域もあります。 | ナビダイヤル: 0570-783-556 フリーダイヤル: 0120-783-556(毎月10日) |
| SNS相談(生きづらびっと等) | 電話が苦手な方向けに、LINEなどのSNSで相談できる窓口です。 | 各団体のウェブサイトから友達登録して利用します。 対応時間は団体により異なります。 |
一つの窓口で解決しなくても、諦めずに別の窓口を頼ってみてください。
いじめ被害を受けた場合の法的対応方法


就労移行支援事業所でのいじめは、単なる人間関係のトラブルではなく、法的に対処すべき人権侵害となる場合があります。
事業所内での解決が難しい、あるいは被害が深刻な場合には、法的措置を視野に入れることも自分の心と権利を守るための重要な選択肢です。
ここでは、いじめ被害を受けた場合の具体的な法的対応方法について解説します。
証拠収集の重要性と具体的な方法
法的措置を講じる上で、いじめがあったことを客観的に証明するための「証拠」が何よりも重要になります。
「言った、言わない」の水掛け論を避け、被害の事実を第三者に明確に示すために、冷静に証拠を集めましょう。
精神的に辛い作業ですが、ご自身の権利を守るために非常に有効です。
| 証拠の種類 | 具体的な収集方法とポイント |
|---|---|
| 記録(日記・メモ) | 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、事実を時系列で具体的に記録します。 「〇月〇日〇時頃、訓練室で〇〇さんから『仕事ができない役立たず』と皆の前で言われた」など、詳細に残しましょう。 感情的な記述だけでなく、客観的な事実を書き留めることが重要です。 |
| 音声データ | 暴言や脅迫的な発言を、ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリで録音します。 相手に無断での録音も、自分を守るための証拠収集であれば法的に認められる可能性が高いです。 ただし、公開方法には注意が必要です。 |
| メール・SNSの記録 | いじめに関するメールやLINE、その他のSNSでのやり取りは、全文がわかるようにスクリーンショットで保存します。 送信日時や相手のアカウント名が明確にわかるように撮影することがポイントです。 |
| 物的証拠の写真 | 持ち物を壊されたり、落書きされたりした場合は、その状態を写真や動画で撮影します。 いつ、どこで、誰にされた可能性があるかもメモしておきましょう。 |
| 医師の診断書 | いじめによる精神的ストレスで心身に不調をきたした場合(不眠、食欲不振、うつ症状など)、心療内科や精神科を受診し、診断書をもらいましょう。 いじめと症状の因果関係を証明する重要な証拠となります。 暴力を受けた場合は、怪我の診断書も必要です。 |
| 第三者の証言 | いじめの現場を目撃していた他の利用者やスタッフがいれば、証言してもらえるか相談してみましょう。 誰が、いつ、どこで、何を見ていたかを具体的に記録した書面に署名をもらえると、より強力な証拠となります。 |
法的相談が可能な機関
いじめ問題について法的なアドバイスを受けたい場合、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが第一歩です。
無料で相談できる窓口もありますので、積極的に活用しましょう。
| 相談機関名 | 特徴と相談できる内容 |
|---|---|
| 法テラス(日本司法支援センター) | 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。 経済的な余裕がない場合でも、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できる場合があります。 まずどこに相談すればよいか分からない場合に最適です。 |
| 弁護士会 | 各都道府県の弁護士会が運営する法律相談センターで、有料(30分5,000円程度が目安)ですが、直接弁護士に相談できます。 労働問題や人権問題に詳しい弁護士を紹介してもらえることもあります。 |
| 法務局「みんなの人権110番」 | いじめや嫌がらせなどの人権問題に関する相談窓口です。 法務局の職員や人権擁護委員が相談に応じ、事案によっては調査や救済措置(当事者間の関係調整、助言、勧告など)を行ってくれます。 電話やインターネットで相談が可能です。 |
| 市区町村の無料法律相談 | 多くの市区町村では、弁護士による無料の法律相談会を定期的に開催しています。 日程や予約方法は、お住まいの自治体のウェブサイトや広報誌で確認できます。 身近な場所で気軽に相談できるのがメリットです。 |
損害賠償請求の可能性
いじめによって精神的・肉体的な損害を受けた場合、加害者本人や監督責任を怠った就労移行支援事業所に対して、損害賠償(慰謝料など)を請求できる可能性があります。
これは、民法上の「不法行為」や「安全配慮義務違反」に基づくものです。
請求できる損害の主な内容
- 治療費:
いじめが原因で通院した場合の診察料、薬代など。
- 慰謝料:
受けた精神的苦痛に対する金銭的な賠償。
いじめの態様、期間、被害の程度などを考慮して金額が算定されます。
- 逸失利益:
いじめがなければ得られたであろう利益。
例えば、いじめが原因で就労移行支援を辞めざるを得なくなり、就職の機会を失った場合の損害などが考えられます。
実際に損害賠償請求を行うかどうかは、収集した証拠を基に弁護士などの専門家と十分に相談し、見通しを確認した上で慎重に判断することが重要です。
いじめ経験者の体験談と解決事例


就労移行支援でのいじめは、決して他人事ではありません。
しかし、多くの人が適切な対処によって問題を乗り越え、新たな一歩を踏み出しています。
ここでは、実際にいじめを経験した方々の体験談と、そこから得られる解決のヒントを具体的な事例としてご紹介します。
実際にいじめを乗り越えた成功事例
Aさん(20代・発達障害)は、特定の利用者グループから無視されたり、持ち物を隠されたりするいじめに悩んでいました。
当初は「自分が悪いのかもしれない」と一人で抱え込み、事業所へ行くのが日に日に辛くなっていきました。
しかし、このままでは就職どころではないと考え、勇気を出して担当の支援員に相談することを決意しました。
相談を受けた支援員は、まずAさんの話を親身に聞き、感情を受け止めた上で、具体的な事実関係を整理しました。
「いつ、どこで、誰に、何をされたか」を記録することを勧め、Aさんはスマートフォンのメモ機能を活用して冷静に記録を続けました。
数日分の記録が溜まった段階で、支援員は事業所の責任者も交えて対策会議を実施。
事業所として以下の対応を行いました。
・加害者とされる利用者グループとの個別面談を実施し、事実確認と指導を行った。
・グループワークの座席配置を見直し、Aさんが安心して過ごせる環境を整備した。
・利用者全員に向けて、改めて事業所内でのルールや他者への配慮についてのアナウンスを行った。
・Aさんに対しては、定期的なカウンセリングの機会を設け、精神的なケアを継続した。
これらの対応により、いじめ行為は徐々になくなりました。
Aさんは精神的な安定を取り戻し、再び安心して訓練に集中できるようになりました。
事業所変更で環境改善した事例
Bさん(30代・うつ病)のケースでは、事業所そのものが合わないという問題がありました。
特定のスタッフから「そんなことだから就職できないんだ」といった高圧的な指導や人格を否定するような発言を繰り返され、精神的に追い詰められていました。
責任者に相談しても「熱心な指導の一環」として真剣に取り合ってもらえず、孤立感を深めていました。
状況が改善しないことに絶望したBさんは、お住まいの市区町村の障害福祉課に相談しました。
担当者はBさんの話を丁寧に聞き、事業所での出来事がパワーハラスメントにあたる可能性を指摘。
そして、無理に通い続けるのではなく「事業所を変更する」という選択肢があることを教えてくれました。
Bさんは障害福祉課のサポートを受けながら、複数の事業所の見学や体験利用に参加。
その中で、スタッフが一人ひとりのペースを尊重し、穏やかな雰囲気でコミュニケーションが取れる事業所を見つけました。
手続きを経て事業所を変更した結果、Bさんを取り巻く環境は劇的に改善されました。
新しい事業所では、スタッフとの信頼関係を築きながら、自分のペースで訓練を進めることができました。
自信と自己肯定感を取り戻したBさんは、ストレスなく通所を続け、最終的には体調に合った職場への就職に成功しました。
事業所がどうしても合わない、相談しても改善が見られない場合は、環境そのものを変える「事業所変更」が有効な解決策となり得ます。
専門機関のサポートで解決した事例
Cさん(40代・精神障害)は、他の利用者から金銭を要求されたり、私的な用事を強要されたりするという、より深刻ないじめに直面していました。
断ると暴言を吐かれるため、恐怖心から要求に応じてしまうこともありましたが、事業所に相談しても「利用者同士の個人的なトラブル」として、積極的な介入をしてもらえませんでした。
身の危険を感じたCさんは、無料法律相談が可能な「法テラス(日本司法支援センター)」に連絡。
弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることにしました。
弁護士は、Cさんが置かれている状況が単なるいじめではなく、恐喝や強要といった犯罪行為に該当する可能性があると判断し、具体的な解決プロセスを提示しました。
| ステップ | 具体的な対応内容 | 目的と効果 |
|---|---|---|
| Step 1: 証拠の収集 | 弁護士の助言のもと、ICレコーダーでの会話の録音、要求された日時や金額、内容のメモを作成。 | 客観的な証拠を確保し、法的手続きや交渉を有利に進めるため。 |
| Step 2: 内容証明郵便の送付 | 弁護士名で加害者に対し、嫌がらせ行為の即時中止を求める内容証明郵便を送付。 | 法的措置を辞さないという強い意志を示し、相手に心理的圧力をかける。 |
| Step 3: 事業所への申し入れ | 弁護士が代理人として事業所と面談。利用者の安全を確保する義務(安全配慮義務)を怠っていることを指摘し、加害者との隔離など具体的な再発防止策を強く要請。 | 事業所に問題の深刻さを認識させ、組織としての責任ある対応を促す。 |
| Step 4: 行政・警察との連携 | 状況が改善しない場合、市区町村の障害福祉課への通報や、警察の生活安全課への相談も視野に入れることを加害者と事業所の双方に伝達。 | 外部機関の介入を示唆することで、迅速な問題解決を促す。 |
弁護士という専門家が介入したことで、事業所の対応は一変しました。
事態を重く受け止めた事業所は、直ちに加害者への厳重な指導と、Cさんとの接触を避けるためのクラス分けを実施。
結果として、加害者からの嫌がらせは完全になくなり、Cさんは再び安心して通所できるようになりました。
この事例のように、いじめの内容が悪質・深刻である場合や、事業所が適切に対応しない場合には、弁護士などの専門機関に相談することが、身の安全を守り、問題を根本的に解決するための極めて有効な手段となります。
まとめ
就労移行支援でのいじめは一人で悩まず、相談することが解決への第一歩です。
事業所や行政機関など相談先は多数あります。
適切な対処法を知り、自分に合った環境を選ぶことで、安心して訓練に集中できます。
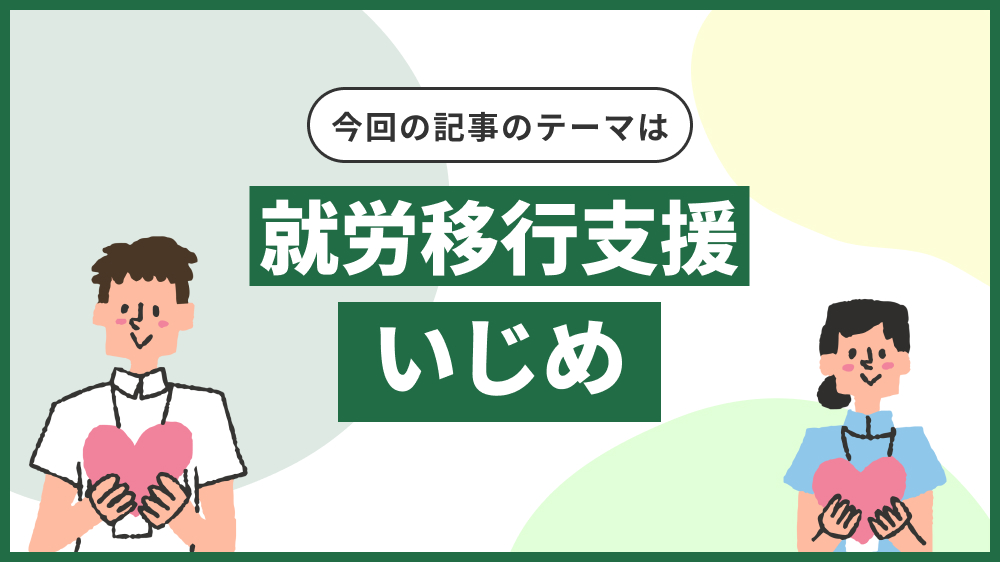









コメント