この記事では
- 差別的思考の背景にある心理
- 社会構造
- 歴史的背景
を解き明かし、その影響と私たちができることを考えます。
 編集長
編集長無意識の偏見から生まれる差別的言動をなくし、共生社会の実現に向けて、まずは自分自身の内面と向き合う必要性を理解しましょう。
無意識の偏見と差別「障害者を馬鹿にする」心理


私たちは日常生活の中で、気づかぬうちに偏見や差別的な感情を抱いていることがあります。
「障害者を馬鹿にする」という心理も、その一つです。
これは、悪意から生まれるものばかりではなく、無意識のうちに形成された偏見や差別が根底にある場合が多く見られます。



ここでは、その心理メカニズムについて深く掘り下げていきます。
可視化されるものとされないもの
障害には、視覚的に認識しやすいものと、そうでないものがあります。
例えば、車椅子を利用している人や、視覚障害のある人は、比較的容易に障害を認識できます。
しかし、発達障害や精神障害などは、外見からは分かりにくいため、周囲の理解が得られにくい傾向にあります。
このような「見えない障害」を持つ人々は、周囲から誤解されたり、偏見の目にさらされたりする可能性が高くなります。
例えば、発達障害のある子どもが公共の場でパニックを起こした場合、「しつけがなっていない」と非難されるケースがありますが、これは障害特性への無理解からくる偏見に基づくものです。
また、精神障害のある人が、周囲に理解されずに孤立してしまうケースも少なくありません。



このように、可視化されない障害に対する理解不足が、「障害者を馬鹿にする」心理につながる可能性があります。
恐怖と不安の投影
人は、自分にとって未知のものや理解できないものに対して、恐怖や不安を抱くことがあります。
障害もまた、多くの人にとって未知の領域であり、理解が難しいものです。
そのため、障害に対する恐怖や不安を、無意識のうちに「馬鹿にする」という形で表現してしまうことがあります。
これは、自分自身の不安や恐怖から目を背けるための、一種の防衛機制と言えるでしょう。
自分を守るための防衛機制
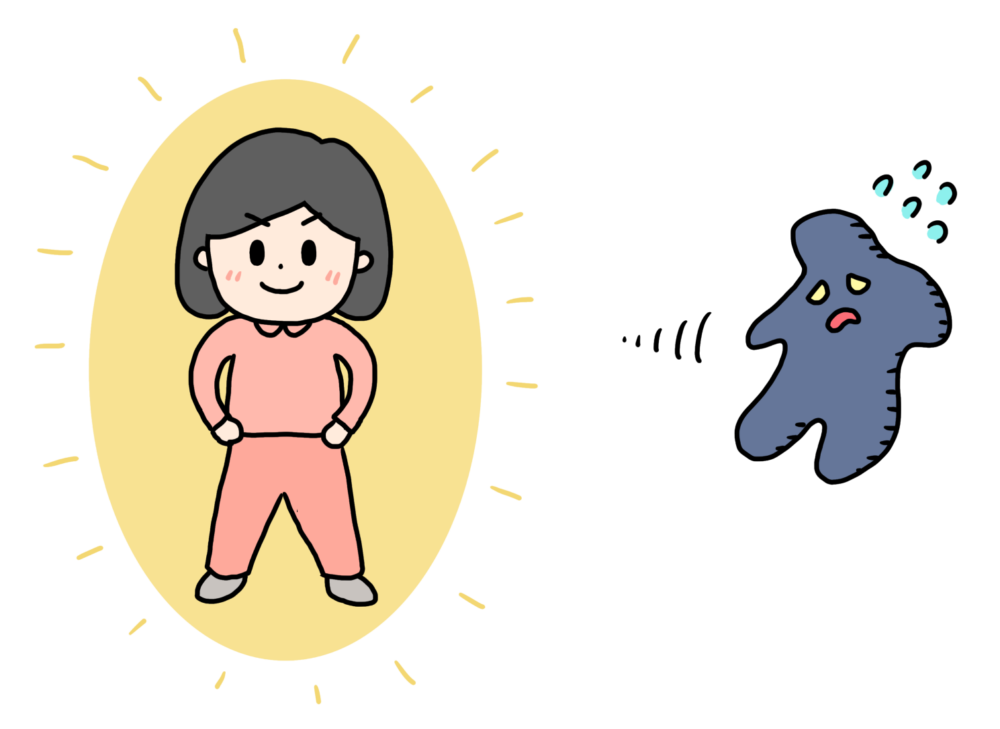
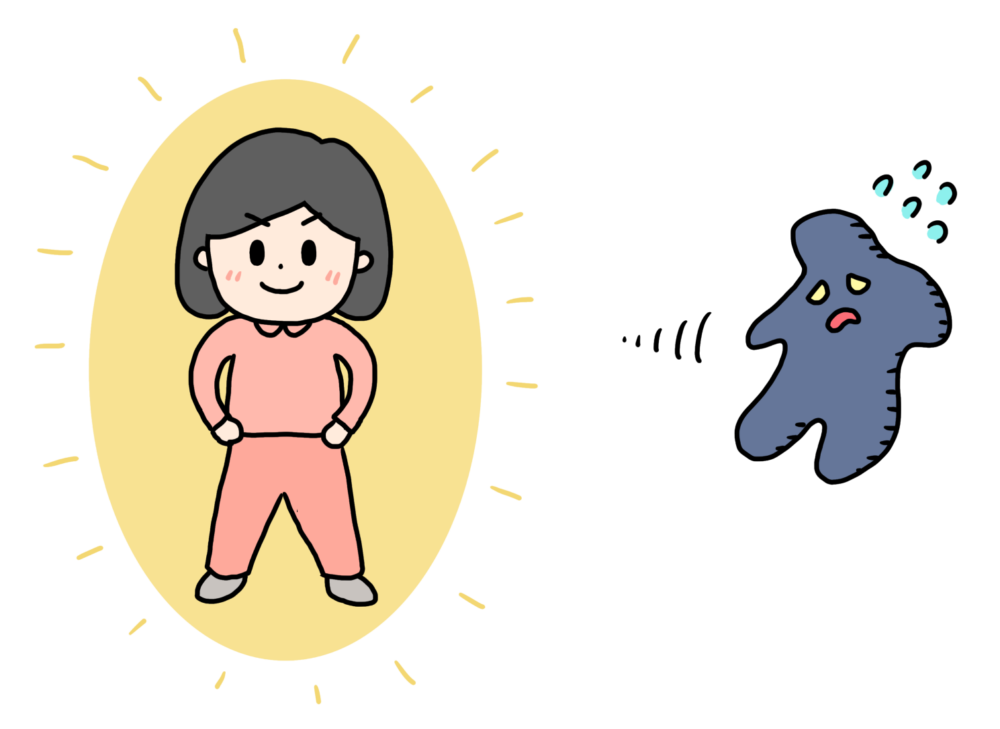
「障害者を馬鹿にする」という行為は、自分自身の劣等感や不安を隠蔽するための防衛機制として働く場合もあります。
障害者を劣った存在とみなすことで、相対的に自分の優位性を確認し、自尊心を保とうとする心理が働くのです。
また、社会の中で自分の居場所を見つけられない人が、障害者を排除することで、集団への帰属意識を高めようとするケースも考えられます。
| 心理メカニズム | 具体的な例 |
|---|---|
| 可視化されるものとされないもの | 外見からは分かりにくい発達障害や精神障害への理解不足からくる偏見 |
| 恐怖と不安の投影 | 自分も同じような境遇になるかもしれないという不安から障害者を遠ざける |
| 自分を守るための防衛機制 | 障害者を劣った存在とみなすことで自尊心を保とうとする |
これらの心理メカニズムは複雑に絡み合い、「障害者を馬鹿にする」という行動につながります。
重要なのは、これらの心理が誰にでも潜んでいる可能性があることを認識し、自分自身の無意識の偏見と向き合うことです。
社会構造が生み出す「障害者を馬鹿にする」土壌
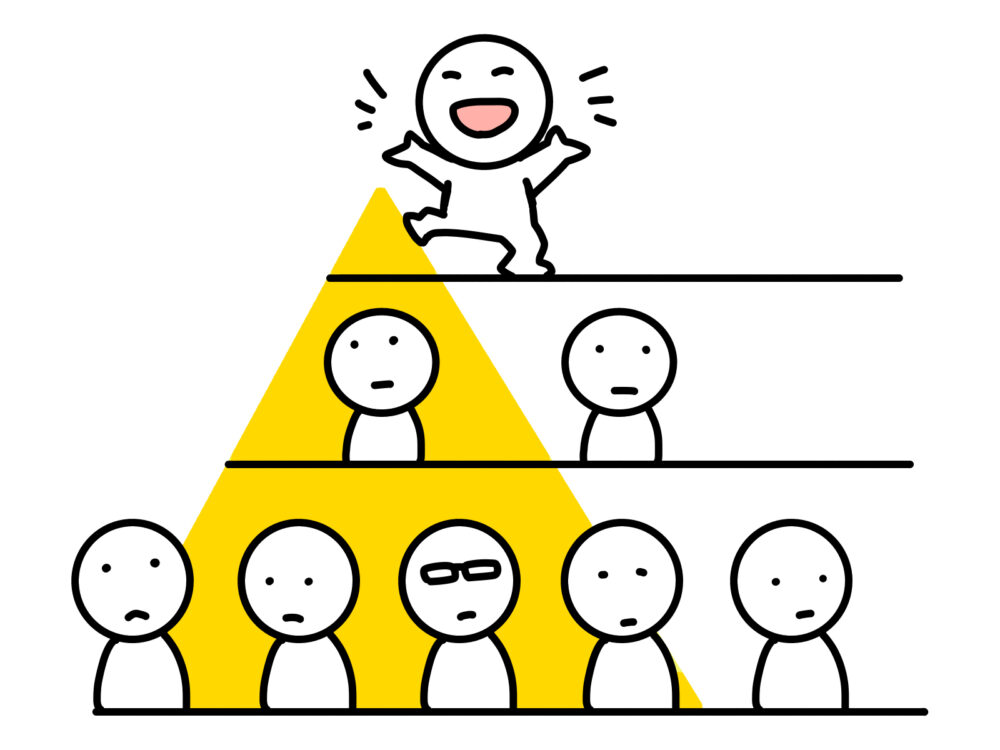
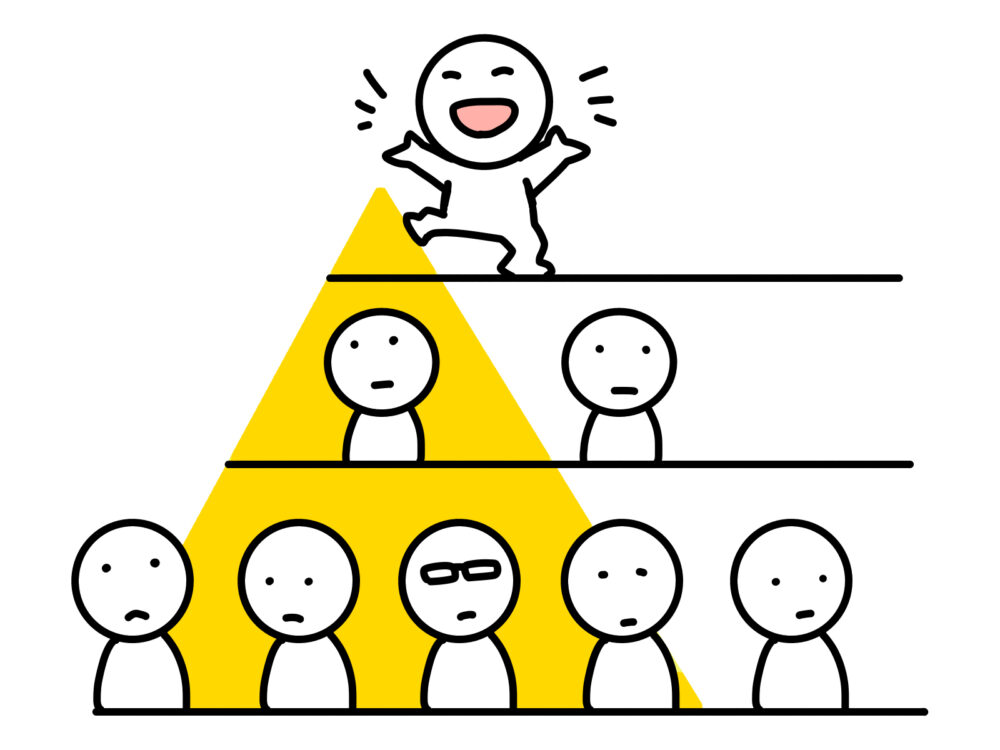
障害者を馬鹿にする言動は、個人の問題にとどまらず、社会構造そのものが差別を生み出す土壌となっている側面があります。
社会の様々なシステムや慣習が、無意識のうちに差別を助長し、固定化させている可能性について考えてみましょう。
メディアの偏向報道とステレオタイプ
メディアは、社会の共通認識を形成する上で大きな影響力を持っています。
しかし、過去には障害者を特定のイメージで描く偏向報道や、ステレオタイプを強化するような表現が用いられてきた歴史があります。
例えば、障害者を
- 「かわいそう」
- 「不幸」
といった紋切り型のイメージで描くことで、真の理解を阻害し、偏見を助長する可能性があります。
また、感動ポルノと呼ばれるような、障害者の困難を克服するストーリーのみを強調する報道も、障害者の多様な生き方を無視し、ステレオタイプを強化する危険性があります。



近年では、多様性を尊重する報道が増えてきていますが、依然として注意が必要です。
教育現場におけるインクルーシブ教育の遅れ
インクルーシブ教育とは、障害のあるなしに関わらず、すべての子どもが共に学ぶ教育システムです。
しかし、日本のインクルーシブ教育は、未だ発展途上であり、多くの課題を抱えています。
例えば、特別支援学校と普通学校の分離、特別支援学級における十分な支援体制の不足、教員の専門知識の不足などが挙げられます。
インクルーシブ教育が遅れていることで、子どもたちは幼い頃から障害者と接する機会が少なくなり、相互理解が深まりにくいため、偏見や差別意識が形成されやすくなります。
また、障害のある子どもたちが社会から隔離されることで、社会参加への意欲を阻害する可能性も懸念されます。
雇用における差別と機会の不平等
障害者雇用促進法は、企業に障害者の雇用を義務付けていますが、法定雇用率を達成できていない企業も多く、障害者の雇用を取り巻く状況は依然として厳しいのが現状です。
また、雇用されても、単純作業や補助的な業務に限定されるなど、能力に見合った仕事に就けないケースも少なくありません。
さらに、昇進や昇給においても差別的な扱いを受けるなど、機会の不平等が根強く残っています。
このような状況は、障害者の経済的自立を阻害し、社会参加を困難にするだけでなく、自己肯定感を低下させ、社会から疎外されているという意識を強める可能性があります。
| 社会構造の課題 | 具体的な問題点 | 改善に向けた取り組み |
|---|---|---|
| メディア | 偏向報道、ステレオタイプな表現 | 多様性を尊重した報道、障害者への取材における配慮 |
| 教育 | インクルーシブ教育の遅れ、支援体制の不足 | 特別支援教育の充実、教員の研修、合理的配慮の提供 |
| 雇用 | 法定雇用率の未達成、機会の不平等 | 企業への啓発活動、障害者雇用の促進、合理的配慮の提供 |
これらの社会構造上の問題は複雑に絡み合い、障害者を馬鹿にする言動の温床となっています。真の共生社会を実現するためには、これらの問題を一つ一つ解決していく必要があります。
歴史的背景から見る障害者差別


障害者に対する差別は、現代社会特有の問題ではなく、長い歴史の中で様々な形で存在してきました。
その背景には、社会の価値観や思想、制度などが複雑に絡み合っています。
歴史的背景を理解することは、現代の差別問題を解決するための重要な手がかりとなります。
優生思想と社会ダーウィニズム
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、優生思想が世界的に広まりました。
これは、遺伝的に「優れている」とされる人種や階級を増やし、「劣っている」とされる人種や階級を減らすべきだという考え方です。
障害のある人は「劣っている」とされ、断種や隔離の対象となりました。
この法律は、1996年に優生保護法に改正されるまで、長期間にわたって障害者差別の根拠として利用されました。
社会ダーウィニズムは、生物の進化論を社会現象に適用した考え方で、「適者生存」の原理に基づき、社会的に弱い立場の人々は淘汰されるべきだと主張されました。
この思想もまた、障害者差別を正当化する根拠として用いられました。
隔離政策と社会からの排除
歴史的に、障害のある人は社会から隔離されることが多くありました。
精神障害のある人は精神病院に収容され、身体障害のある人は施設に入れられるなど、社会参加の機会が奪われていました。
このような隔離政策は、障害のある人を社会から見えなくし、差別を助長する結果となりました。
ハンセン病患者に対する隔離政策は、特に過酷なものでした。
彼らは療養所への強制収容を強いられ、社会から完全に隔離されました。
この政策は、ハンセン病に対する偏見や差別を深刻化させ、患者の人権を著しく侵害しました。
差別の歴史を学ぶ重要性
過去の障害者差別を学ぶことは、現代社会における差別をなくすために不可欠です。
歴史を振り返ることで、差別がどのように生まれ、どのような影響を与えてきたのかを理解することができます。
また、過去の過ちを繰り返さないためにも、歴史から学ぶ姿勢が重要です。
差別をなくすためには、一人ひとりが過去の事実を認識し、差別解消に向けて行動していく必要があります。
| 時代 | 出来事 | 影響 |
|---|---|---|
| 1940年 | 国民優生法制定 | 障害者への強制断種 |
| 1948年 | 優生保護法への改正 | 断種手術の対象拡大 |
| 1996年 | 母体保護法への改正 | 優生手術に関する条項削除 |
上記以外にも、
- 近世以前の障害者に対する差別や偏見
- 生活の実態
- 宗教観との関連性
- 福祉の始まり
- 近代における障害者福祉の進展
- パラリンピックの歴史
なども学ぶことで、より深く障害者差別について理解を深めることができます。



様々な資料や書籍を通して、歴史的背景を学び、多角的な視点を持つことが重要です。
障害者を馬鹿にする言動がもたらす影響
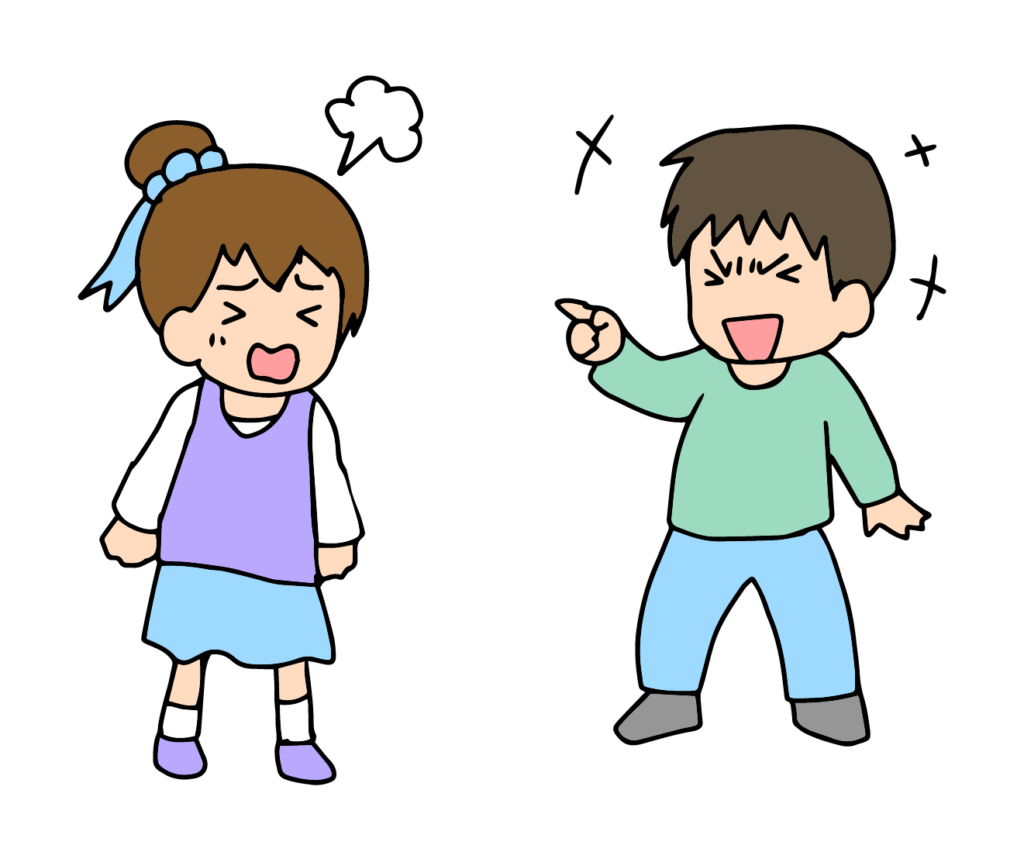
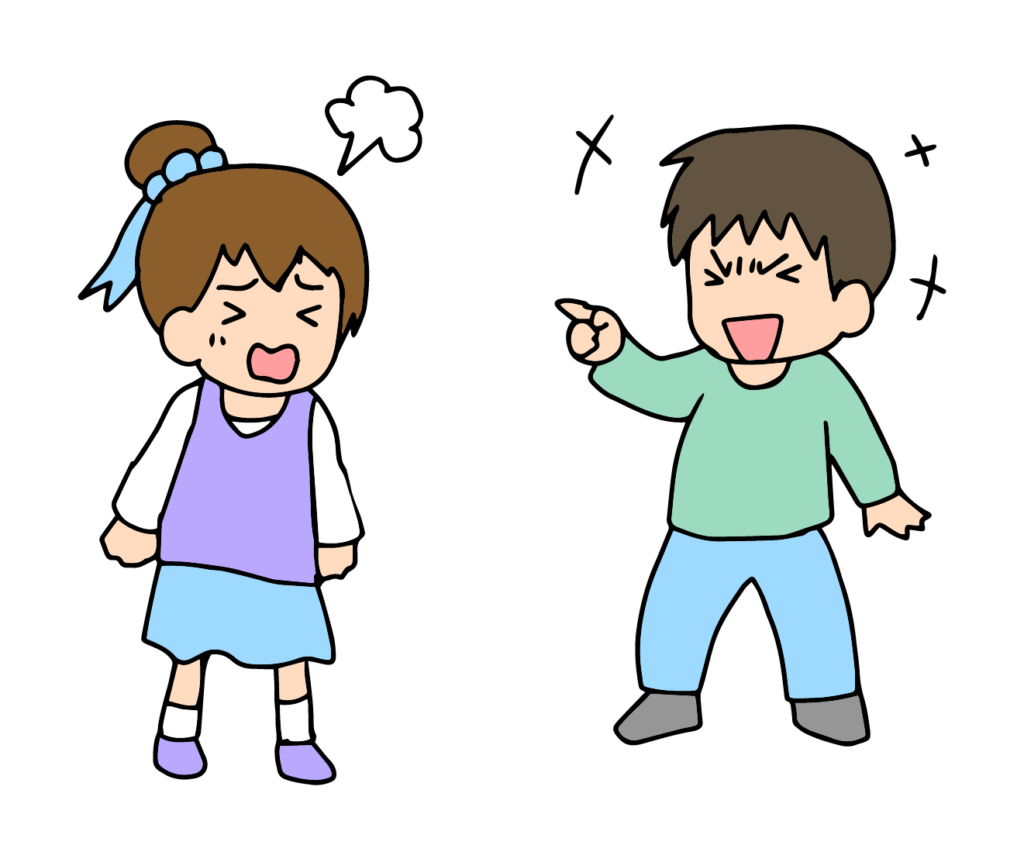
障害者を馬鹿にする言動は、様々な形で深刻な影響をもたらします。それは、直接的な被害を受ける障害者だけでなく、社会全体にも及ぶ深刻な問題です。
障害者への精神的苦痛
心無い言葉や態度は、障害者にとって大きな精神的苦痛となります。
自己肯定感の低下や、不安、抑うつ状態を引き起こす可能性があり、日常生活にも支障をきたすこともあります。
特に、発達障害のある人は、他者の言葉や態度に敏感な場合が多く、より深刻な影響を受ける可能性があります。
また、インターネット上での誹謗中傷も、深刻な精神的苦痛を与えます。
トラウマとなる可能性
一度受けた心の傷は、トラウマとして長く残り続ける可能性があります。
過去の辛い経験がフラッシュバックしたり、特定の人や場所を避けるようになったりするなど、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に、幼少期に受けた差別や偏見は、人格形成にも影響を与える可能性があります。
社会参加への阻害
障害者を馬鹿にする言動は、障害者の社会参加を阻害する大きな要因となります。
外出を控えたり、社会活動への参加を諦めたりするなど、社会から孤立してしまう可能性があります。
| 場面 | 影響 |
|---|---|
| 就職活動 | 面接で差別的な質問を受けたり、採用を断られたりするなど、就職の機会が奪われる可能性があります。 |
| 教育現場 | いじめに遭ったり、授業に参加しづらくなったりするなど、学習の機会が損なわれる可能性があります。 |
| 地域社会 | 地域活動への参加をためらったり、孤立してしまう可能性があります。 |
社会全体の分断
障害者を馬鹿にする風潮は、社会全体の分断を招きます。障害者への理解が深まらず、共生社会の実現が阻害される可能性があります。
また、差別や偏見が蔓延する社会は、すべての人にとって生きづらい社会と言えるでしょう。
多様性の喪失
誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、多様性を認め、互いを尊重することが重要です。
障害者を排除するような言動は、社会の多様性を損ない、活力を失わせることに繋がります。
様々な個性や能力を持つ人が活躍できる社会こそが、真に豊かな社会と言えるでしょう。
人権意識の低下
障害者を馬鹿にする行為は、人権侵害にあたります。このような行為を容認することは、社会全体の人権意識の低下に繋がりかねません。
すべての人々が、等しく人権を尊重される社会を実現するためには、障害者差別を根絶するための努力が必要です。
「障害者を馬鹿にする」言動をなくすために私たちができること
障害者を馬鹿にする言動をなくすためには、社会全体で意識を変革していく必要があります。
私たち一人ひとりができることを考え、実践していくことが重要です。
自分自身の偏見を認識する
まず、自分自身の中に潜む無意識の偏見に気づくことが大切です。
私たちは知らず知らずのうちに、メディアや周囲の影響を受けて偏見を持っている可能性があります。
- 障害者と接した時の自分の感情を意識する
- 障害者に関する情報に触れた際の自分の反応を振り返る
- ステレオタイプなイメージにとらわれていないか確認する
偏見に気づいたらどうすれば良いか
偏見に気づいたら、それを否定したり抑え込もうとするのではなく、なぜそのような偏見を持っているのかを深く掘り下げて考えることが重要です。
過去の経験や周囲の環境が影響している可能性もあります。



自分自身と向き合い、偏見の根本原因を探ることで、意識を変革していく第一歩を踏み出せます。
正しい知識を身につける
障害についての正しい知識を身につけることも重要です。
障害の種類や特性、社会における現状などを理解することで、偏見や誤解を解消し、適切な対応ができるようになります。
- 書籍やウェブサイトで障害に関する情報を収集する
- 講演会やセミナーに参加する
- 障害当事者団体が発信する情報に耳を傾ける
- NHKハートネットTVなどの番組を視聴する
障害者と共生する社会の実現に向けて
障害者と共生する社会を実現するためには、私たち一人ひとりが積極的に行動していく必要があります。
日常生活の中で、以下のような行動を心がけましょう。
| 行動 | 具体例 |
|---|---|
| 困っている人がいたら声をかける | 電車内で車椅子の方が乗車する際に、周りの人に協力を呼びかける |
| 配慮を必要とする人がいることを意識する | エレベーターのボタンを押す際に、視覚障害者の方のために音声案内を確認する |
| 障害者と接する機会を増やす | 地域のイベントやボランティア活動に参加する |
| 障害者差別を許さない姿勢を示す | SNSなどで差別的な発言を見かけた際には、毅然とした態度で反論する |
| 合理的配慮の提供を促す | 職場や学校で、障害のある人が働きやすい、学びやすい環境づくりを提案する |
| 政治や行政に関心を持ち、積極的に意見を表明する | 障害者福祉に関する政策や制度について、自分の意見を伝える |
これらの行動は、小さな一歩かもしれませんが、社会全体を変える大きな力となります。
私たち一人ひとりが意識を変え、行動することで、誰もが生きやすい、共生社会の実現に貢献できるはずです。
インターネットにおける「障害者を馬鹿にする」問題
インターネットの普及は情報アクセスを容易にし、多様な意見交換を可能にする一方で、障害者に対する誹謗中傷や差別的な言動を増幅させる温床にもなっています。
匿名性の高い環境や情報拡散の速さといった特性が、現実世界では表出しにくい悪意を助長し、深刻な問題を引き起こしています。
匿名性による誹謗中傷の増加
インターネット上では、匿名で活動することが容易であるため、現実世界では抑圧されている差別意識が表面化しやすく、障害者を標的にした心ない言葉や誹謗中傷が後を絶ちません。
匿名の掲示板やSNS、動画サイトのコメント欄などが、こうした誹謗中傷の温床となっています。
実名での活動が主流の場と比較して、匿名環境では責任感が希薄になり、加害行為に対する心理的ハードルが下がってしまうことが要因の一つと考えられます。
また、一度書き込まれた誹謗中傷は瞬時に拡散され、被害者の目に触れる可能性が高く、精神的な苦痛を与えるだけでなく、社会生活にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
法律と制度から考える障害者差別


障害者に対する差別は、倫理的に許されないだけでなく、法的に禁じられています。
日本では、障害者に対する差別を解消し、社会参加を促進するための様々な法律や制度が整備されています。
この章では、それらの概要と課題、そして更なる法整備の必要性について解説します。
障害者差別解消法とその課題
2016年4月に施行された障害者差別解消法は、障害を理由とする差別を禁止し、合理的配慮の提供を義務付ける画期的な法律です。
行政機関だけでなく、民間事業者にも差別解消のための措置を講じる義務を課しています。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 不当な差別的取扱い | 障害を理由とする不利益な取扱い | 障害を理由とした入店拒否、解雇など |
| 合理的配慮の不提供 | 障害者が社会生活を送る上で必要な配慮を怠ること | 車いす利用者へのスロープ設置の拒否、聴覚障害者への情報保障の不足など |
障害者差別解消法における合理的配慮の具体例
- 聴覚障害のある人に対して:手話通訳、要約筆記、筆談など
- 視覚障害のある人に対して:点字資料、音声案内、誘導など
- 肢体不自由のある人に対して:スロープの設置、エレベーターの設置、移動の介助など
- 知的障害のある人に対して:わかりやすい説明、情報の提供方法の工夫、意思決定支援など
- 精神障害のある人に対して:休憩時間の確保、柔軟な勤務時間の調整、精神的なサポートなど
障害者差別解消法の課題と改善策
- 合理的配慮の範囲の曖昧さ:ガイドラインの充実、事例集の作成など
- 罰則規定の不在:実効性を高めるための罰則導入の検討
- 相談体制の不備:相談窓口の周知徹底、相談員の専門性向上など
- 事業者への周知不足:研修の実施、啓発活動の強化など
合理的配慮の提供
合理的配慮とは、障害者が他の者と平等に社会生活を送ることができるよう、それぞれの障害特性に応じて、負担になりすぎない範囲で必要かつ適切な変更・調整を行うことです。
具体的には、設備の改修、サービス内容の変更、情報提供方法の工夫などが挙げられます。合理的配慮の提供は、障害者差別解消法において義務付けられています。
合理的配慮提供の具体例
- 物理的環境の整備:スロープ、エレベーター、点字ブロック、音声案内装置の設置など
- 情報提供方法の工夫:点字、音声、手話、字幕、拡大文字の使用など
- 時間の配慮:休憩時間の延長、柔軟な勤務時間の設定など
- 手続きの簡素化:代理人による手続きの許可、書類の簡略化など
更なる法整備の必要性
障害者差別解消法は大きな前進ですが、更なる法整備が必要とされています。
例えば、差別を未然に防ぐための予防措置の義務化、差別を受けた場合の救済措置の強化などが検討されています。
また、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備も重要な課題です。
国際的な視点を取り入れながら、より包括的な法整備を進める必要があります。
障害者権利条約の国内法整備
障害者権利条約は、障害のある人が人権を十分に享受できる社会の実現を目指した国際条約です。
日本は2014年に批准しましたが、条約の理念を国内法に反映させるための更なる法整備が求められています。
今後の法整備の方向性
- 差別禁止規定の強化:間接差別、複数根拠に基づく差別への対応など
- 合理的配慮の義務付けの明確化:提供基準の明確化、合理的配慮提供計画の策定など
- 救済措置の充実:紛争解決手続きの整備、損害賠償制度の確立など
- モニタリング体制の強化:独立した監視機関の設置、定期的な調査の実施など
障害者を取り巻く社会環境は常に変化しており、法律や制度もそれに合わせて進化していく必要があります。
私たちは、障害者の人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、共に努力していく必要があります。
まとめ
「障害者を馬鹿にする」言動は、無意識の偏見や社会構造、歴史的背景などが複雑に絡み合って生じる深刻な問題です。インターネット上での誹謗中傷も増加しており、障害者への精神的苦痛や社会参加の阻害につながります。
自分自身の偏見を認識し、正しい知識を身につけることで、障害者差別解消法の理念に基づき、共生社会の実現に向けて一人ひとりが行動していく必要があります。
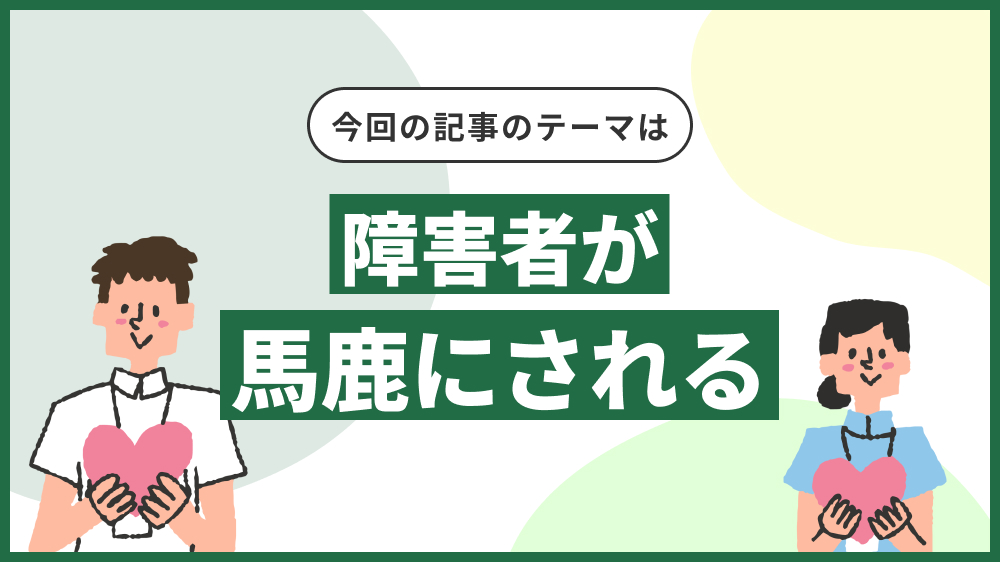

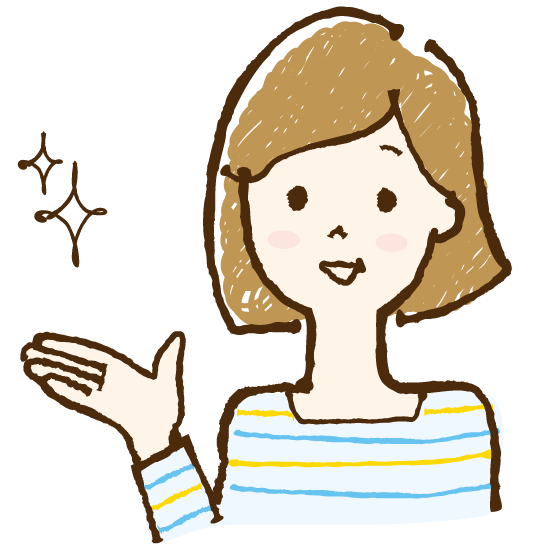








コメント