幼稚園の盗撮は、園と家庭の連携で防げます。
本記事では、保護者が園に確認すべき7つのチェックリストや家庭でできる防犯教育を解説。
わが子を危険から守るための具体的な方法がすべてわかります。
増加する幼稚園での盗撮 その巧妙な手口とは

大切なお子さまを預ける幼稚園。
安全な場所であるはずの園で、子どもたちを狙った卑劣な盗撮事件が後を絶たないという現実をご存知でしょうか。
犯行は外部の不審者によるものだけでなく、関係者を装って園内に侵入するなど、その手口は年々巧妙化・悪質化しています。
運動会や発表会など行事での盗撮リスク
子どもたちの成長した姿を見られる運動会や発表会、お遊戯会などの行事は、保護者にとって大きな楽しみの一つです。
しかし、多くの人が集まり、誰もがカメラやスマートフォンを構える状況は、盗撮犯にとって紛れ込みやすい絶好の機会となってしまいます。
保護者や関係者のふりをして紛れ込んだり、園の外部から高性能なカメラで狙ったりと、さまざまな手口が想定されます。
| 手口の種類 | 具体的な行動 | 危険なポイント |
|---|---|---|
| 保護者を装った侵入・撮影 | 保護者になりすまし、他の保護者に混じって堂々と敷地内に入り、ビデオカメラやスマートフォンで撮影する。 | 人の出入りが多いため、受付や名札での本人確認が甘いと簡単に見分けがつかず、不審な撮影行為も目立ちにくい。 |
| 望遠レンズによる園外からの盗撮 | 園のフェンスや壁の外、近隣のマンションのベランダや公園などから、高性能な望遠レンズ付きカメラで園内の様子を狙う。 | 園の敷地外からの犯行であるため、職員や保護者が気づきにくく、発見が遅れる可能性がある。 |
| 小型カメラの悪用 | ペン型、ボタン型、メガネ型、腕時計型などのカモフラージュされた小型カメラを使用し、気づかれないように子どもたちの姿を撮影する。 | 撮影していること自体が周囲から全く分からず、至近距離での悪質な撮影につながる危険性が高い。 |
| スマートフォンでの巧妙な撮影 | 通話やゲームをしているふりをしながら、カメラを子どもたちに向ける。 一見すると普通のスマートフォン操作に見えるため、不審に思われにくい。 | 誰もが持っている機器であるため警戒されにくく、着替えやトイレの近くなど、無防備な瞬間を狙われるリスクがある。 |
日常の保育に紛れ込む盗撮の危険性
盗撮のリスクは、特別な行事の日に限りません。
園児たちが園庭で遊んでいたり、お散歩に出かけたりする日常の保育時間にも、危険は潜んでいます。
配送業者や設備点検業者、ボランティアなどを装って園内に侵入したり、園の死角に隠しカメラを設置したりする悪質なケースも報告されています。
| 手口の種類 | 具体的な行動 | 危険なポイント |
|---|---|---|
| 関係者を装った園内への侵入 | 宅配業者や工事業者、自治体の職員などを装い、インターホンを鳴らして園内に入る。 目的の場所以外をうろつき、撮影の機会をうかがう。 | 職員が多忙な時間帯などを狙われると、身分証明の確認がおろそかになり、侵入を許してしまう可能性がある。 |
| 隠しカメラの設置・回収 | 園児が使うトイレや更衣室、お昼寝の部屋、遊具の死角など、人目につきにくい場所に超小型カメラを事前に設置し、後日回収しに来る。 | 犯行が極めて発覚しにくく、最もプライベートな空間が標的になるため、子どもたちの心身に深刻な被害を及ぼす。 |
| フェンス越しなど外部からの盗撮 | 園児が園庭で遊んでいる時間帯を狙い、園のフェンスや生け垣の隙間からスマートフォンやカメラで撮影する。 | 短時間で犯行が行われることが多く、不審な人物がいても「子ども好きな人かな」と見過ごされてしまうことがある。 |
| ドローンによる上空からの撮影 | 園の上空にドローンを飛行させ、園庭や、場合によっては窓から教室内の様子を撮影する。 | 比較的新しい手口であり、騒音で気づくこともあるが、誰がどこから操作しているのか特定が困難。 |
 編集長
編集長これらの手口を知ることは、保護者として園の安全対策をチェックする上での重要な視点となります。
【保護者向け】幼稚園の盗撮を防ぐための7つのチェックリスト


わが子を盗撮の危険から守るためには、幼稚園任せにするのではなく、保護者自身が主体的に関わり、園の安全対策を確認することが不可欠です。
しかし、具体的に何をどうチェックすれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、保護者の視点から幼稚園の盗撮防止対策を確認するための、今すぐできる7つのチェックリストをご紹介します。
幼稚園の防犯カメラ設置状況と運用ルールを確認する
防犯カメラは、不審者の侵入や盗撮行為を抑止する効果が期待できるだけでなく、万が一の際の重要な証拠となります。
しかし、ただ設置されていれば安心というわけではありません。
その運用ルールが適切に定められ、遵守されているかを確認することが重要です。



園の見学や個別面談、保護者会などの機会に、以下の点について質問してみましょう。
| チェック項目 | 確認したい具体的な内容 |
|---|---|
| 設置場所と範囲 | 正門、裏口、園庭、廊下など、不審者が侵入しやすい場所や子どもの活動エリアをカバーできているか。 トイレや更衣室など、プライバシーを侵害する可能性のある場所が映り込んでいないか。 |
| 録画と保存期間 | カメラは24時間作動しているか。 録画データの保存期間はどのくらいか(警察への相談などを考慮すると、最低でも1ヶ月以上が望ましい)。 |
| 管理・運用ルール | 誰が映像を管理し、どのような場合に閲覧できるのか。 閲覧の際の申請手続きや記録は適切に行われているか。 個人情報保護の観点から、厳格なルールが定められているかを確認します。 |
職員や業者など外部の人の入退室管理は徹底されているか
盗撮は、必ずしも園の外部から行われるとは限りません。
業者や関係者を装って侵入するケースも考えられます。
そのため、外部の人の入退室管理が厳格に行われているかは、非常に重要なチェックポイントです。
- 保育時間中、門は施錠されているか(オートロックや電子錠が望ましい)。
- 来訪者はインターホンで用件と身元を確認してから入室を許可しているか。
- 給食や教材の納入業者、施設のメンテナンス業者などが出入りする際、名札の着用や入退室記録簿への記入、職員の付き添いなどが義務付けられているか。
- 保護者であっても、送迎時間外に園内に入る際の手続きは明確になっているか。
行事における撮影ルールは明確になっているか
運動会や発表会、お遊戯会といった行事は、多くの保護者や関係者が集まるため、盗撮犯が紛れ込みやすい機会でもあります。
楽しい思い出を残すための撮影が、思わぬトラブルに発展しないよう、園が明確な撮影ルールを設けているかを確認しましょう。
保護者会や行事前のお便りなどで、以下のルールが周知されているかチェックしてください。
| ルールの種類 | 確認したい具体的な内容 |
|---|---|
| 撮影許可とエリア | 撮影者を示すための許可証(ネックストラップなど)を配布しているか。 撮影可能なエリアが指定されているか。 |
| 機材の制限 | 過度な望遠レンズや、周囲の迷惑となる大型三脚の使用を制限しているか。 |
| SNS等への投稿 | 撮影した写真や動画をSNSや動画サイトへ投稿することに関するルール(原則禁止、限定公開の徹底など)が明確に定められ、周知されているか。 |
| 違反者への対応 | ルールを守らない人に対して、職員が注意や声かけを行う体制が整っているか。 |
先生や職員の防犯意識と研修体制をヒアリングする
どんなに優れた設備やルールがあっても、それを運用する先生や職員の防犯意識が低ければ意味がありません。
子どもたちと最も長く接する職員の意識と知識こそが、最大の防御壁となります。
園長先生や主任の先生との面談の際に、少し踏み込んで質問してみるのも良いでしょう。
- 保育時間中、門は施錠されているか(オートロックや電子錠が望ましい)。
- 来訪者はインターホンで用件と身元を確認してから入室を許可しているか。
- 給食や教材の納入業者、施設のメンテナンス業者などが出入りする際、名札の着用や入退室記録簿への記入、職員の付き添いなどが義務付けられているか。
- 保護者であっても、送迎時間外に園内に入る際の手続きは明確になっているか。
トイレや更衣室など死角になる場所の安全対策は十分か
トイレやお昼寝・お着替えのスペースは、子どものプライバシーが特に守られるべき場所であり、盗撮のターゲットにされやすい危険なエリアでもあります。
こうした死角になりがちな場所の安全対策が十分に行われているかを確認しましょう。
保護者が直接立ち入ることが難しい場所も多いため、園の設備や保育方針についてヒアリングすることが中心になります。
- お着替えは、他の子や外部から見えないよう、パーテーションで区切ったり、専用の部屋で行ったりする配慮があるか。
- トイレの個室のドアや壁に不審な穴や傷がないか、職員が定期的に点検しているか。
- 窓に目隠しフィルムを貼る、植栽で遮るなど、外部からのぞき見を防ぐ工夫がされているか。
- 職員の目が届きにくい場所に、定期的に巡回するなどのルールはあるか。
保護者同士の連携と情報共有の仕組みはあるか
園の安全は、園と保護者が一体となって守るものです。
保護者同士が連携し、情報を共有する仕組みが整っていると、防犯のネットワークはより強固になります。
「保護者の目」を増やすための仕組みがあるか、確認してみましょう。
- 園からの不審者情報や注意喚起が、メール配信システムや専用アプリなどで迅速に全保護者に共有される体制があるか。
- 保護者会やクラス懇談会などで、地域の安全に関する情報交換を行う機会が設けられているか。
- PTAや保護者会が主体となった、登降園時の見守り活動や防犯パトロールなどが実施されているか。
園周辺の環境や不審者情報の共有体制を確認する
盗撮のリスクは園の中だけではありません。
登降園の道中や、園の周囲も危険が潜むエリアです。
園が周辺環境のリスクを把握し、地域と連携して対策を講じているかを確認しましょう。
- 園のフェンスや壁の外に、死角となる公園の茂みや建物の陰、駐車場などがないか。ある場合、園としてどのような対策(巡回強化、防犯カメラの設置角度の工夫など)を講じているか。
- 近隣で発生した不審者情報などを、警察や地域コミュニティから入手し、速やかに保護者へ共有する体制が整っているか。
- 地域の防犯ボランティアやこども110番の家などと連携しているか。
- 送迎バスを利用している場合、バス停の場所は安全か、乗降時の職員の対応は適切か。
家庭でできること 子ども自身の身を守る力を育む


幼稚園でのセキュリティ対策は非常に重要ですが、それだけでは万全とは言えません。
巧妙化する盗撮などの犯罪からわが子を守るためには、子ども自身が「自分の身を守る力」を身につけることが不可欠です。
家庭での日々のコミュニケーションを通じて、子どもが危険を察知し、適切に行動できるための土台を育んでいきましょう。
「いやだ」と言える勇気を教える
子どもが自分の気持ちや違和感を正直に表現できることは、性被害を含むあらゆる危険から身を守るための第一歩です。
自分の意思をはっきりと伝える「自己表現力」を育むことが、子どもの安全を守る盾となります。
大切なのは、相手が誰であっても、自分が「いやだ」と感じたときには、その気持ちを尊重し、声に出して良いのだと教えることです。
- 日常会話での実践:
「今日の給食、苦手なものがあったの?」「そのお洋服、チクチクして嫌だった?」など、子どもの些細な「いやだ」という気持ちを肯定的に受け止め、「そう感じたんだね。教えてくれてありがとう」と伝える習慣をつけましょう。
- ロールプレイング(ごっこ遊び):
人形などを使って、「お友達におもちゃを無理やり取られそうになったら、なんて言う?」「知らない人に『こっちにおいで』と言われたらどうする?」といった具体的な場面を想定し、「いやだ!」「やめて!」と言う練習を遊び感覚で取り入れます。
- 親が手本を示す:
親自身が無理な頼み事をされた時に、相手を尊重しつつも断る姿を見せることも、子どもにとって良い学びになります。



子どもが「いやだ」と伝えてきたときは、その理由を問いただす前に、まずはその勇気を褒め、「あなたの気持ちが一番大切だよ」と安心させてあげることが、親子の信頼関係を深め、いざという時の相談しやすさにも繋がります。
プライベートゾーンの大切さを伝える
盗撮は、子どもの尊厳を傷つける深刻な性加害です。
自分の体の大切な部分(プライベートゾーン)について正しく理解し、それを他者から守る意識を持つことは、子どもを性的な被害から守る上で極めて重要です。
このテーマはデリケートですが、決して隠したり避けたりせず、子どもの発達段階に合わせて、明るく、分かりやすい言葉で伝えることが大切です。



「水着で隠れる場所」という表現は、多くの子どもにとって理解しやすいでしょう。
プライベートゾーン教育の4つのルール
ご家庭でプライベートゾーンについて話す際は、以下の4つのルールを基本にすると分かりやすく伝えられます。
| ルール | 具体的な伝え方の例 |
|---|---|
| 1. 場所を知る | 「お口、お胸、おしり、おちんちん(パンツの中)は、あなただけの大切な場所(プライベートゾーン)だよ。水着で隠れるところだね。」 |
| 2. 見せない・さわらせない | 「この大切な場所は、他の人に見せたり、さわらせたりしなくていいんだよ。」 |
| 3. 他人のものも見ない・さわらない | 「同じように、お友達や他の人の大切な場所を、あなたが見たりさわったりするのもいけないことだよ。」 |
| 4. いやな気持ちになったら相談する | 「もし誰かに大切な場所をさわられたり、見せてと言われたりして、少しでも『いやだな』『こわいな』と思ったら、すぐにパパやママに教えてね。あなたは何も悪くないからね。」 |
お風呂の時間などを活用し、体を洗いながら「ここは大切な場所だから、きれいにしようね」と自然な形で触れるのも良い方法です。
例外として、お医者さんが診察する時や、保護者がお世話をする時など、プライベートゾーンに触れる必要がある場面についても、「ちゃんと『もしもしするね』って声をかけてからだよね」と説明し、子どもが不安にならないよう配慮しましょう。
不審な人や行動について親子で話し合う
盗撮犯や子どもを狙う犯罪者は、一見して「怪しい」と分かる見た目をしているとは限りません。
そのため、「知らない人にはついていかない」という教えだけでは不十分です。
重要なのは、相手の「見た目」ではなく「行動」に注目し、危険を判断する力を養うことです。
防犯標語「いかのおすし」を合言葉に
子どもが危険な状況に遭遇した際の具体的な行動指針として、警視庁が推奨する防犯標語「いかのおすし」は非常に有効です。
親子で意味を確認し、声に出して練習しておきましょう。
- いか:知らない人についていかない
- の:知らない人の車にのらない
- お:おおごえで助けをよぶ(「助けてー!」と叫ぶ)
- す:すぐにげる
- し:おうちの人にしらせる
ただ暗記させるだけでなく、「どんな時に『助けて』って叫ぶ?」「どこに逃げたらいいかな?」など、具体的なシチュエーションを想定して話し合うことで、子どもの理解が深まります。
地域の安全拠点「こども110番の家」を知っておく
万が一の時に子どもが駆け込める場所として、「こども110番の家」の存在を教えておくことも重要です。
これは、地域の商店や民家などが協力し、子どもが危険を感じた時に保護してくれる制度です。
普段から散歩のついでに、自宅や幼稚園の周辺にある「こども110番の家」のステッカーや旗を親子で一緒に探し、「もし怖いことがあったら、このマークがあるお家に逃げ込んでいいんだよ」と教えておきましょう。
まとめ
幼稚園での盗撮から子どもを守るには、園の対策任せにせず、保護者自身がチェックリストを基に確認することが重要です。
家庭での防犯教育と合わせ、園と保護者が連携し、子どもの安全な環境を築きましょう。
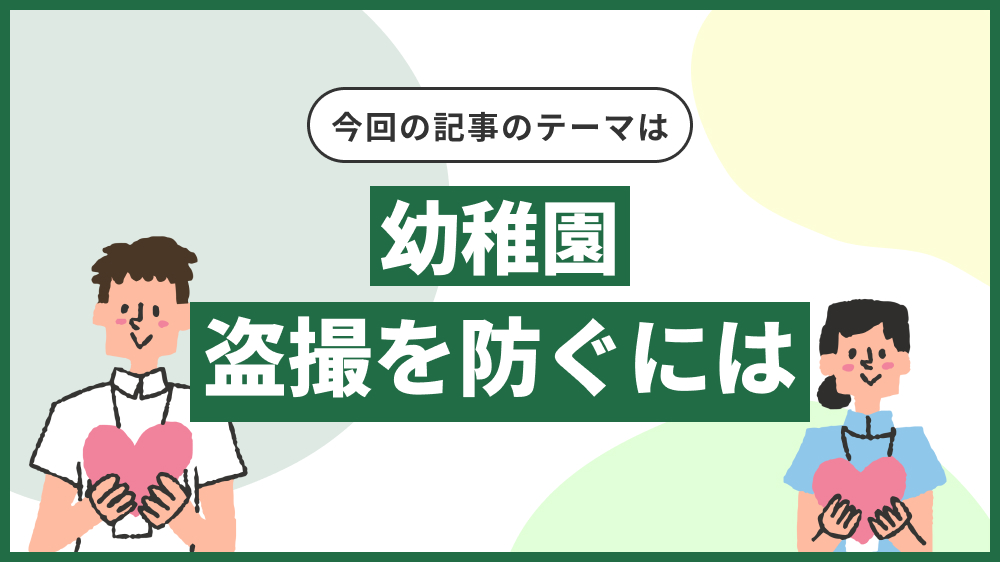









コメント