介護施設の事例
利用者がセラピストから指示され腹を立てた事例
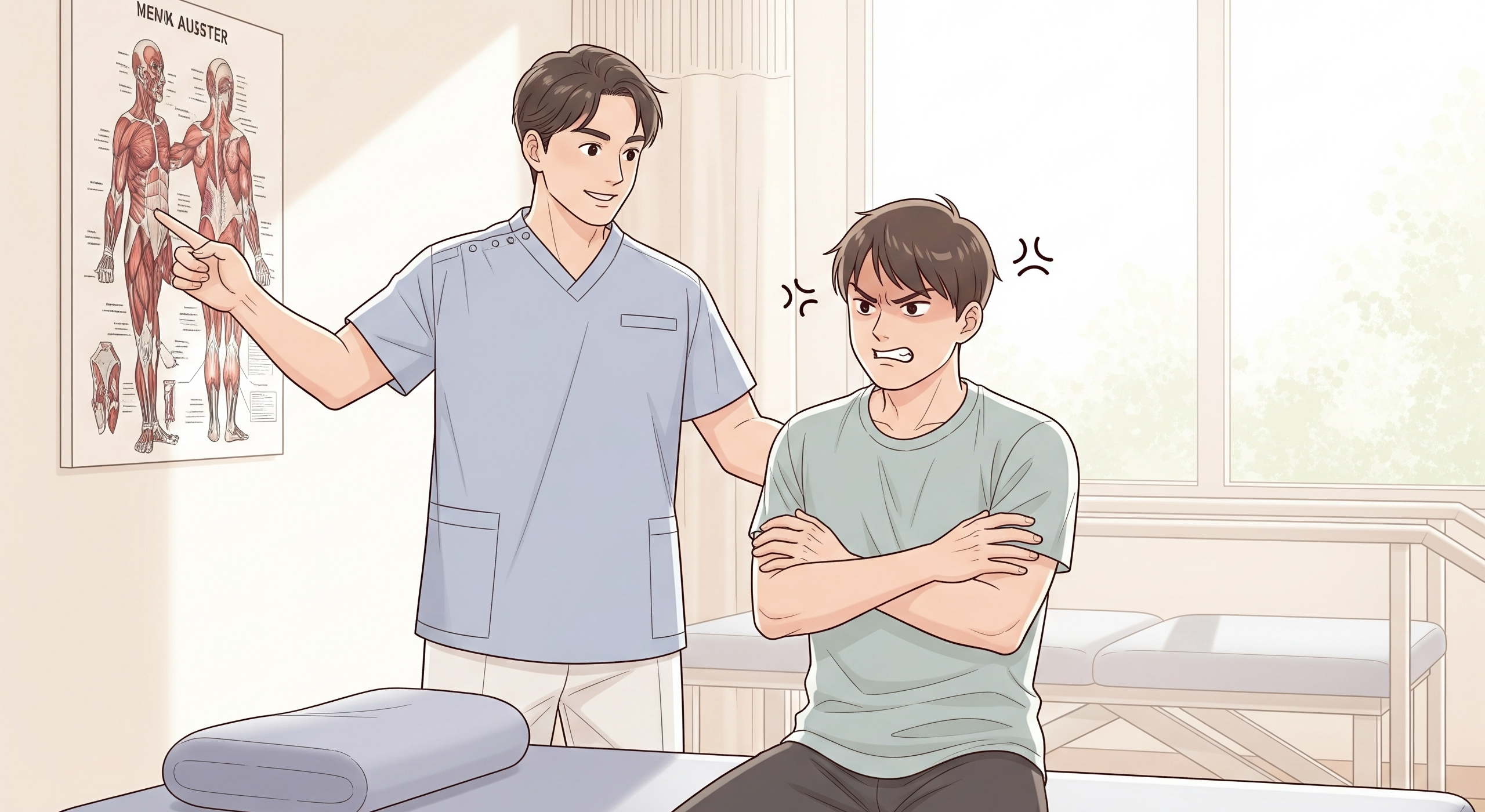
事例データ
投稿者

対応者 理学療法士
性別 男性
お相手

寝たきり度 J1
認知症の状況 Ⅱa
性別 男性
K様は当事業所で1年前からリハビリを受けている方でした。担当のケアマネージャーさんから少し癖があり、自分の考えを否定されるようなことがあると過敏に反応してしまうと、事前情報を頂いておりました。
リハビリを開始し1年程過ぎた頃、当事業所で急な人事異動があり、K様の担当が変更されることになりました。
変更後も通常通り利用されていたのですが、ある日突然担当のケアマネージャーさんから、利用を終了したいとK様が仰っていると話を受けました。

理由としては、セラピストが自分のやっていることに指示をしてきたからというものでした・・・
よかった点
利用者様の意見を聞き、また担当セラピストから話を聞きました。概ね両者の話は一致していましたが、セラピストとしてはK様にアドバイスのつもりで指示をしたということであり、言い方も常識的な範囲内であったため、当事業所としてはK様には相談の上利用を終了していただきました。
今回は職員も自分の責務を全うしただけであり、利用者様も職員の態度に腹を立てたのではなく、自分の行っていることに口を出してほしくないという意見であったため、事業所としては終了を告げて良かったと感じています。

悪かった点としては、人事異動とはいえ急な担当者変更による利用者様の情報共有が十分ではなかった点であり、今後は情報共有を徹底する必要があると感じました。
改善点
今回のケースで言えば自身で様々なトレーニングをしており、またその内容について専門的な意見をあまり必要としていない方であるため、適した期間を設けサービスの卒業を告げるべきであったと感じております。卒業も一方的でなく、利用者様が納得するような形で終了していれば、利用者様も気持ちよく次のステップに進めていたであろうと感じます。
先輩福祉士からのコメント
なぜこのようなことが起きるの?
今回の出来事は、急な担当交代によってK様の大切にしている価値観が十分に伝わらなかったことが背景にあります。
K様は「自分のやり方を尊重してほしい」という気持ちが強く、それが配慮しきれなかったため、助言が否定に感じられてしまったのです。
分析とアドバイスは?
支援の場では、専門的な助言と利用者の自己決定をどう両立させるかが大切です。 担当交代の際には生活習慣や心理的特性まで丁寧に共有し、卒業支援を含めた「次のステップへの準備」を一緒に考えることで、利用者も安心して前へ進むことができます。
参考文献
-
厚生労働省「地域包括ケアにおける多職種連携」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html -
日本社会福祉士会「倫理綱領」
https://www.jacsw.or.jp/about/ethics/ -
独立行政法人福祉医療機構「利用者主体のケアに関する実践事例」
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/
新着の介護事例
関連ワードから探す
- アルバイト(11)
- ケースワーカー(20)
- ケアマネージャー(介護支援専門員)(43)
- サービス提供責任者(61)
- その他(19)
- 介護事務(15)
- 介護助手・介護補助(28)
- 介護福祉士(162)
- 介護職員(249)
- 介護職員(ホームヘルパー)(138)
- 作業療法士(15)
- 支援相談員(25)
- 機能訓練指導員(15)
- 歯科衛生士(2)
- 理学療法士(12)
- 生活支援コーディネーター(3)
- 生活支援員(11)
- 生活相談員(14)
- 相談支援専門員(12)
- 看護学生(1)
- 看護師(45)
- 福祉用具専門相談員(3)
- 管理栄養士・調理スタッフ(3)
- 管理者(施設長・ホーム長)(50)
- 臨床心理士(2)
- 薬剤師(3)
- 言語聴覚士(2)
- 運転手(介護ドライバー)(1)










